【クロロホルム事件】早すぎた構成要件の実現とは?最高裁判例の事案と争点を徹底分析

この記事を読んで理解できること
- クロロホルム事件の事案と争点
- クロロホルム事件の判旨
- 因果関係の錯誤
早すぎた構成要件の実現とは、行為者は第1行為の後で第2行為によって結果を実現しようと計画していたものの、行為者の認識に反して第1行為によって結果が発生した(可能性がある)場合をいいます。
リーディングケースとしては、クロロホルム事件(最決平成16年3月22日)が非常に有名ですが、みなさんはこの事件の事案と争点を瞬時に答えられるでしょうか。
刑法は事案が極めて重要であり、結論だけを覚えていても意味がありません。
そこで今回は、早すぎた構成要件の実現について、クロロホルム事件の事案と争点を詳しく分析した上で、最高裁がどのような判断を下したのかを解説したいと思います。
第1章 クロロホルム事件の事案と争点
クロロホルム事件の事案は以下のとおりです。
(判旨を要約しています)
・クロロホルム事件 最決平成16年3月22日
(事案の概要)
① 被告人Aは、被告人Bに、夫のCの殺害を依頼した。被告人Bは、依頼を引き受け、実行犯3名を仲間に加えた。
② 犯人らは、クロロホルムを使ってCを失神させた上、港まで運び自動車ごと崖から海に転落させてでき死させるという計画を立てた。
③ 実行犯3名は、多量のクロロホルムを染み込ませてあるタオルをCの鼻口部に押し当て、Cを昏倒させた(以下、この行為を「第1行為」という。)。その後、実行犯3名は、Cを約2km離れた港まで運んだ。第1行為の約2時間後、被告人Bが到着し、実行犯3名と共にCを自動車ごと海に転落させた(以下、この行為を「第2行為」という。)。
④ Cの死因は、でき水かクロロホルム摂取に基づくものであるが、いずれであるかは特定できない。Cは、第2行為の前の時点で、第1行為により死亡していた可能性がある。
⑤ 被告人B及び実行犯3名は、第1行為自体によってCが死亡する可能性があるとの認識を有していなかった。しかし、客観的にみれば、第1行為は、人を死に至らしめる危険性の相当高い行為であった。
まとめると、クロロホルム事件の概要は以下のとおりです。
【犯行計画】
Cをクロロホルムで失神させ(第1行為)、自動車ごと海に転落させて(第2行為)溺死させる計画
▼
【実行】
Cをクロロホルムで昏倒させ(第1行為)、自動車ごと海に転落させた(第2行為)。
▼
【後に判明した事実】
Cは、第1行為のクロロホルム摂取により死亡していた可能性がある。
このように、本件は、被告人が第1行為の後で第2行為によって結果を実現しようと計画していたものの、被告人の認識に反して第1行為によって結果が発生した可能性があるという事案です。
次に、本件の上告趣意書を見てみましょう。
・クロロホルム事件 最決平成16年3月22日
(被告人Bの弁護人による上告趣意書)
「被告人Bらの認識としては、クロロホルムを使用するのは被害者を気絶させることのみを目的としているのであって、クロロホルムにより被害者を殺害するという殺人の故意は認められない。従って、クロロホルムを嗅がせる行為そのものについて、殺人の実行行為性を認めることはできないのであるから、殺人罪の実行行為の着手はない。」
「故意の有無は、殺害の目的のための実行に着手した時点で判断されるのであり、規範に直面するだけの認識の有無は、あくまで実行行為時を基準に考えるのである。本件では、仮にクロロホルムを被害者に吸引させたときに、殺害の故意を認定するのであれば、クロロホルムを吸引させる行為が殺人の実行行為であり、この時点で殺害の故意が存在しなければならないことになる。」
このように、弁護人は、
・クロロホルムを嗅がせる行為に実行行為性は認められず、実行の着手がない。
・クロロホルムを嗅がせた時点で殺人の故意は存在しない。
という主張をしました。
つまり、本件の主な争点は、実行の着手と故意の二つです。
ここで、被告人は被害者の殺害を意図していたにもかかわらず、なぜ故意が問題となるのかを解説します。
みなさんは、「同時存在の原則」という言葉はご存知かと思います。
責任能力が争点となる事案で、「実行行為の時点で責任能力があることが必要となる」という趣旨で使われることが多いですよね。
この「同時存在の原則」は、故意においても同様にあてはまります。
つまり、「実行行為の時点で故意があることが必要となる」ということです。
そのため、弁護人は、クロロホルムを嗅がせる行為が実行行為であるならば、その時点で殺人の故意がなければならないと主張したのです。
仮に被害者が第1行為によって死亡した場合、その時点で故意が認められないのであれば、殺人罪は成立しません。
本件では、第1行為と第2行為のどちらで被害者が死亡したのか明らかでないので、第1行為の時点で故意がなければ「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、殺人罪の成立は認められないことになります。
したがって、殺人罪が成立するためには、第1行為の時点で故意が認められる必要があるのです。
ここまで、クロロホルム事件の事案と争点を詳しめに解説しました。
次章では、最高裁がどのような判断を下したのかを解説します。
第2章 クロロホルム事件の判旨
それでは、クロロホルム事件の判旨を見ていきましょう。
・クロロホルム事件 最決平成16年3月22日
(判旨)
「実行犯3名の殺害計画は、クロロホルムを吸引させてCを失神させた上、その失神状態を利用して、Cを港まで運び自動車ごと海中に転落させてでき死させるというものであって、第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。また、実行犯3名は、クロロホルムを吸引させてCを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、たとえ、実行犯3名の認識と異なり、第2行為の前の時点でCが第1行為により死亡していたとしても、殺人の故意に欠けるところはなく、実行犯3名については殺人既遂の共同正犯が成立するものと認められる。」
まとめると、判旨は、
・第1行為は第2行為に密接な行為
▶ 第1行為の時点で実行の着手が認められる。
・一連の殺人行為に着手して目的を遂げた
▶ 殺人の故意に欠けるところはない。
という認定をしました。
ここでいう「密接な行為」、「一連の殺人行為」は、一般的には実行行為の一体性と表現されることが多い概念です。
【実行の着手】
第1行為と第2行為は実行行為の一体性あり
▼
第1行為から第2行為に至る危険性あり
▼
実行の着手が認められる。
【故意】
第1行為と第2行為は実行行為の一体性あり
▼
一連の実行行為により結果が発生する認識があれば足りる
▼
故意が認められる
そして、実行行為の一体性を判断する際には、
・第1行為が第2行為に必要不可欠か
・第1行為の後、第2行為の障害となるような特段の事情があるか
・第1行為と第2行為の時間的場所的近接性
などを考慮することになります。
本件では、
・クロロホルムを吸引させてCを失神させるという第1行為は、Cを車ごと海中に転落させるという第2行為に必要不可欠であった
・第1行為に成功した場合、第2行為の障害となるような特段の事情は存在しない
・第1行為の約2時間後、約2km離れた港でCを転落させる第2行為には時間的場所的近接性が認められる
という理由から、第1行為と第2行為の一体性を認めました。
なお、実行の着手の検討で第1行為と第2行為の一体性を論じたのであれば、故意の検討では「前述のとおり、第1行為と第2行為は一体のものである」といった論証で問題ありません。
実行の着手と故意の問題は、相互に関連していることを意識しておきましょう。
第3章 因果関係の錯誤
最後に、因果関係の錯誤について軽く解説します。
クロロホルム事件において、被告人は海中への転落による溺死という因果経過を認識していましたが、実際はクロロホルムの摂取により死亡した可能性もあるため、因果関係の錯誤が問題となります。
前章までの話は「実行行為時に故意が認められるか」という問題で、今回の話は「認識と異なる因果経過をたどった場合に故意が阻却されるか」という問題なので、別の論点として論じる必要があります。
結論として、因果関係の錯誤が故意を阻却することはありません。
詳しくは具体的事実の錯誤の解説で述べる予定ですが、同一構成要件内での錯誤に過ぎないため、故意の有無に影響することはないからです。
クロロホルム事件の控訴審(仙台高判平成15年 7月8日)も「すでにクロロホルムを吸引させる行為により死亡していたとしても、それはすでに実行行為が開始された後の結果発生に至る因果の流れに関する錯誤の問題に過ぎない。」と判示し、最高裁は「殺人罪の成立を認めた原判断は、正当である」と判示しています。
因果関係の錯誤で故意が阻却されないことは判例通説ですので、簡潔に論じれば問題ありません。
第4章 まとめ
以上のとおり、クロロホルム事件は、実行の着手と故意の二つが争点となりました。
いずれの検討においても、第1行為と第2行為の一体性が基準となります。
そして、故意の認定においては、因果関係の錯誤も別途検討する必要があります。
クロロホルム事件は「なんとなく知ってはいる」という受験生は多いはずなので、正確な理解を示すことで圧倒的な差をつけましょう。
▼次のおすすめ記事はこちら▼
【保存版】構成要件の実質的な重なり合いとは?抽象的事実の錯誤を徹底解説



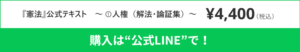


LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。