【憲法入門5】信教の自由と政教分離について、重要判例を徹底解説
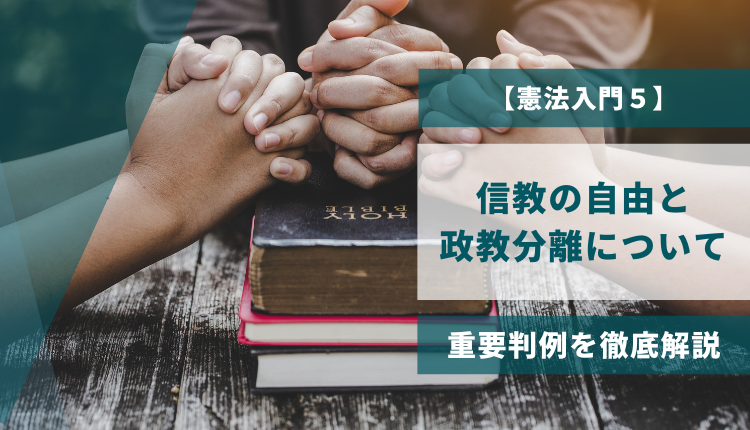
目次
この記事を読んで理解できること
- 信教の自由とは何か
- 宗教的行為に関する判例
- 政教分離とは何か
- 政教分離の審査基準
▼前回の記事▼
【憲法入門4】思想良心の自由とは?基礎から重要判例まで解説!
この記事は、
- 信教の自由とは何かを知りたい
- 政教分離とは何かを知りたい
- 信教の自由や政教分離についての判例を知りたい
といった方におすすめです。
信教の自由と政教分離は、司法試験や予備試験でも頻出の重要な概念ですが、多くの方は宗教となじみがなく、イメージがつかみにくいところもあるのではないでしょうか。
そこで、この記事では、
第1章で信教の自由とは何かについて、
第2章で宗教的行為に関する判例について、
第3章で政教分離とは何かについて、
第4章で政教分離の審査基準について、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 信教の自由とは何か
この章では、信教の自由とは何かを解説します。
まずは条文を読んでみましょう。
憲法20条
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
一般的な解釈としては、憲法20条は
- 信仰の自由
- 宗教的行為の自由
- 宗教的結社の自由
を保障していると考えられています。
それぞれ説明します。
1-1 信仰の自由
信仰の自由とは、宗教を信仰すること、あるいは信仰しないこと(消極的信教の自由)を個人が自分の意思で決められるということです。
心の中でどのような宗教を信仰するかを自由に選べるのはもちろんですが、それだけではなく
- 信仰告白をすること、信仰告白を強制されないこと
- 信仰を否定する行為を強制されないこと(踏み絵など)
- 信仰を理由とした不利益を受けないこと
なども信仰の自由として保障されます。
1-2 宗教的行為の自由
宗教的行為の自由とは、宗教上の祝典・儀式・行事・布教等を行う自由のことです。
宗教的行為をしない自由も含まれています。
内心で宗教を信仰するだけでなく行動が伴うことから、どこまで許されるかが問題となる場合もありますので、次章で詳しく解説します。
1-3 宗教的結社の自由
宗教的結社の自由とは、特定の宗教を宣伝したり、共同で宗教的行為を行ったりすることを目的とする団体を結成する自由のことです。
結社の自由は憲法21条1項で保障されていますが、宗教団体の場合は20条1項でも保障されることになります。
第2章 宗教的行為に関する判例
この章では、宗教的行為の自由が問題となった判例を紹介します。
特に有名な判例は
- 加持祈祷事件(最判昭和38年5月15日)
- 牧会活動事件(神戸簡判昭和50年2月20日)
- エホバの証人剣道受講拒否事件(最判平成8年3月8日)
の3つです。
それぞれ説明します。
2-1 加持祈祷事件
■事件の概要
|
被告人は、被害者の精神異常平癒を祈願するため、線香護摩による加持祈祷の行として、「狸が憑いているので追い出すしかない」と言い、被害者の手足を縛って線香の火に当たらせたり、背中を殴りつけたりした。 その結果、被害者は急性心臓麻痺により死亡し、被告人は傷害致死罪で起訴された。 |
被告人は、加持祈祷は宗教的行為であり、憲法20条1項で保障されると主張しました。
これに対し、最高裁は、「他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ない」と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
宗教的行為の自由も無制限ではなく、「著しく反社会的」な行為は許されないということです。
2-2 牧会活動事件
■事案の概要
|
教会牧師である被告人は、学園紛争において建造物侵入、凶器準備集合等の罪を犯した少年2名を教会に居住させ、反省の指導に当たった。被告人の指導によって少年らは反省し、警察署に任意出頭した。 その後、被告人は、犯人蔵匿罪で起訴された。 |
少年たちの世話をして反省を促した牧師さんが、犯人をかくまったとして罪に問われてしまったという気の毒な事件です。
裁判所は、「宗教行為の自由が基本的人権として憲法上保障されたものであることは重要な意義を有し、その保障の限界を明らかに逸脱していない限り、国家はそれに対し最大限の考慮を払わなければなら」ないとした上で、被告人の行為はむしろ称賛されるべきであり、違法性はないと判断しました。
加持祈祷事件と異なり、
- 重大犯罪ではないこと
- 少年らが任意出頭したため、実害が生じていないこと
などが考慮されたものと考えられます。
2-3 エホバの証人剣道受講拒否事件
■事案の概要
|
高等専門学校の学生である原告(被上告人)は、エホバの証人の教義により格技である剣道実技に参加できないという信念を持っていた。 そこで、必修科目である保健体育の剣道の授業ではレポート提出等の代替措置を認めてほしい旨申し入れたが、被告(上告人)である学校長は代替措置をとらなかった。 原告は剣道の授業中準備体操に参加するなどしたが、剣道実技には参加せず欠席扱いとされた。 そのため、体育の成績が認定されず原級留置処分となり、2回連続の原級留置処分により退学処分となった。 そこで、原告は、当該退学処分について取消しの訴えを提起した。 |
被告は、退学処分は裁量の範囲内であると主張しました。
これに対し、最高裁は、「退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であり」、「特に慎重な配慮を要する」とした上で、本件の退学処分は違法であると判断しました。
(最高裁が考慮した事情)
- 教義に反する行動を余儀なくさせられる
→学校側は相応の考慮を払う必要があった。
- 原告はレポート提出等を申し入れていた
→代替措置について考慮すべきであった。
剣道の授業は原告の信教の自由を直接的に制約するものではないものの、信仰上の真摯な理由による申し出に対して配慮は必要ということです。
ここまでは、信教の自由について解説しました。
次章からは、政教分離について解説します。
第3章 政教分離とは何か
ここからは政教分離について説明していきます。
まずは条文を読んでみましょう。
憲法20条
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
このように、政教分離とは、国家が宗教的に中立であるために、国家と宗教を分離する原則のことです。
具体的には、以下の2種類があります。
① 国が宗教的行為を行うことの禁止
・20条3項
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」
② 国が特定の宗教を援助することの禁止
・20条1項後段
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
・89条前段
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、…これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
①と②は必ずしも厳密に分けられるものではありませんので、まとめて検討することもあり得ます。
第4章 政教分離の審査基準
それでは、国家の行為が政教分離違反かどうかを審査するには、どのような基準を用いればいいでしょうか。
結論として、政教分離の審査基準は、
- 目的効果基準
- 総合考慮基準
の2つがあります。
それぞれ見ていきましょう。
4-1 目的効果基準
最高裁は津地鎮祭事件(最判昭和52年7月13日)において、以下の基準を示しました。
|
宗教的活動とは、…当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。 |
このように、目的効果基準とは、
- 目的→宗教的意義を持つ
- 効果→宗教への援助、助長、促進又は圧迫、干渉
に該当する場合には、政教分離違反を認めるという基準です。
また、愛媛玉串料事件(最判平成9年4月2日)では、以下のとおり詳細な考慮要素が示されました。
|
宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。 |
国と宗教が少しでも関わり合いを持てば、何でもかんでも違憲になるわけではないということです。
例えば、役所の敷地内にクリスマスツリーを飾ったからといって、キリスト教をひいきしていることにはなりませんよね。
4-2 総合考慮基準
近年では、目的や効果に言及しない判例が現れるようになりました。
空知太神社事件(最判平成22年1月20日)では、以下の基準が示されています。
|
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が,…信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。 |
このように、最近の判例では、目的効果基準よりも柔軟な判断基準が採用されることがあります。
ただし、
- 一般人の評価を考慮すること
- 社会通念に従って判断すること
などは、愛媛玉串料事件でも指摘されていることなので、それほど大きく判断基準が変わったわけではありません。
「どちらの基準を採用すればいいか」と悩む受験生もいるかと思いますが、大事なのはそこではなく、具体的な事情をしっかりと評価することです。
第5章 まとめ
以上のとおり、信教の自由は
- 信仰の自由
- 宗教的行為の自由
- 宗教的結社の自由
を保障しています。
特に有名な判例は
- 加持祈祷事件
- 牧会活動事件
- エホバの証人剣道受講拒否事件
の3つです。
政教分離は
- 国が宗教的行為を行うことの禁止
- 国が特定の宗教を援助することの禁止
の2種類に分けられます。
審査基準は
- 目的効果基準
- 総合考慮基準
の2つがありますが、どちらを採用するかよりも、具体的な事情をしっかりと評価することが大事です。
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
判例などの詳細な解説や、実践的な答案の書き方を知りたい方は、ヨビロン憲法のテキストをご購入いただけると幸いです。


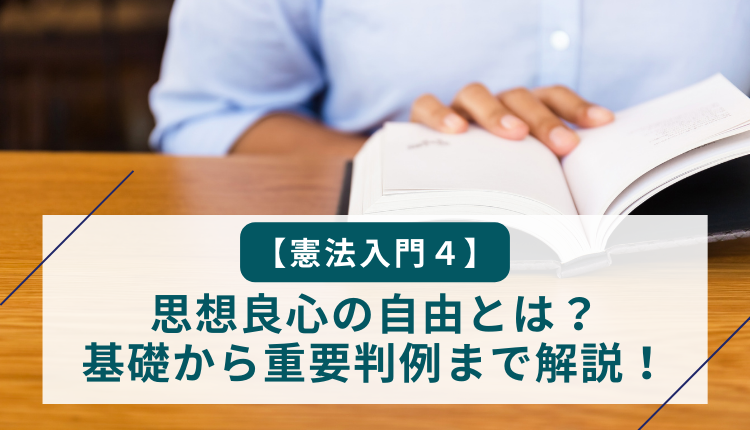
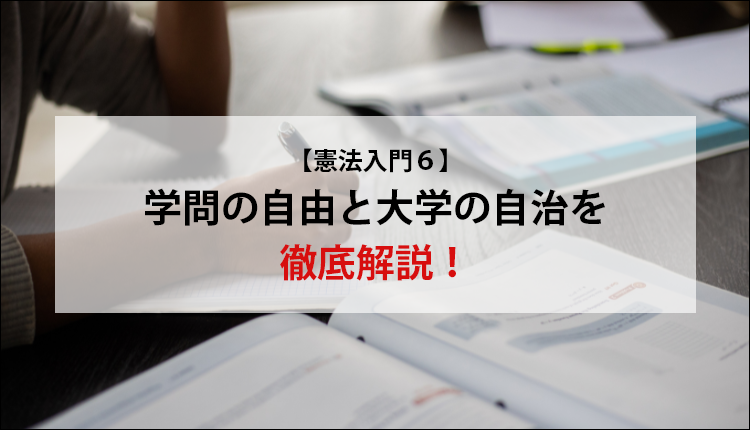
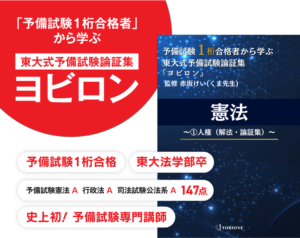



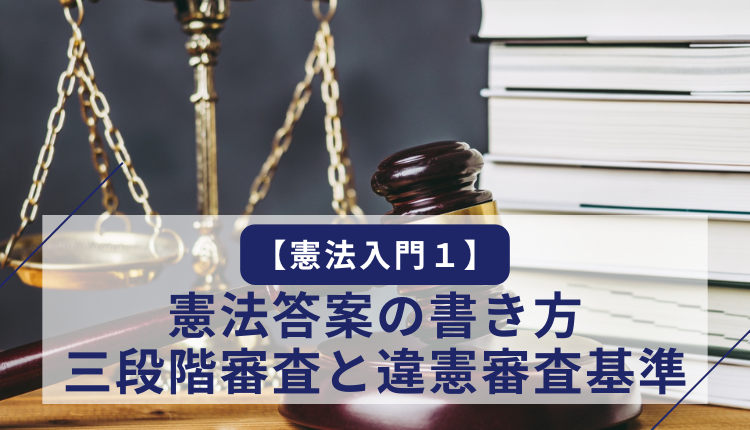
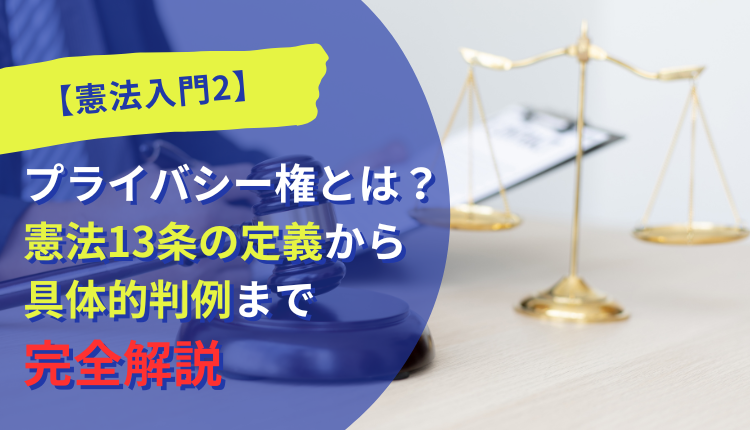
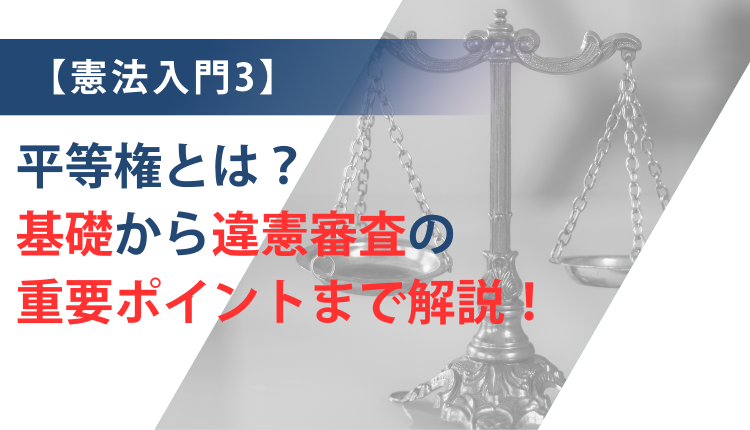

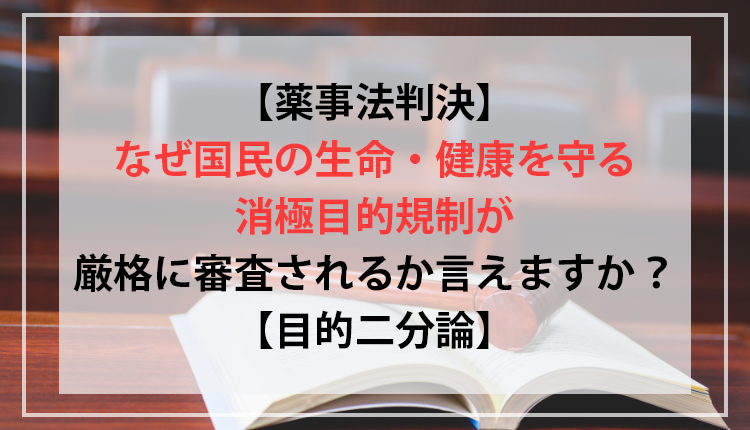
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。