- 公開日:2025.02.17
- 更新日:2025.02.18
- #ステメン
- #一橋ロー
- #一橋大学法科大学院
【記載例付き】一橋ローのステメンはこう書く!押さえるべきポイント3つ
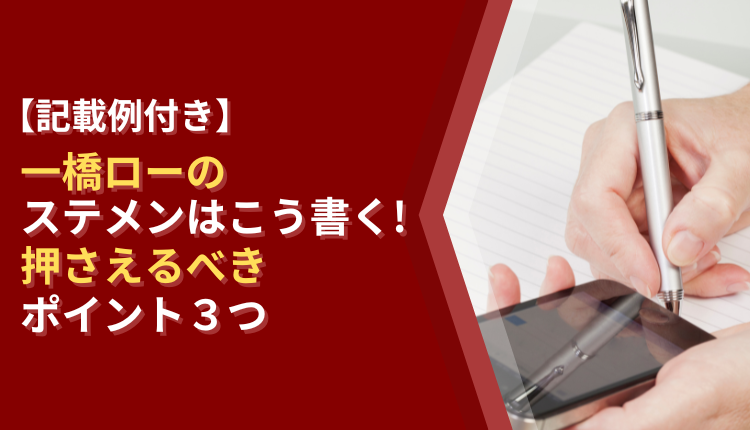
目次
この記事を読んで理解できること
- 一橋ロー入試におけるステメンの位置づけ
- 【2025年度】一橋ローのステメンで問われる内容
- ステメンを書くときの3つのポイント
- ステメンの記載例
あなたは、
- 一橋ローのステメンは合否にどう影響するのか知りたい
- 一橋ローのステメンを書くときのポイントを知りたい
- 具体的な記載例を見てみたい
とお考えではありませんか?
一橋大学法科大学院(一橋ロー)の入試では、他の多くの法科大学院と同様に、ステートメント(ステメン)の提出が必須です。
しかし、何を基準に書けばいいのか分からなかったり、どこまで合否に影響するか分からず、不安に思われたりする方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、一橋ローの入試では、ステメンを含む出願書類は、筆記試験や面接の成績などと総合的に評価し、合否を決定するとしています。
個別の配点は明らかではありませんが、筆記試験の成績が十分でもステメンが原因で不合格になる事例もあるため、決して軽視はできません。
でもこの記事を読めば、一橋ローにおけるステメンの位置づけ、書くときの3つのポイント、実際の記載例を知ることができるので、自信をもってステメンを作成できるようになります。
具体的には、
1章で一橋ロー入試におけるステメンの位置づけ
2章で一橋ローのステメンで問われる内容
3章でステメンを書くときの3つのポイント
4章で実際の記載例
について、詳しく解説します。
一橋ローのステメンの効果的な書き方を理解し、総合点で確実に点が取れるように対策していきましょう。
1章:一橋ロー入試におけるステメンの位置づけ
一橋ローにおいて、ステメンは合否判定の重要な要素となっています。
既修者・未修者ともに、TOEIC等の成績、筆記試験、面接試験、およびステメンを含む提出書類を総合して合否を決定するとされているからです。
まずTOEIC等による第1次選抜があり、筆記試験と書類審査による第2次選抜、面接試験と第2次選抜までの結果を総合する第3次選抜が実施されます。
それぞれの配点は公表されていませんが、筆記試験の成績が合格レベルであっても、ステメンなどの書類点で不合格になる事例もあるため、ステメンを疎かにしてはいけません。
また、面接試験ではステメンの内容について聞かれることもあるため、口頭でも答えられるようにしておく必要があります。
なお、一橋ロー入試の日程や募集人数、筆記試験の具体的内容等が知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
一橋大学法科大学院(一橋ロー)に入るには?入試難易度と司法試験合格率
2章:【2025年度】一橋ローのステメンで問われる内容
一橋ローでは、出願書類の「自己推薦書」がステメンにあたり、以下の内容について、2,400字相当以内で記載することが求められます。
自分が法科大学院に入学するのにふさわしいと考える理由、自分が魅力的な法曹になることができると考える理由など、自己のアピールポイントをこれまでの自己の経験、学業・社会活動などに基づいて記載してください。
引用元:一橋大学法科大学院「2025年度(一般)選抜試験募集要項」(p8)
作成の際注意が必要なのは、所定の様式はなく、自身で用意した紙に指定された条件で記載する必要があり、そのルールを守っていないものは減点対象となることです。
詳しいルールは以下の様式例や募集要項に記載されているので、作成前に必ず確認しましょう。
各要素について、どのような記載をすれば良いのかを解説します。
ただし、これは書き方の一例のため、あくまで参考と考えてください。
■自分が法科大学院に入学するのにふさわしいと考える理由
(自己の経験、学業・社会活動などに基づいて記載)
一橋ローの求める人材であり、教育目標に貢献する人材である具体的な理由を論理的に記述します。
学業などでの具体的な成果を示しながら法学の基礎力や学習意欲をアピールしたり、解決したい社会問題など明確な目的意識があることを記載したりすると良いでしょう。
■自分が魅力的な法曹になることができると考える理由
(自己の経験、学業・社会活動などに基づいて記載)
まず自身がどのような法曹を目指し、社会にどのように貢献したいかを具体的に示し、その中でも魅力的な法曹とは何かを論じます。
そしてそうなるために、これまでどのような活動をしてきたか、どのような能力を培ってきたかを具体的に示しましょう。
3章:ステメンを書くときの3つのポイント
一橋ローのステメンを書くにあたって意識すべきポイントは、以下の3つです。
- 問われていることに正確に結論ファーストで答える
- 一橋ローの理念に沿う理想の学生像・法曹像を示す
- 活動内容だけでなく培った能力や強みを示す
それぞれ説明します。
3-1:問われていることに正確に結論ファーストで答える
当たり前ですが、問われていることに正確に答えましょう。
なぜなら、他の法科大学院のステメンでよく問われる志望理由を書けばいいと思い込み、自己推薦書になっていないパターンがあるからです。
その場合、読解力・表現力がないと大きなマイナス評価になるだけでなく、点数もつかない可能性があります。
必ず「自己の経験、学業・社会活動」に基づき、「自分が法科大学院に入学するのにふさわしいと考える理由」と「自分が魅力的な法曹になることができると考える理由」のどちらも書きましょう。
ただし、ここでいう「法科大学院」は、一橋ローに特定して書く必要があります。
また、正確に答えていることが伝わるように、最初に結論を端的に示し、その後それを裏付ける具体的なエピソードを記載することが重要です。
4章で紹介している記載例でも先に結論を示す書き方になっているため、ぜひ参考にしてください。
一度原稿を完成させたら最初から見直し、すべての要素について結論ファーストで書けているか、必ず確認してください。
3-2:一橋ローの理念に沿う理想の学生像・法曹像を示す
説得力のあるステメンにするには、「一橋ローに入学するのにふさわしい学生」と「魅力的な法曹」が具体的にどのようなものなのかを定義する必要があります。
また、採点者は当然自校の理念に合う人物かどうかも見ているので、一橋ローの教育目標や求める人材に合致するものとすることが重要です。
この目指す方向性に説得力がなかったり、ロー側の理念に沿っていなかったりすれば、いくら素晴らしい実績を並べても高評価を得ることは難しいでしょう。
一橋ローの教育目標や求める人材については、最低限「入学者に関する受入れ方針(アドミッション・ポリシー)」を読むと方向性が分かります。
一橋ローのアドミッション・ポリシーには、以下のように記載されています。
1.求める学生像
本法科大学院は、「ビジネス法務に精通した法曹」「国際的な視野を持った法曹」「人権感覚に富んだ法曹」という3つの資質を兼ね備えた法曹を養成することを目指しています。
(中略)
そこで、本学では、次のような資質・知識・能力を持つ多様な人材を受け入れたいと考えています。
(1)豊かな人間性・感受性を持ち、現代社会における公正な法の運用において、指導的役割を果たそうという高い志を有している人材
(2)社会における課題を発見し、自分に備わっている基礎的な知識・技能と創造力を活用して、その解決を図るために粘り強く取り組むことができる人材
(3)問題解決のために必要となる思考力・判断力、表現力を有する人材
(4)自己の主体性を保ちつつ、多様なバックグランドを持つ人々とコミュニケーションを交わし、協働して学ぶ姿勢がある人材
(5)国際的な視野と、英語による授業に対応できる基礎的な力を身につけている人材
引用元:一橋大学法科大学院「3つのポリシー」
つまり、「ビジネス法務に精通」「国際的な視野」「人権感覚」を意識しつつ、関心のある分野や社会問題と結び付けることで、オリジナルの理想の法曹像を示せると良いでしょう。
理想の学生像としては、上記の(1)~(5)のような資質・知識・能力を持ち合わせたうえで、一橋ローに具体的にどのように貢献できる人物かを示します。
3-3:活動内容だけでなく培った能力や強みを示す
「自己の経験、学業・社会活動」について記載するときは、単に取組内容や学んだことだけでなく、具体的な成果やそこから得られた能力などを書きましょう。
一橋ローのステメンで書く必要があるのは自己のアピールポイントであり、自己の強みと法曹としての適性を説得的に伝えなければならないからです。
たとえば、「留学生支援団体で活動した」という事実だけでなく、以下のように活動の成果と培われた能力について書きます。
「異文化背景を持つ留学生10名の学習支援を担当し、全員の単位取得に貢献。この経験で、相手の立場に立って問題の本質を理解し、適切な解決策を提示する能力を培った。」
そのうえで、先ほど定義した「一橋ローに入学するのにふさわしい学生」と「魅力的な法曹」との関連性を論理的に結び付けて記載すれば、説得力のあるステメンになります。
4章:ステメンの記載例
これまで紹介したポイントを踏まえて、未修者・既修者それぞれの具体的な記載例を紹介します。
なお、これらの例はあくまで考え方の参考としていただくものであり、決して文章をそのまま利用することのないようにしてください。
4-1:未修者の場合
以下は、架空の受験生(非法学部生)を想定した未修者のステメンの記載例です。
|
私は、理系的思考と科学的知見を活かし、環境問題の解決に貢献する法曹を目指しています。環境科学を専攻し、気候変動問題に取り組んだ経験と、環境NPOでの実践活動を通じて培った問題解決能力や多様な人々との協働経験は、貴校の求める「社会の課題を発見し、その解決に粘り強く取り組む人材」に合致すると考えます。 私の強みは、環境科学の専門知識と論理的な分析力を持ち、多様なバックグラウンドを持つ人々と協働した経験があることです。これを活かし、科学と法の両面から環境問題にアプローチできる法曹として、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。
Ⅰ.魅力的な法曹になれる理由 第一に、私が科学的専門知識と理系的思考力を活かして、環境問題の法的課題を分析し、解決策を提示できることが挙げられます。 教授指導下での共同研究プロジェクトで生物多様性モニタリングを行う中、風力発電候補地の環境アセスメント調査に携わりましたが、その経験を通じて法制度の重要性を認識しました。現地ガイドからオオタカの飛来情報を収集する過程で、希少種の生息地情報の公開制限が地域住民や研究者との協議を困難にしている問題に直面したのです。そこで私は、守秘義務を課した上で関係者間の情報共有を可能にする仕組みを提案しました。この提案は、地域の環境審議会で新たなガイドライン策定の参考とされました。 この経験から、科学的データをもとに法的課題を分析し、実効的な解決策を提示できる法曹の必要性を強く認識しました。私の理系的思考と問題解決能力は、このような法曹になるための重要な素養だと確信しています。 第二に、私が多様な立場の人々との対話を通じて合意形成を図り、科学的な専門知識を分かりやすく伝えられることが挙げられます。 環境NPOでの活動では、地域の小学校と連携した河川環境保全プロジェクトに携わり、科学的調査と啓発活動を行いました。当初は、調査結果を子どもたちに分かりやすく伝えることに苦心しましたが、実験や観察を取り入れた体験型の環境教育プログラムを開発することで、この課題を克服しました。 さらに、活動を通じて、農業用水路からの生活排水混入という問題が明らかになりました。私は行政の環境課や地域の農業関係者との対話の場を設定し、水質データや地図を基に問題の所在を説明しました。その結果、排水経路の一部改善への取り組みにつながったのです。 この経験は、法曹に必要な「関係者の利害を適切に調整し、実現可能な解決策を導く力」を培う貴重な機会となりました。科学的な専門知識と対話力を備えた私は、環境分野で、このような調整能力を活かせる法曹になれると確信しています。
Ⅱ.自分が一橋大学法科大学院に入学するのにふさわしい理由 私は、理系的思考力と環境分野での実践経験を活かし、貴校の目指す3つの法曹像の実現に貢献できる人材です。特に、環境法務という観点から、企業の持続可能な発展とコンプライアンスの両立に寄与できると考えています。 環境問題は、人権課題であると同時に、企業経営における重要な法務課題です。私は環境NPOでの活動を通じて、再生可能エネルギー事業者の環境アセスメントや、中小企業の排水処理対策など、ビジネスと環境保護の接点となる課題に取り組みました。この経験から、企業活動と環境保全の両立には、科学的知見に基づく法的判断が不可欠だと実感しています。 また、私の経験は、貴校が重視する「多様なバックグラウンドを持つ人々とコミュニケーションを交わし、協働して学ぶ姿勢」を体現するものです。環境問題の解決には、行政、企業、地域住民など、多様なステークホルダーとの調整が必要です。NPOでの活動では、これらの関係者との対話を通じて合意形成を図る経験を積み、その過程で環境法や行政法の実務的な知識も習得してきました。 貴校が重視する「多様な人々と協働する姿勢」にも合致します。環境問題の解決には行政、企業、地域住民との調整が不可欠であり、NPOでの活動を通じてその経験を積みました。 さらに、英語による学術論文の読解や国際環境会議への参加を通じ、グローバルな環境規制の動向を理解する力も養っています。近年、ESG投資の拡大やカーボンニュートラルの推進により、企業の環境対応は経営戦略の中核となりつつあります。この分野で科学的知見と法的専門性を兼ね備えた人材の需要は高まっており、私はその役割を担いたいと考えます。 以上のように、私は環境科学の専門知識と理系的思考力を持ち、それらを活かして具体的な問題解決に取り組んできました。また、多様な人々との協働経験を通じて、環境問題における法制度の重要性と、科学と法を架橋する法曹の必要性を強く認識しています。これらの経験と能力は、貴校で学ぶ上で大きな強みとなり、将来、科学的知見と法的専門性を兼ね備えた法曹として社会に貢献できる基盤になると確信しています。 |
4-2:既修者の場合
以下は、架空の大学生を想定した既修者のステメンの記載例です。
|
Ⅰ.自分が魅力的な法曹になることができると考える理由 私は、企業活動における人権尊重の実現を牽引する「魅力的な法曹」になれると考えています。これは、①法学部での研究を通じて培った企業法務と人権問題に関する専門的知見、②法律相談所での実務経験、③留学を通じて得た国際的視点という3つの強みがあるからです。 私が考える魅力的な法曹とは、法的知識を活かし、企業の持続的な成長と人権保護の両立を実現できる存在です。これは、企業活動における人権侵害の問題が深刻化する中、それを単なるリスク要因として捉えるのではなく、持続的な企業価値の向上につなげる視点が不可欠と考えるためです。 その実現可能性の根拠として、まず、企業活動における人権問題への具体的な取り組み実績があります。3年次の会社法演習では、日本企業のサプライチェーンにおける人権デューデリジェンスをテーマに、特に技能実習生の労働環境に焦点を当てて研究を行い、企業が自主的に人権尊重に取り組むインセンティブ設計について考察しました。この研究は指導教員から高い評価を受け、学内の法学会誌に掲載されただけでなく、他大学との合同ゼミでも発表の機会をいただき、「実務的な観点からの分析が優れている」との評価を得ました。 また、大学の法律相談所での活動では、月2回程度、弁護士の先生の指導下で法律相談に同席し、理論と実務の架け橋の重要性を学びました。特に印象的だったのは、中小企業の社長からのハラスメント対策に関する相談でした。私は、相談員の先生の指導の下、就業規則の確認や社内研修制度の調査を担当し、企業に実情に即した具体的な改善案の作成に関わりました。その後、この企業では私たちが提案した定期的な従業員面談制度が導入され、職場環境の改善につながったと報告を受けています。 そして、3年次の○○大学(イギリス)への留学では、Business and Human Rightsの授業を履修し、グローバルな文脈での企業活動と人権保護について学びました。特に、イギリスの現代奴隷法の実効性に関する事例研究を通じて、法規制と企業の自主的な取り組みをいかに調和させるかという視点を得ることができました。 これらの経験を通じて、①企業法務に関する理論的理解、②人権も代の実務的解決能力、③国際的な視点からの問題分析力を培ってきました。これらの能力は、企業の持続的な成長と人権保護の両立を実現する法曹として必要不可欠なものであり、これらを基盤として、今後も研鑽を重ねることで、必ず魅力的な法曹になれると確信しています。
Ⅱ.自分が一橋大学法科大学院に入学するのにふさわしいと考える理由 私は、貴校の教育理念である「ビジネス法務に精通し」「国際的な視野を持ち」「人権感覚に富んだ法曹」の育成に合致する人材であると考えています。その理由は以下の3点です。 第一に、ビジネス法務と人権問題に関する確かな基礎力があります。学部の成績では、会社法・労働法の単位を優秀な成績で修得し、GPAは上位10%以内を維持しています。また、ゼミでは企業のコンプライアンス体制における人権尊重の位置づけについて研究し、特に内部通報制度の実効性確保をテーマに、判例分析と企業へのヒアリング調査を行いました。この研究を通じて法解釈と実務の両面から問題を分析する力を養いました。 第二に、多様なバックグラウンドを持つ人々との協働経験があります。法律相相談所では留学生を含む10名程度のメンバーと協力しながら、年間20件ほどの法律相談に関わりました。また、相談所のメンバーとして、地域の外国人住民向けの法律相談会の運営を経験し、言語や文化の違いを超えたコミュニケーションの重要性を学びました。 第三に、英語力と国際感覚を活かした学習意欲があります。TOEIC〇〇点の英語力を基盤に、留学中は現地の授業に積極的に参加し、法的議論を英語で行う力を養いました。帰国後は、この経験を活かして学内の留学生との交流会を月1回程度開催し、日本法と外国法の比較を通じた学習会を継続しています。 以上の経験と実績は、貴校のカリキュラムを通じてさらに発展させることができると考えています。特に、ビジネスロー・コースと人権クリニックは、私の目指す法曹像の実現に最適なプログラムだと考えています。また、実務家教員による実践的な教育を通じて、企業活動と人権保護の調和という課題に取り組む具体的なスキルを習得できると確信しています。 私は、貴校での学びを通じて、企業活動における人権尊重の実現を牽引する「魅力的な法曹」として、持続可能な社会の発展に貢献していきたいと考えています。 |
まとめ|一橋ローのステメンは志望理由ではなく自己アピールを書くもの
一橋ローの入試では、英語能力、筆記試験、ステメンを含む提出書類、面接試験を総合して合否が決定されますが、それぞれの配点は明らかにされていません。
ただし、ステメンの出来が合否に影響した事例もあり、ステメンの内容を面接試験で聞かれることもあるので、ステメンは質の高いものを準備する必要があります。
一橋ローのステメンは、一般的なステメンとは違い、志望理由ではなく自己アピールを書くことが求められる点に注意し、以下の3つのポイントを押さえて書きましょう。
- 問われていることに正確に結論ファーストで答える
- 一橋ローの理念に沿う学生像・法曹像を示す
- 活動内容だけでなく培った能力や強みを具体的に示す
本記事で紹介する記載例でイメージをつかんでいただきながら、自身の魅力が伝わる質の高いステメンを作成し、自信を持って一橋ローの入試に臨んでください。


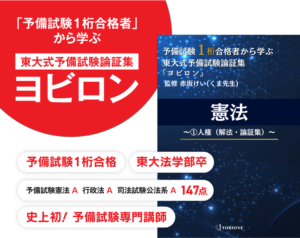



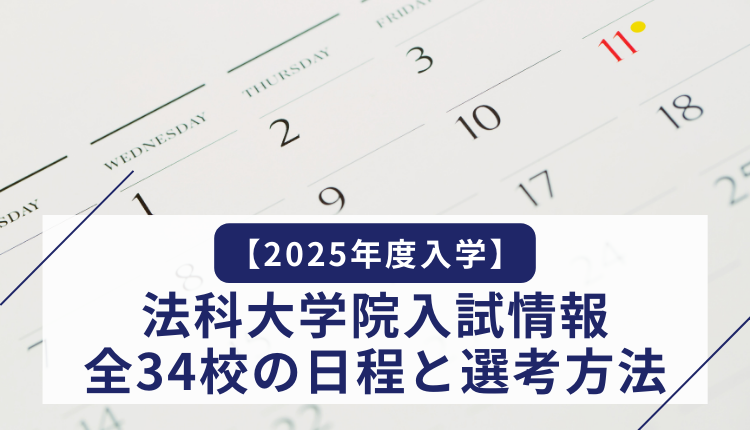
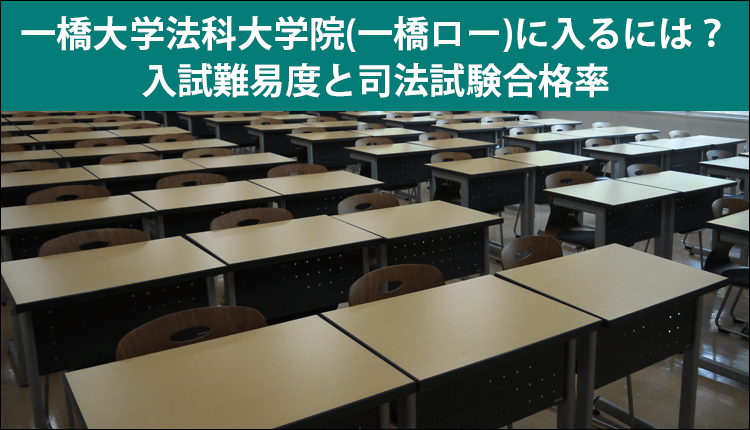
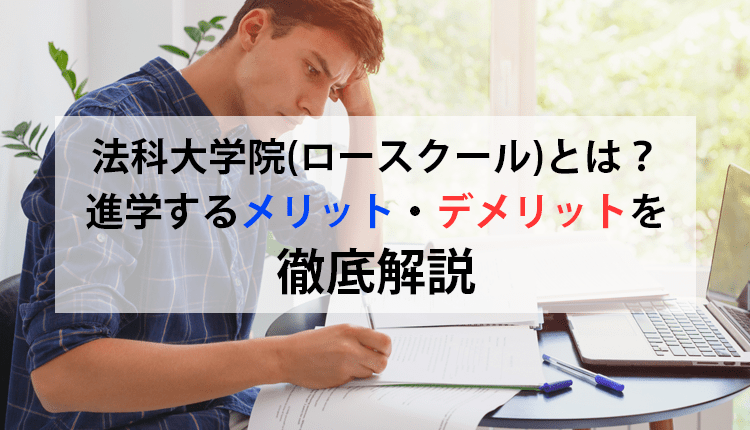
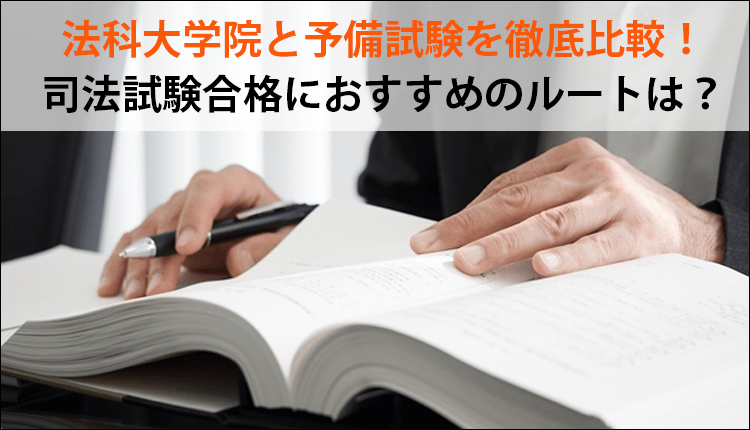
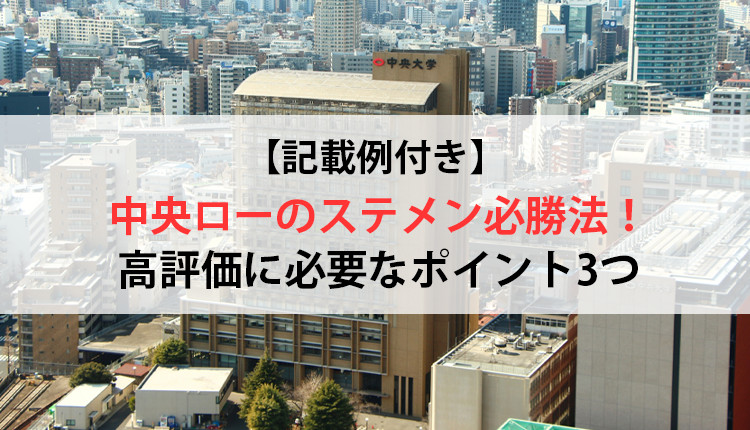
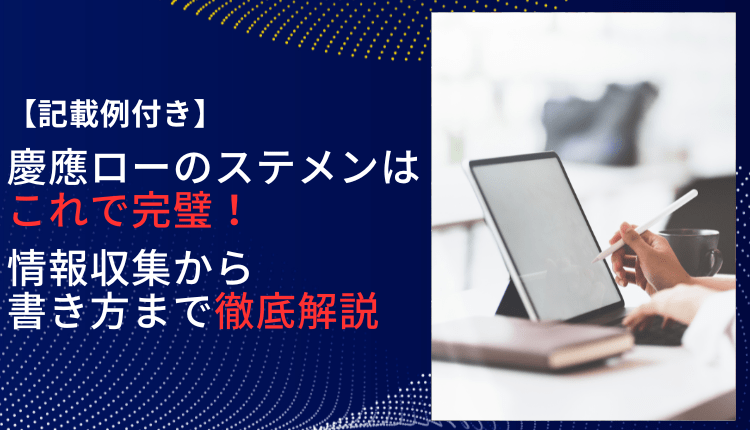
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。