- 公開日:2025.01.28
- 更新日:2025.01.28
- #ステメン
- #京都大学法科大学院
【記載例付き】京大ローのステメンで失敗しない!守るべきポイント3つ
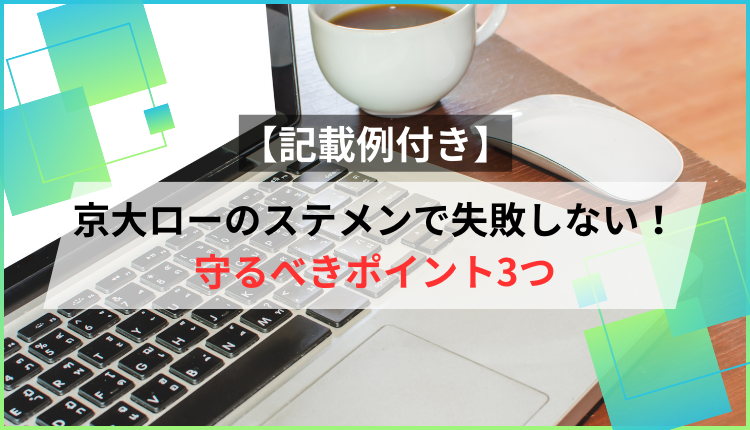
目次
この記事を読んで理解できること
- 京大ロー入試におけるステメンの重要性
- 【2025年度】京大ローのステメンで問われる内容
- ステメンを書くときの3つのポイント
- ステメンの記載例
あなたは、
- 京大ローのステメンは合否にどう影響するのか知りたい
- 京大ローのステメンをどう書けばいいのか知りたい
- 実際に参考になる記載例を見てみたい
とお考えではありませんか?
京都大学法科大学院(京大ロー)への出願では、他の多くの法科大学院と同様、ステートメント(ステメン)の提出が求められます。
ステメンの評価方法は明確にされていない場合が多いので、どれくらい合否に影響するのか、どのように書けばいいのかなど、意外と悩んでしまいますよね。
結論から言うと、京大ローの入試では、学業成績やステメンを含む出願書類の配点は決まっており、総合点の3~4割を占めています。
ステメン単独の配点の公表はありませんが、多様性の確保を入学者受入方針に掲げているため、多様な実績をステメンでアピールすることは効果的でしょう。
この記事を読めば、京大ローにおけるステメンの重要性、高評価につながる書き方、実際の記載例を知ることができ、合格レベルのステメンの完成イメージが明確になります。
具体的には、
1章で京大ロー入試におけるステメンの重要性
2章で京大ローのステメンで問われる内容
3章でステメンを書くときの3つのポイント
4章で実際の記載例
について、詳しく解説します。
京大ローのステメンの戦略的な作成方法を身につけ、ステメンで悩む時間をなくしましょう。
1章:京大ロー入試におけるステメンの重要性
京大ローの入試では、学業成績やステメンを含む出願書類の審査結果が合否に大きな影響を与えます。
以下の表は最終合格者の決定段階における配点率を示しており、出願書類の配点率は一般選抜でも総合点の3~4割を占めるからです。
|
未修者 特別選抜 |
出願書類 |
口述試験 |
|
100点満点 |
200点満点 |
|
|
未修者 一般選抜 |
出願書類 |
小論文試験 |
|
100点満点 |
200点満点 |
|
|
既修者 一般選抜 |
出願書類 |
法律科目試験 |
|
400点満点 |
550点満点 |
|
|
既修者 法学部3年次生 |
出願書類 |
法律科目試験 |
|
400点満点 |
350点満点 |
|
|
既修者 5年一貫型 |
出願書類 |
口述試験 |
|
400点満点 |
50点満点 |
引用元:京都大学法科大学院「令和7年度入学者選抜関係 Q&A」(Q7-1のA.)
特に未修者特別選抜(社会人または非法学部出身者が対象)では、出願者数が多いと出願書類の内容に基づく第一段階選抜がおこなわれます。
また、口述試験では出願書類の内容から質問がされるため、その点も意識して記載内容を考える必要があるでしょう。
京大ロー入試では、学業成績が重要な判断材料になっているとされています。
しかし、多様性の確保に重点を置く方針を掲げており、ステメンで多様な学識や課外活動の実績、社会経験等をアピールすれば加点になるため、しっかり書く必要があります。
なお、京大ロー入試の全体の概要や筆記試験の内容が知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
京都大学法科大学院(京大ロー)を徹底解説!入試難易度と司法試験合格率
2章:【2025年度】京大ローのステメンで問われる内容
京大ローでは、出願書類の「自己評価書」がステメンにあたり、そこで問われる内容は以下のとおりです。
学業についての自己評価、学業以外の活動実績、社会人としての活動実績、出願の動機等を 2,000 字以内で記述すること。
引用元:京都大学法科大学院「自己評価書」
各項目に記載する内容についてそれぞれ説明します。
■学業についての自己評価
優秀な成績を収めた科目などを具体的に挙げて、積極的に学習に取り組んだエピソードを示すことが考えられます。
単なる成績の羅列ではなく、何を学び、その成果としてどのような能力が得られたかなどを説明しましょう。
■学業以外の活動実績
サークル活動などを通じて積極的に行動した実績、得られた学びや周りからの評価などを記載し、これらの経験を法曹としてどのように活かせるかを説明しましょう。
■社会人としての活動実績
成果を上げた業務経験などを詳しく記載し、それにより培った高度な専門知識や実務能力について、法曹としてどのように活かせるのかを具体的に説明しましょう。
なお、社会人経験を証明する客観的資料の添付が必須です。
■出願の動機
なぜ法科大学院で学ぶ必要があるのか、なぜ他の法科大学院ではなく京大ローなのかということが明確に伝わるように書く必要があります。
3章:ステメンを書くときの3つのポイント
京大ローのステメンを書くにあたって意識すべきポイントは、以下の3つです。
- 問われていることに答える
- 具体的事実に基づき法曹の資質をアピールする
- 求める学生像を意識して論理的に記載する
それぞれ説明します。
3-1:問われていることに答える
基本的なことですが、まずは問われていることすべてについて趣旨を正しく理解し、的確に答えることが重要です。
問の趣旨からずれていたり、答えていない項目があったりすれば、そもそも読解力や表現力がないとみなされ、大きなマイナスになるからです。
京大ローのステメンでは、「学業についての自己評価」「学業以外の活動実績」「社会人としての活動実績(社会人の場合)」「出願の動機」に答える必要があります。
各項目に対して回答するときは、相互に関連づけるように意識すると説得力のあるステメンになります。
たとえば、ゼミを通じて法制度の原理的理解の重要性を実感し、その問題意識を課外活動で深め、京大ローで学びたいとの志望動機につながったといった書き方です。
「出願の動機」では、他の法科大学院ではなく、京大ローで学ぶべき理由を明確にする必要があります。
以下の記事では、京大ローの教育の特色についても解説しているので、参考にしてみてください。
京都大学法科大学院(京大ロー)を徹底解説!入試難易度と司法試験合格率
一度書き終わった後に再度読み直し、すべての問に答えているか、一貫性のある書き方になっているかについて必ず確認しましょう。
3-2:具体的事実に基づき法曹の資質をアピールする
ステメンでは抽象的な自己PRは避け、具体的な事実に基づいて記述することが重要です。
ただし、実績や経験をたくさん書けばいいというわけではなく、それらが、どのように法曹の資質に結びつくのかという点を説得的に記載しましょう。
イメージしやすいように、各項目の記載例を紹介するので参考にしてください。
■「学業についての自己評価」
「民法の学習に力を入れていた」などの抽象的な表現ではなく、具体的な学習プロセスを示しましょう。
記載例:
「民法演習では判例百選の課題を毎回レジュメにまとめ、制度の趣旨から結論を導く議論を展開した結果、教授から論理的な思考力を評価していただきました。」
■「学業以外の活動実績」
活動内容と得られた成果を具体的に示し、法曹の資質と結び付けて記載します。
記載例:
「学生相談所のピアサポーターとして、2年間留学生の相談に携わり、文化や価値観の違いを踏まえた問題解決をサポートしました。この経験で培った、相手の立場に立って問題を理解し適切な助言をする力は、法曹に必要な対話力や問題解決力の基礎になると考えています。」
■「社会人としての活動実績」
具体的な業務経験と法曹の資質を結びつけて記載します。
記載例:
「金融商品の販売担当として、顧客の資産状況を適切に把握する業務に携わり、高齢の顧客には収益機会より顧客保護を優先して安全な商品を提案するなど、常に顧客の立場に立った判断を心がけてきました。この経験は、依頼者の利益と法的正義の両立を図る法曹としての基礎になると考えています。」
3-3:求める学生像を意識して論理的に記載する
ステメンでは、京大ローが求める学生像を意識して記載することが重要です。
なぜなら、入学者選抜において、提出されたステメンは、その志願者が本学の教育理念や方針に適合しているかどうかを判断する重要な材料となるからです。
まず京大ローの教育目標は、以下のとおり定められています。
これを実現するため、京大ローのアドミッションポリシーにおいて、求める学生像は以下のとおりとされています。
法制度の役割や人間と社会の在り方に対する強い関心をもって法曹を志し、また、法曹となるにふさわしい優れた資質と能力を備えた学生
引用元:京都大学法科大学院「入学者の受入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)」
このため、法制度と社会との関わりについての問題意識や、法曹としての資質を備えていることを記載することが重要です。
また、「多様な知識又は経験を有する者を入学させる」という方針を強調しているため、他分野での専門的知識や社会経験がある受験生は効果的にアピールしましょう。
4章:ステメンの記載例
これまで紹介したポイントを踏まえて、未修者・既修者それぞれの具体的な記載例を紹介します。
なお、これらの例はあくまで考え方の参考としていただくものであり、決して文章をそのまま利用することのないようにしてください。
4-1:未修者の場合
以下は、架空の社会人受験生を想定した未修者のステメンの記載例です。
1.学業についての自己評価
私は、学部時代に情報工学を専攻し、論理的思考力とデータに基づく分析力を培いました。
卒業研究では、機械学習を用いた自然言語処理の研究に取り組み、大量のテキストデータから有益な情報を抽出するアルゴリズムを開発しました。この研究により、複雑な問題を要素に分解して検証し、論理的に解決策を導き出す力が身についたと感じています。また、研究室のゼミでは、最新の論文を題材に議論する機会が多くあり、他者との建設的な対話を通じて、多角的な視点で課題を分析する力を磨きました。
また、3年次から履修した「情報システムと社会」では、技術がもたらす社会的影響について多面的に学びました。この授業では、情報セキュリティやプライバシー保護などの今日的な課題について、技術面だけでなく、倫理的・社会的な観点からも検討を行いました。グループワークでは、SNSにおける個人情報の利活用に関する事例研究に取り組み、利便性向上と個人の権利保護の両立について、チームメンバーと活発な議論を重ねました。
これらの経験を通じて、法曹に不可欠な公正な判断力や論理的分析力、多様な意見を調整しながら解決策を導く力の基礎を築くことができたと考えています。
2.社会人としての活動実績
私は2013年から現在まで、IT企業においてプライバシー保護とデータ保護の業務に従事しています。具体的には、個人情報保護法や海外のデータ保護法制への対応、利用規約やプライバシーポリシーの策定、社内外からの法務相談対応などを担当しています。
特に印象的な経験は、2019年における欧州でのサービス展開に伴い、GDPR(EU一般データ保護規則)対応のプロジェクトをリードしたことです。このプロジェクトでは、社内の開発チームや事業部門と密接に連携し、サービス設計の初期段階から法令遵守の仕組みを組み込む体制を確立しました。この過程で、技術と法制度の両面を理解した上で、様々な部門の利害関係者と議論を重ね、実務的な解決策を見出す経験を積みました。この経験を通じて、プロジェクトマネジメントの重要性を学ぶとともに、利害関係者間の調整能力や公平な判断力を養うことができました。
また、2021年からは、若手エンジニア向けにデータ保護に関する勉強会を主催し、約2年間にわたって継続的な啓発活動を行いました。この活動では、延べ50名以上の参加者に対し、具体的な事例を用いて、技術的対応と法的要件の関係について分かりやすく説明することを心がけました。参加者からは「法制度の意義を実感できた」という評価を得ており、技術者と法律家の架け橋となる役割の一端を担えたのではないかと考えております。
3.出願の動機
私が法科大学院への進学を志望する最大の理由は、テクノロジーの進展に伴う法的課題に、技術的な知見を活かしながら取り組む法曹を目指しているためです。
IT企業での業務を通じて、AI・ビッグデータの活用やデジタルプラットフォームの台頭により、従来の法制度では十分に対応できない新たな課題が次々と生まれていることを実感しました。例えば、AIシステムの判断に関する責任の所在、アルゴリズムの透明性確保、デジタル空間でのプライバシー保護など、技術と法の両面からの検討が必要な問題が山積しています。
このような課題に対して、技術の特性を理解した上で適切な法的助言ができる法曹が不足していると感じています。私は、エンジニアとしての経験と法曹としての専門性を組み合わせることで、デジタル社会における新たな法的課題の解決に貢献したいと考えています。
そして貴校を志望する理由は、以下の3点です。
第一に、「生命倫理と法」「情報法」などの展開・先端科目に加え、法理学や法社会学といった基礎法学科目を通じて、新しい技術がもたらす法的・倫理的課題を多角的に検討できるカリキュラムが、私の目標に最も適していると考えたためです。
第二に、多様なバックグラウンドを持つ学生を積極的に受け入れる方針が、技術者としての経験を活かしながら学べる環境として魅力的だと感じたためです。
第三に、少人数での双方向・多方向的な討議を重視する教育方針が、実務で培った問題解決能力をさらに向上させる機会になると考えたためです。
以上のような動機から、貴校において法曹としての基礎を築きたいと考え、出願いたしました。技術と法の両面の知識を持つ法曹として、デジタル社会の健全な発展に貢献できるよう、全力で学びに取り組む所存です。
4-2:既修者の場合
以下は、架空の大学生を想定した既修者のステメンの記載例です。
1.学業についての自己評価
私は、法学部での4年間の学びを通じて、法制度に関する体系的理解と論理的思考力を確実に身につけてきました。
特に「民事法演習」と「刑事法演習」の授業では、判例研究や事例問題の報告を担当し、法的分析力を養いました。民事法演習では、消費者契約法に関する最新判例を分析・報告する機会があり、従来の判例との整合性や射程範囲について、教員や他の受講生と徹底的な議論を行いました。その過程で、複数の判例評釈や学説を比較検討し、法的問題を整理・分析する手法を習得しました。また、刑事法演習では、新しい形態の詐欺事案における構成要件該当性の判断基準について、判例の展開を踏まえながら検討を行い、理論的考察を深めました。
これらの演習科目に加えて、「行政法」「民法」「商法」の基幹講義では、事前に重要判例や重要論点について関連文献を精読し、教員の見解と比較しながら自身の考えをまとめるという学習方法を実践してきました。その結果、憲法及び民法の講義・演習科目でGPA○(○満点中)を達成するなど、着実な成果を上げることができました。
2.学業以外の活動実績
私は3年次から公法研究会に所属し、憲法・行政法分野の研究発表や議論に定期的に参加してきました。特に印象に残っているのは、行政手続法における手続的権利保障の意義をテーマに、海外法制や判例と比較しながら議論を行った経験です。この経験を通じて、法的問題を幅広い視点から検討する重要性を学びました。
また、4年次には研究会の幹事を務め、地方自治体の法務部門で働く行政職員を招いた研究会を企画しました。研究会では、空き家対策条例の制定過程を具体例として、自治体における政策法務の実態について学び、市民財産権の調整や条例の実効性確保における法的課題の解決がいかに重要であるかを実感しました。この経験を通じて、自治体法務における法的思考の意義を深く理解するとともに、行政法分野の課題に取り組む法曹の必要性を痛感しました。
さらに、3年次の夏休みに、地元の法律事務所で2週間のインターンシップに参加しました。特に印象深かったのは、多重債務問題を抱える依頼者の法律相談に同席した経験です。担当弁護士は、依頼者の断片的な記憶を丁寧に聞き取り、金融機関からの請求内容の問題点を整理し、過払金返還請求の可能性を検討しました。この過程で、法的分析と依頼者とのコミュニケーションを両立させる重要性を学びました。また、依頼者に寄り添いながら法的解決策を分かりやすく説明する姿勢から、法曹としての社会的責任を強く意識しました。
3.出願の動機
私は、貴校の教育目標である「法の精神が息づく自由で公正な社会の実現のため、様々な分野で指導的な役割を果たす創造力ある法曹を養成する」に深く共感し、出願を決意しました。
この決意の背景には、上述した研究会活動での経験があります。空き家対策条例の制定過程を通じて、自治体法務における理論と実務の架橋の重要性を認識し、この分野で貢献できる法曹になりたいと強く感じました。また、インターンシップでは、専門的な法知識を駆使しながら、依頼者や他分野の専門家との適切なコミュニケーションを図り、問題解決に導く弁護士の姿に深く感銘を受けました。この経験を通じて、法的知識と実践的スキルを兼ね備え、社会の複雑な課題に柔軟に対応できる法曹になることが、私の目指すべき道であると確信しました。
貴校は、「現代の行政法制」「現代立法論」といった行政法分野の展開・先端科目やリサーチペーパー科目など、より高度な理論研究を可能とする科目を設けており、最新の行政法上の課題について原理的・体系的な理解と研究的思考力を涵養できる点が魅力です。さらに、研究者教員と実務家教員が緊密に連携しながら授業を展開し、理論と実務の両面から指導を受けられる点も、貴校ならではの特徴だと考えています。これは、上述した自治体の政策法務の分野において、条例制定などの理論面と、その運用実務の両面に精通した法曹を目指す私の目標に合致します。
私は、貴校での学びを通じて、法的知識と思考力をさらに深化させるとともに、実務的な対応力も身につけ、社会の要請に応えられる法曹を目指したいと考えています。特に、行政法分野での学びを深め、将来的には行政訴訟や自治体の政策法務に携わることで、公正な社会の実現に貢献したいと考えています。
以上のような理由から、私は貴校への入学を志望いたしました。入学後は、これまでの学びや経験を活かしながら、さらなる研鑽を重ねる所存です。
まとめ|京大ローのステメンは多様な実績と学習意欲をアピールしよう
京大ローの入試では、学業成績やステメンを含む出願書類の配点が高め(総合点の3~4割)なのが特徴です。
また、多様性の確保を重視しているため、ステメンでは多様な実績と共に、法制度や社会問題に対する強い学習意欲をアピールすることで、高評価を得られる可能性があります。
効果的で質の高いステメンを作成するには、主に以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
- 問われていることの趣旨に的確に答えること
- 具体的事実に基づき法曹の資質をアピールすること
- 京大ローが求める学生像を意識して記載すること
本記事で紹介したポイントと記載例を参考に、あなたの強みや熱意が伝わるステメンを早速作成してみてください。


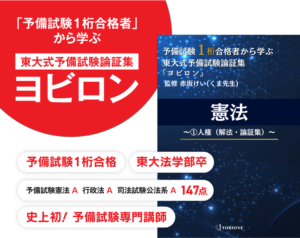



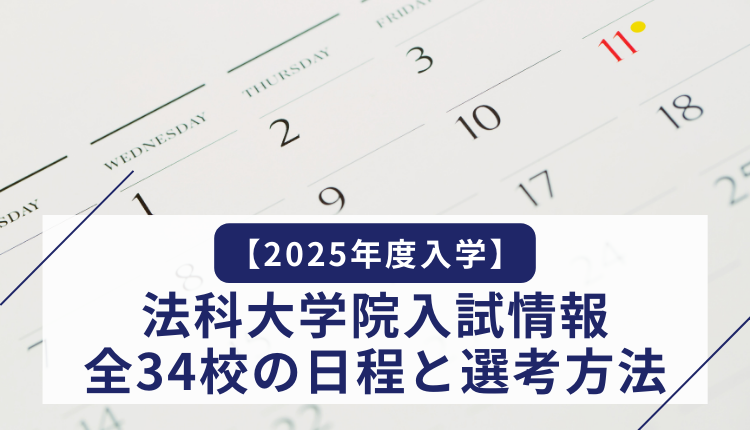
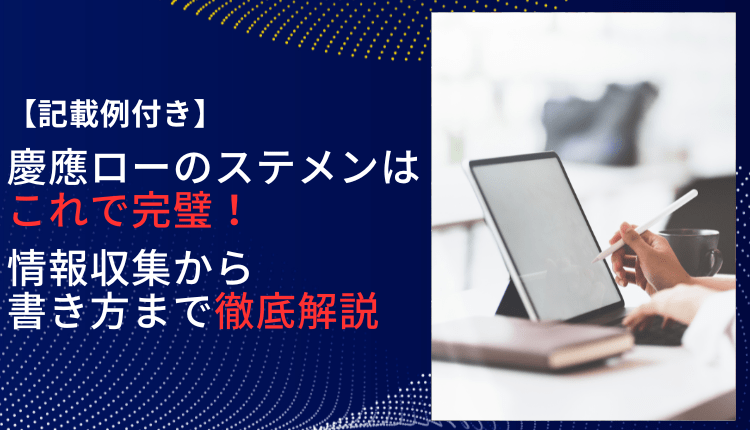
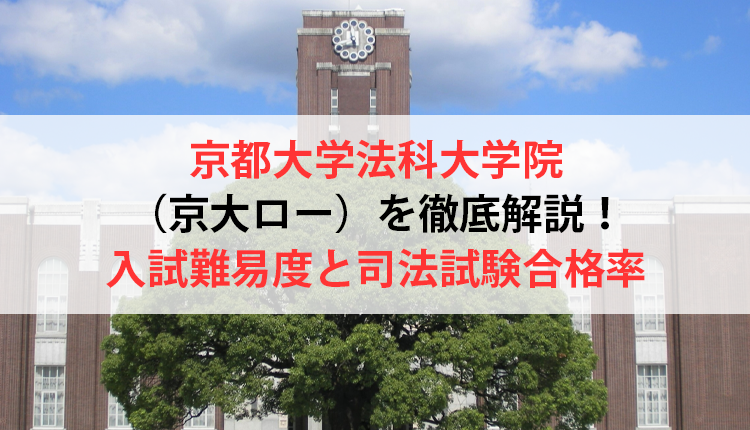
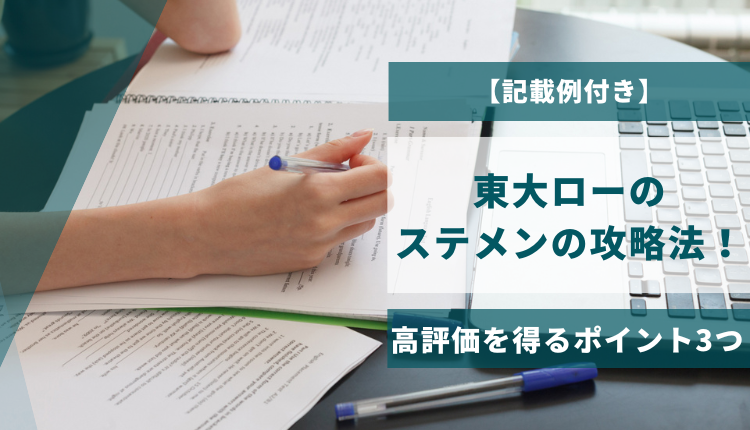
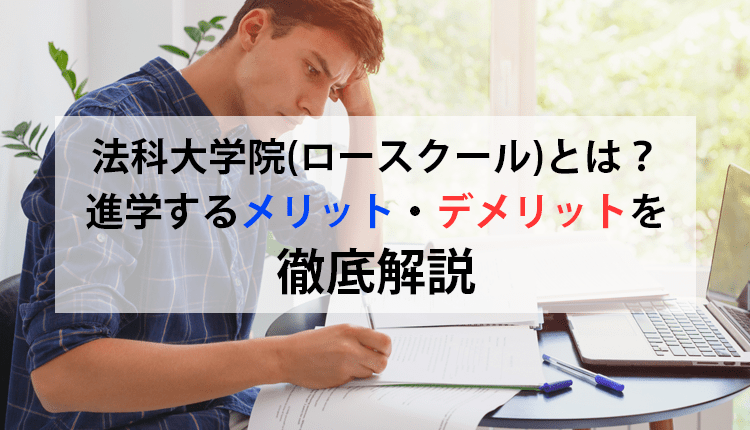
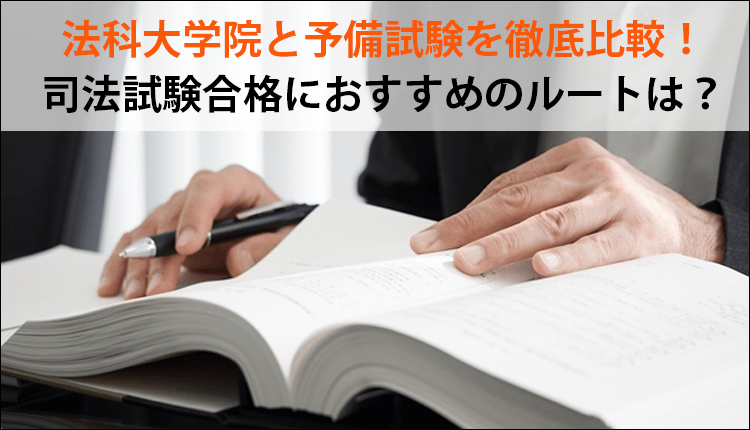
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。