【法科大学院修了生の就活】就職できないはうそ!強みが活かせる就職先
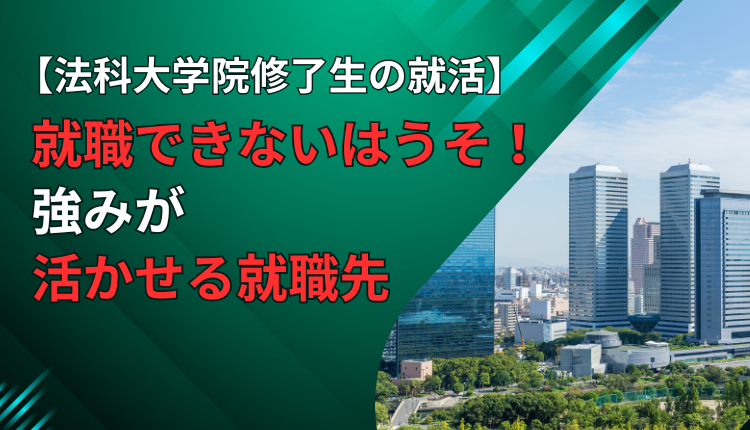
目次
この記事を読んで理解できること
- 法科大学院生の就活の進め方
- 法曹以外で法務スキルが活かせる就職先
- 法科大学院修了生は就職できない?不利な点3つを克服する方法
- 法曹を目指すなら予備試験にも挑戦しよう
あなたは、
- 法科大学院生の就活の進め方が知りたい
- 司法試験に落ちた場合の就活先を知りたい
- 法科大学院修了生は就職が難しいのかどうかを教えてほしい
とお考えではありませんか?
もし司法試験に合格できなかったら就職先がないのではないかと、不安を抱えている法科大学院生は少なくないでしょう。
結論からいうと、司法試験に合格しなくても、法科大学院で培った法務スキルを活かせる就職先はあります。
しかし、一般の学部卒生と比べて不利になりやすい点もあるので、適切な対策が必要です。
この記事を読めば、法科大学院生の就活の進め方や法曹以外の就職先、不利になる点とその対策が分かり、試験の合否に関わらず理想のキャリアを選べるようになります。
具体的には、
1章で法科大学院生の就活の進め方
2章で法曹以外で法務スキルが活かせる就職先
3章で就活で不利な点を克服する方法
について、詳しく解説します。
法科大学院生の強みを活かす就活の方法を知り、自信を持って目標のキャリアに向けた準備を進めていきましょう。
1章:法科大学院生の就活の進め方
法科大学院生の就活における、一般的なスケジュールは以下のとおりです。

ここでは、司法試験の合格発表前までの期間と、合格発表後の期間について、その結果ごとに就活の進め方を詳しく説明します。
なお、この記事では、法科大学院生が法律事務所への就職を目指す場合の就活について取りあげます。
その他の就職先や弁護士の就活全体像、就職先別の就活スケジュールなどについては、以下の記事を参考にしてください。
弁護士の就活完全ガイド!7つの就職先別の特徴と就活スケジュール
1-1:司法試験合格発表まで
特に法律事務所への就職を希望する場合は、司法試験の合否がわかる前から行動しなければなりません。
まず、ロー在学中にサマークラークに積極的に参加しましょう。
サマークラークに参加すれば、就活で有利になれる可能性が高いからです。
特に大手法律事務所への就職を希望する場合は、参加は必須といえます。
サマークラークとは、主に法科大学院生を対象とした法律事務所のインターンのことです。
8~9月頃に2日間程のプログラムで実施され、弁護士業務の体験や、所内弁護士との交流などがおこなわれます。
3~4月頃に募集が開始され、定員に達し次第締め切る事務所もあるため、募集開始時期を逃さないよう注意してください。
2~3月に実施されるウインタークラーク、もしくはスプリングクラークでも、法科大学院生が対象となる場合があります。
こちらは前年の10月~12月頃募集が開始されるので、希望の法律事務所の情報は早めに確認しましょう。
事務所説明会は、1月以降から開催され始めます。事務所の雰囲気や実際の働き方の参考になるため、幅広く参加することをおすすめします。
本選考である個別訪問や面接の時期は法律事務所によりますが、本格化するのは7月中旬の司法試験日後からです。
試験の合否が気になる時期ですが、就活に頭を切り替えて、早めの行動を心がけてください。
その他、法律事務所への就活の流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも併せてご覧ください。
【完全版】法律事務所の就活の進め方と対策!事務所選びのポイント7つ
1-2:司法試験に合格した場合
11月の司法試験合格発表後は、準大手・中堅法律事務所の採用が本格化します。
日本弁護士連合会が運営している「ひまわり求人求職ナビ」などの求人サイトに、求人情報が掲載されるようになるのがこの時期です。
参照:ひまわり求人求職ナビ
東京三弁護士会(東京弁護士会、第一、二東京弁護士会)による大規模なオンライン合同説明会も開催されます。
複数の事務所を比較検討することで、自分の新たな興味に気づくこともあるので、積極的に参加するのがおすすめです。
小規模法律事務所の採用活動時期は遅く、司法修習期間中と重なることもあります。
そもそも採用状況が不明の場合もあるため、希望の事務所があれば、自分から連絡をとる姿勢が必要です。
このように、大手法律事務所を目指していない場合は、合格発表後に就活を始める方も少なくありません。
ただし、司法試験前から個別訪問の募集をおこなっている事務所もあるため、希望の事務所の採用時期をよく確認しておきましょう。
1-3:司法試験に合格しなかった場合
司法試験に不合格となった場合、冷静に次の選択肢を考えることが重要です。
まず検討すべきは、翌年に司法試験を再受験するかどうかです。
司法試験は、法科大学院を修了した年の4月1日から5年を経過するまでの期間に、最大5回受験することができます。
文部科学省の調査では、1回目の司法試験で不合格だった法科大学院修了生のうち、70%以上は司法試験の勉強を継続していることが分かります。
再受験する場合、一旦就職して、仕事と両立しながら司法試験勉強を続ける方法もあるでしょう。
勉強時間の確保が難しいですが、パートタイムで勤務時間を調整する選択肢も考えられます。
再受験を選ばない場合でも、法科大学院で培った法的思考力などを活かせる道は他にも多数あります。
2章:法曹以外で法務スキルが活かせる就職先
法曹以外で、法科大学院において培った法務スキルが活かせる就職先として、以下が挙げられます。
- 法律事務所(パラリーガル)
- 一般企業(法務担当)
- 公務員
- その他
それぞれ説明します。
2-1:法律事務所(パラリーガル)
パラリーガルは、法律事務所で弁護士の業務をサポートする事務職です。
主な業務は、法律文書の作成補助や法律・判例調査、依頼者との連絡調整などです。
弁護士資格がないため、法律相談や法廷活動はできませんが、専門知識を活かして弁護士の業務効率化に貢献できます。
年収は法律事務所の規模によって異なりますが、300万円〜500万円程度となります。
大手法律事務所であれば、企業法務や国際取引案件で高度な語学力・法律知識を持つパラリーガルが必要とされ、年収相場も高めです。
秘書業務とは分離して、新卒採用がおこなわれています。
パラリーガルは、法律事務所での経験が積めて、司法試験の再受験を目指す場合は、勉強のモチベーションが維持しやすいでしょう。
将来的には、企業法務に転職する道もあります。
2-2:一般企業(法務担当)
一般企業の法務部門も、法科大学院修了生の専門性が高く評価される職場です。
企業活動のグローバル化やコンプライアンス強化の流れから、法務人材の需要は年々高まっており、法科大学院修了生は即戦力として期待されるからです。
実際、経営法友会が2020年に実施した調査によると、回答企業の約3割において、弁護士資格のない法科大学院修了生が法務部に在籍しています。
在籍人数にすると、2015年の調査から、2倍近く増加しているのです。
参照:第114回法科大学院等特別委員会配布資料「企業法務の役割と求められる人材(経営法友会提出資料)」
業務内容としては、契約書の作成・審査、各種法令遵守のチェック、紛争対応などがあり、年収は企業規模や業界によってかなり差があります。
将来的には法務部長などの管理職を目指すことも可能で、キャリアパスの選択肢も広がります。
2-3:公務員
公務員には、法科大学院生の法的素養を活かせる職種が複数あります。
ただし、公務員試験は、司法試験より早い日程で実施されることが多いため、同じ年に挑戦する場合は、並行して取り組まなければなりません。
主な職種のおよその試験日程と、それぞれの業務内容は以下のとおりです。
■国家公務員(総合職、一般職)
総合職は3月~5月に筆記試験、6月に採用面接がおこなわれ、一般職は6月に筆記試験、7月に採用面接がおこなわれます。採用後は各省庁に配属され、法制度の企画・立案や国際交渉など、行政の中核業務に携わります。
■地方公務員
大卒程度の地方上級試験は、6月に筆記試験、7~8月頃採用面接がおこなわれます。条例や規則の制定・改廃、行政不服審査、住民からの法律相談対応などが業務内容です。
■国税専門官
5月に筆記試験、8月に採用面接がおこなわれます。税務署において、税務調査や税金の督促、滞納処分などをおこないます。
■裁判所事務官
5月~7月に筆記試験と面接がおこなわれます。裁判所に配属され、裁判の運営補助や総務・人事・会計などの事務全般に従事します。
公務員の業務内容は法律と密接に関係するため、上記以外にも法務スキルが活かせる職種はあります。ただし、公務員は年齢制限があり、30歳が上限となる場合が多いので、注意が必要です。
職種や年齢にもよりますが、年収は600万円〜700万円程度で、安定した雇用と福利厚生の充実が魅力です。
2-4:その他
その他にも、法科大学院修了生のスキルを活かせる職業は多数あります。
例えば、司法書士や行政書士などの法曹以外の士業を目指す道があります。
法科大学院での学習内容と重なる部分が多いため、比較的短期間での資格取得が可能でしょう。
また、法科大学院での学びを基礎に、大学院博士課程に進学して研究者を目指すことも考えられます。
法学研究者になれば、大学教員として後進の指導にあたりながら、専門分野の研究を深めることができます。
論文執筆や学会発表などを通じて、法学の発展に貢献することができるでしょう。
3章:法科大学院修了生は就職できない?不利な点3つを克服する方法
「もし司法試験に合格できなかったら、どこにも就職できないかも」という不安を抱える法科大学院生は、少なくないでしょう。
法科大学院修了生が、一般的な就職市場で不利になり得る点は以下の3つです。
- 年齢が高い点
- 実務経験がない点
- 法曹になるのを一度挫折している点
しかし、正しい対策をとれば、法科大学院での経験をむしろ強みに変えることができます。
ここでは、これら3つの不利な点をそれぞれ克服する方法を説明します。
3-1:年齢が高い点
法科大学院修了生は、学部卒と比べて年齢が高いため、就職活動で不利になる可能性があります。
ストレートで法科大学院まで進学しても、修了時には24~25歳となり、司法試験を5回全て受験すれば、30代に突入する方もいるでしょう。
新卒枠は基本的にポテンシャル採用のため、育成期間や柔軟性を考慮して若手の採用が優先される傾向があります。
この年齢的な不利を克服するためには、面接で素直さや柔軟性を示し、コミュニケーション能力で高評価を得ることが重要です。
まず、たとえ面接官が年下であっても、丁寧な態度で明るくハキハキと答えましょう。
面接官の質問の意図を正確に理解し、結論を端的に分かりやすく答えることで、年齢に関係なく相手に好印象を与えることができます。
また、相手企業の理念や文化に理解を示し、組織の一員として柔軟に適応できる姿勢をアピールしましょう。
加えて、年齢による不利を最小限に抑えるために、司法試験に固執せず、現実的に判断することも必要といえます。
3-2:実務経験がない点
法科大学院修了生が司法試験を複数回受験した場合、年齢が高いわりに実務経験がない点が、就職活動で不利になる可能性があります。
新卒採用では若い人材が求められ、中途採用では即戦力となる実務経験者が求められるからです。
この問題を克服するには、業界研究と企業研究を徹底的におこないましょう。
業界や相手企業が抱える法的課題を深く理解し、その解決に向けて、自身の法律知識をどう活かせるかをビジネス視点で説明できれば、効果的にアピールできます。
例えば、
「個人情報保護法の知識を活かし、顧客データ管理システムのコンプライアンスリスクを指摘できる」
「契約法の専門性を駆使し、契約書の問題点を特定して、有利な交渉材料を提供できる」
など、具体的な貢献を示しましょう。
企業研究をしっかりおこなえば、志望動機の説得力も高まり、自信を持って面接に臨めます。
3-3:法曹になるのを一度挫折している点
司法試験に合格していない法科大学院修了生は、就活先から「まだ法曹を目指しているのではないか」と懸念される可能性があります。
特に、採用後に司法試験の再受験のために早期退職するのではないかと思われ、採用を控えられるかもしれません。
この問題を克服するには、面接で司法試験への未練を示さず、企業で長く活躍する意思を伝えることが重要です。
具体的には、「法曹ではなく企業法務の専門家として、経営判断を法的に支える仕事に魅力を感じるようになった」といった、前向きな動機を示すことです。
また、法科大学院修了生歓迎の求人に応募すれば、司法試験の挫折経験でマイナス評価を受けずに済む可能性が高いでしょう。
以下のように、法務人材に特化した転職サイトやエージェントもあるので、上手く活用してください。
4章:法曹を目指すなら予備試験にも挑戦しよう
法科大学院生であっても、予備試験に挑戦することをおすすめします。
予備試験に合格できれば、法科大学院生にとっても大きなメリットがあるからです。
まず、司法試験の合格確立を大幅に高められます。
令和6年の司法試験において、予備試験合格者の合格率は約93%に達しています。法科大学院ルートの合格率約35%と比較して、圧倒的な高さを誇るのです。
また、予備試験合格者は、就職活動においても高く評価されます。
特に大手法律事務所では、予備試験合格者のみを対象とした採用プロセスがあり、積極的な採用がおこなわれています。
予備試験合格者の就活については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。
【予備試験合格者は超有利】就活の流れと内定獲得の秘訣を徹底解説!
予備試験は非常に難関な試験ではありますが、司法試験対策と重なる部分も多いので、適切に対策すれば十分に合格は狙えます。
法科大学院ルートと予備試験ルートの両方を視野に入れることで、法曹への可能性を最大限に広げましょう。
まとめ|法科大学院修了生の就活はキャリアプランの明確化が大切
法科大学院生の就活が本格化するのは司法試験日以降になりますが、在学中にサマークラークに参加することによって、採用に有利に働く可能性があります。
もし司法試験に不合格となった場合は、再受験をするか、法曹以外の道を検討するかを冷静に判断しなければなりません。
法曹以外で、法科大学院で培った知識を活かせる就職先は、主に以下のものが挙げられます。
- 法律事務所(パラリーガル)
- 一般企業(法務担当)
- 公務員
- 他の士業
- 研究職
司法試験合格にこだわって年齢を重ねると、年々就職が厳しくなっていくので、キャリアプランを明確にし、あらかじめ他の選択肢も視野に入れておくのが賢明です。
それでも法曹への志望が高い方が多いと思いますが、その場合は予備試験にもぜひ挑戦してください。
予備試験に合格すれば、司法試験に高い確率で合格でき、その後の就活も有利に進めることができます。
予備試験自体が難関すぎると思うかもしれませんが、予備試験上位合格者の戦略を学べば、決して不可能ではありません。
予備試験に合格していないか、総合順位が高くない予備校講師が多い中、「ヨビロン」では、予備試験1桁合格者が提唱する「客観的読解法」や「解法パターン」を学べます。
試験本番で初見の問題が出ても対応できるこれらの方法は、他では絶対に学べません。
今なら、以下のLINE登録により、「解法パターン」とその活用方法などを解説した動画が無料でご覧いただけます。
ぜひ、最難関試験合格への第一歩として、お役立てください。


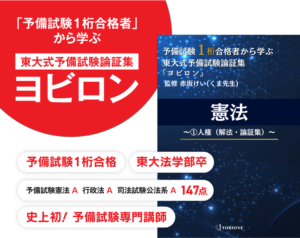



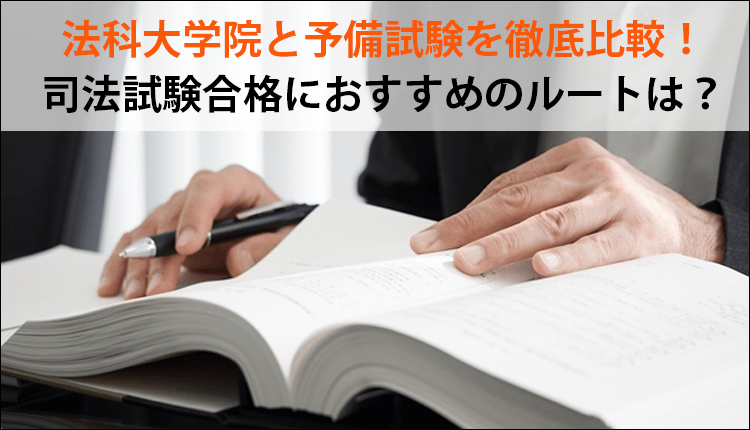
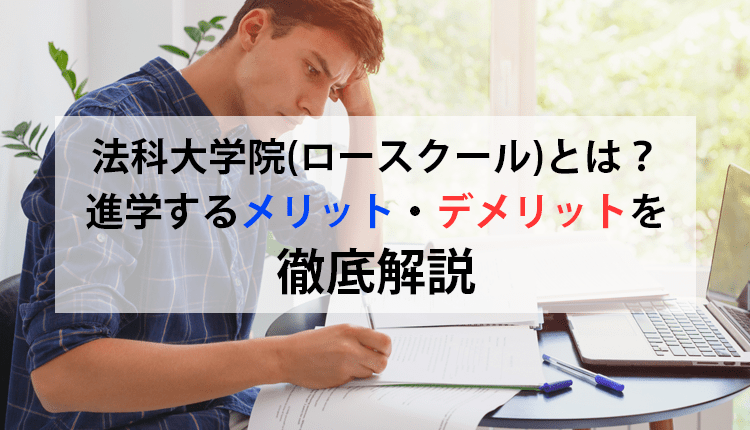
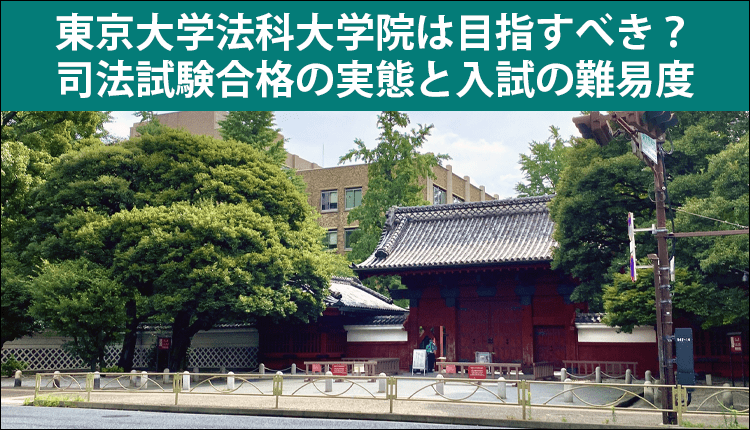
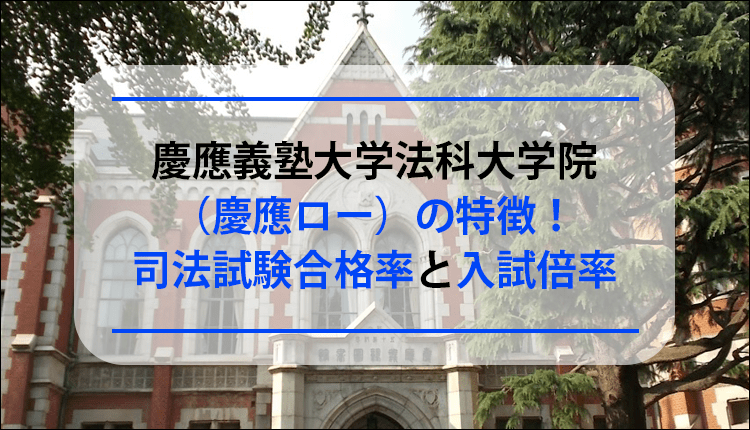
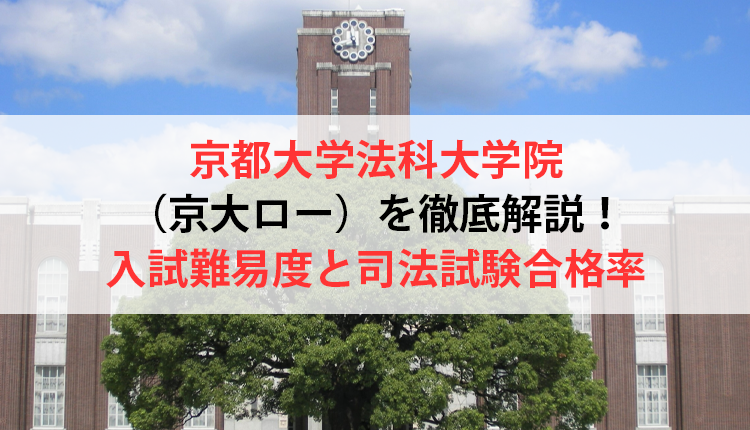
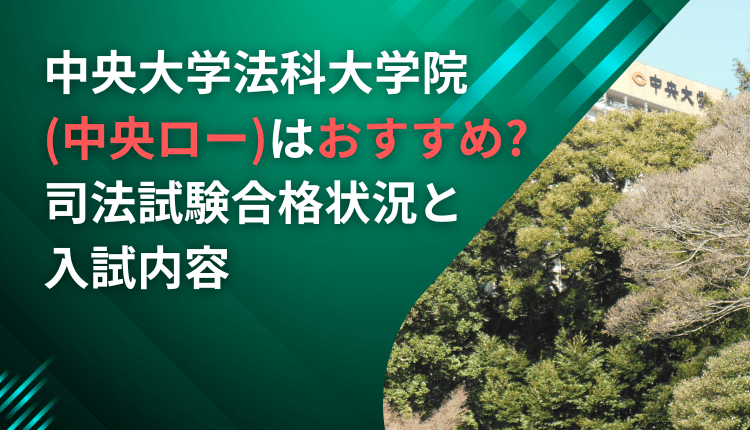
コメント