- 公開日:2025.01.20
- 更新日:2025.01.20
- #ステメン
- #東京大学法科大学院
【記載例付き】東大ローのステメンの攻略法!高評価を得るポイント3つ
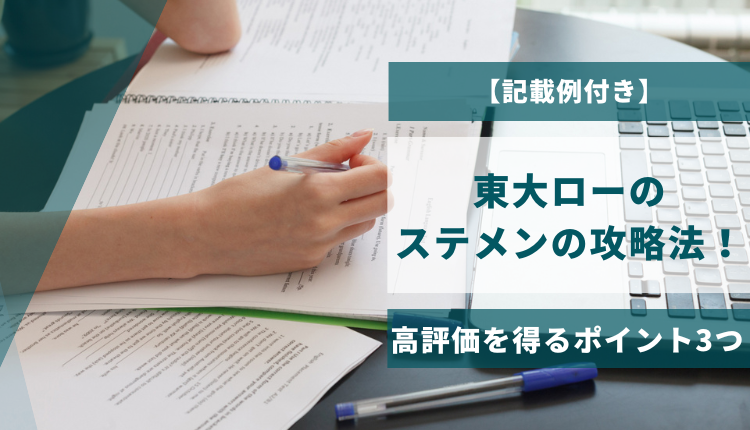
目次
この記事を読んで理解できること
- 東大ロー入試におけるステメンの位置づけ
- 【2025年度】東大ローのステメンの問いと文字数
- ステメンを書くときの3つのポイント
- ステメンの記載例
あなたは、
- 東大ローのステメンは合否にどう影響するのか知りたい
- 東大ローのステメンをどう書けばいいのか知りたい
- 実際に参考になる記載例を見てみたい
とお考えではありませんか?
東京大学法科大学院(東大ロー)の入試では、他の多くの法科大学院と同様、出願時にステートメント(ステメン)の提出が必要です。
当然ステメンも評価の対象になりますが、せっかく筆記試験の勉強を頑張っているのに、ステメンが原因で不合格になるのは絶対に避けたいですよね。
しかし、東大ローのステメンは他の法科大学院と比べて文字数が限られているため、問いに端的かつ的確に答える必要があり、書くのが難しいと感じる受験生は少なくありません。
しかし、この記事を読めば、東大ローのステメンの位置づけ、高評価につながる書き方、実際の記載例を知ることができ、合格レベルのステメンの完成イメージが明確になるでしょう。
具体的には、
1章で東大ロー入試におけるステメンの位置づけ
2章で東大ローのステメンの問いと文字数
3章でステメンを書くときの3つのポイント
4章で実際の記載例
について、詳しく解説します。
東大ローのステメンへの正しい対策方法を理解し、東大ロー入試合格をより確実なものにしていきましょう。
1章:東大ロー入試におけるステメンの位置づけ
東大ロー入試において、ステメンは入学者選抜の重要な評価対象の1つです。
入学者選抜では、「法律家として活動するための基礎となる問題発見能力、論理的思考力、文章作成能力、語学力等」が問われます。
このため、第一段階選抜で外国語能力および学業成績等を総合的に審査し、第二段階選抜では入学願書、外国語能力、学業成績、筆記試験の成績が総合的に審査されます。
参照:東京大学法科大学院「令和7年度学生募集要項 (2.(2)選抜方法)」
提出書類や筆記試験の評価の比重は「機械的な基準というものはない」とされ、ステメンを含む各要素の配点は公表されていません。
合否の決定にあたっては、すべての要素を「総合的に判断」するとしています。
したがって、東大ローのステメンは、受験者の基礎的な能力を総合的に判断するための材料の1つとして位置づけられているといえます。
具体的な配点は明らかではないものの、合格者よりも筆記試験で高得点をとった受験者が、ステメンが原因で不合格になる事例もあるため、決して軽視しないようにしましょう。
なお、東大ロー入試の全体の概要や筆記試験の内容が知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
東京大学法科大学院は目指すべき?司法試験合格の実態と入試の難易度
2章:【2025年度】東大ローのステメンの問いと文字数
東大ローでは、出願書類の「志望理由書」がステートメントにあたり、未修者と既修者で課題が異なります。
他の法科大学院では2,000字以上の文字数が設定されているのに対し、東大ローは未修者で1,200字以内、既修者は800字程度と短い文字数制限が特徴です。
ここでは、それぞれのステメンで問われる内容について説明します。
2-1:未修者の場合
法学未修者のステメンで問われる内容は、以下のとおりです。
以下の2つの事項について、1,200 字以内で簡潔に記述すること。また、自己が法曹養成専攻に入学するのにふさわしいと考える特記事項がある場合は、併せて記述すること。
① これまで大学や社会で学んできたこと、経験してきたこと及び東京大学法科大学院を志望する理由
② あなたの目指す法曹像
引用元:東京大学法科大学院「志望理由書(法学未修者)」
未修者コースには、法学部以外の学部出身者や社会人など、多様なバックグラウンドを持つ人材が志願します。
そのため、なぜ今まで法律を学んでなかったのか、そしてなぜ今から法曹を目指すのかという点について、説得力のある説明が必要です。
「自己が法曹養成専攻に入学するのにふさわしいと考える特記事項」は任意記載ですが、できるだけ記載しましょう。
東大ローは「社会に貢献しようという高い志」を持つ人材を求めています。
その志の具体性を裏付ける経験(たとえば資格・表彰歴、課外活動での実績、社会貢献活動など)を示せば、志望者としての適性をより効果的にアピールできるからです。
2-2:既修者の場合
法学既修者のステメンでは、以下のように問われます。
これまでの勉学の状況等をふまえて、800 字程度で簡潔に記述すること。また、自己が法曹養成専攻に入学するのにふさわしいと考える特記事項がある場合は、併せて記述すること。
引用元:東京大学法科大学院「志望理由書(法学既修者)」
既修者はすでに法律の基礎を学んでいることから、主にこれまでの法学の学習経験と東大ローでの発展的な学習への意欲が問われます。
未修者よりもさらに限られた文字数で、自身の法学学習の成果と志望理由を簡潔かつ論理的に説明しなければなりません。
特記事項(自己PR)では、法律相談の経験やゼミでの研究実績など具体例を示しながら、東大ローが養成しようとする法曹像の素養がある点を効果的にアピールしましょう。
3章:ステメンを書くときの3つのポイント
東大ローのステメンを書くにあたって意識すべきポイントは、以下の3つです。
- 教育理念と求める人物像との整合性
- 問いへの的確な回答
- 具体的事実と志望理由の論理的な結び付け
それぞれ説明します。
3-1:教育理念と求める人物像との整合性
ステメンは、その法科大学院の教育理念と求める人物像を、十分に理解したうえで書く必要があります。
東大ローが掲げている「教育理念」は以下のとおりです。
国民や社会に貢献する高い志と強い責任感・倫理観を持ち、先端的法分野や国際的法分野でも活躍しうる、優れた法律実務家を養成することを目的とする。
引用元:東京大学法科大学院「教育の理念及び目標」
これを実現するために、以下のように「求める学生像」が設定されています。
社会に貢献しようという高い志をもって法律の学習に取り組み、法の体系・理論・運用を理解したうえで、
法的問題を解決するために自らの思考を発展させることのできる者。
引用元:「令和7(2025)年度 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 専門職学位課程(法科大学院)学生募集要項」
よって、以下のような点について積極的に示したうえで、東大ローで学ぶ必要性について説明すれば、高く評価される可能性があります。
■社会に貢献する高い志
単に「司法試験に合格したい」という動機ではなく、将来法曹としてどのような社会問題に取り組み、どのように解決していきたいのかを明確に説明することです。
■先端的法分野や国際的法分野への関心や意欲
既存の法分野だけでなく、科学技術の発展や国際化に伴う新しい法的課題に対して、具体的な問題意識や経験を挙げると良いでしょう。
■問題解決力の素養
学習や課外活動などで直面した課題に対して、どのように取り組み、解決に至ったのかを具体的に示すことが考えられます。
3-2:問いへの的確な回答
問われたこと全てに対して、漏れなく的確に答えることは非常に重要です。
問われたことに答えていなかったり、設問の意図を正しく理解できていなかったりする回答では、法曹に必要な読解力や表現力が不足していると判断されてしまうからです。
また、回答の趣旨が明確に伝わるように、最初に結論を端的に示し、その後にそれを裏付ける経験や実績を記載しましょう。
未修者の場合は、「これまでの経験」「東大ローを志望する理由」「目指す法曹像」の3点について、最も重要な経験と将来像を軸に簡潔に説明します。
既修者の場合は、「これまでの勉学の状況等を踏まえて」という条件に従い、法学学習の中で得た問題意識や東大ローへの志望理由を中心に記載します。
特に、他の法科大学院ではなく東大ローを志望する理由を明確にすることは重要です。
以下の記事では、東大ローの教育の特色についても解説しているので、参考にしてみてください。
東京大学法科大学院は目指すべき?司法試験合格の実態と入試の難易度
一度完成させた後も、全ての問いに過不足なく答えられているかを必ず確認しましょう。
3-3:具体的事実と志望理由の論理的な結び付け
ステメンで重要なのは、実績や経験をたくさん書くことではなく、具体的な事実と志望理由を論理的に結びつけ、一貫した説得力のある文章を作り上げることです。
なぜなら、志望動機の強さや、東大ローの求める法曹像となる素養を備えているかを評価するためには、具体的な事実に基づいた説得力のある説明が不可欠だからです。
予備試験という選択肢がある中で、なぜ法科大学院に進学したいのかという点も、明確にする必要があります。
特別な経験がなくても、大学や社会での学びの中で、自分が解決したいと思った社会問題について、以下の3ステップで記述すれば説得力のある志望理由となるでしょう。
- 具体的な問題との出会いと関心を持った理由
- 問題の分析と法的解決の必要性
- その実現に向けた東大ローでの学びの必要性
4章:ステメンの記載例
これまで紹介したポイントを踏まえて、未修者・既修者それぞれの具体的な記載例を紹介します。
なお、これらの例はあくまで考え方の参考としていただくものであり、決して文章をそのまま利用することのないようにしてください。
4-1:未修者の場合
以下は、架空の大学生を想定した未修者のステメンの記載例です。
私は、中小企業の国際展開を法的側面からサポートする弁護士を目指しています。
経済学部で学ぶ中で、海外展開を図る日本企業が直面する法的課題に関心を持ちました。特にゼミでは、越境EC事業を展開する日本企業の事例を分析し、進出先の消費者保護規制や個人情報保護法制への対応の遅れが、事業機会の損失につながることを明らかにしました。また、経済学の視点でビジネスモデルを分析する中で、現地の規制環境の理解が、グローバル戦略に大きな影響を与えることを実感しています。
学部3年次からは大学の学生法律相談部に所属し、国際取引に関する判例研究を行いました。特に国際的なデータ移転規制の研究を通じ、取引相手国の法的な考え方を理解することの重要性を認識しました。また、輸出企業の方から「国際取引に詳しい弁護士が少なく、法的リスクを十分に検討できない」という声を聞く機会があり、専門性の高い法的支援の必要性を痛感しています。
さらに、投資銀行でのインターンシップでは、海外展開を目指す取引先企業の多くが、現地の法制度や商習慣の違いに戸惑い、進出を躊躇している実態を目の当たりにしています。一方で、適切な法的助言を得られた企業は、現地企業との取引や事業提携を着実に進めていることも分かりました。
これらの経験を通じ、中小企業の海外展開を支援する法的専門家が必要だと強く感じています。そのため、私は、国際取引法や現地法制度の知識を活かしながら、契約書の作成支援から紛争解決まで、海外展開に伴う法的リスクをトータルにサポートする弁護士を目指しています。
貴校を志望する最大の理由は、既存の日本の法制度にとらわれず、国際的な視野から法的問題に取り組む能力を養える点にあります。特に、海外大学との提携による「アメリカ法」の授業や、「グローバル・ビジネスロー・サマープログラム」など、第一線の外国人研究者から直接学べる機会は、国際的な法的思考を養う上で他に代えがたい環境です。
また、基礎法学を重視し、「法のパースペクティブ」や「現代法の基本問題」を必修とする貴校の教育方針も、私の目標に合致します。なぜなら、国際取引における法的問題は、単なる実定法の知識だけでは解決できず、各国の法制度の背景にある考え方や、社会の変化に対応した新しい制度設計の視点が不可欠だからです。
なお、学生法律相談部の活動では、市民の労働問題に寄り添い、個別の状況に即した解決策を提案してきました。この経験を通じ、法的支援を通じて社会に役立つ意義を実感し、貢献する志と法的問題を解決する思考力を培っています。また、学部の英語コースで培った語学力(TOEIC 850点)は、国際的な学びの場で活かせると考えます。
経済学的思考と国際法務の専門性を組み合わせ、日本企業のグローバル展開を支える法曹となるため、貴校への入学を志望いたします。
4-2:既修者の場合
以下は、架空の大学生を想定した既修者のステメンの記載例です。
私は、企業法務の中でも特に労働法分野に強い弁護士として、新しい働き方を法的に支援したいと考えています。
法学部での学修を通じ、労働基準法の労働時間規制がテレワークに十分対応できていない現状に問題意識を持ちました。そのため、労働法ゼミでは、在宅勤務における労働時間の算定や管理監督者の範囲など、具体的な法解釈上の課題を研究しました。また、諸外国の立法例も調べ、EUの「つながらない権利」の法制化など、日本が参考にすべき制度があることも学びました。
労働法演習では、プラットフォームワーカーの労働者性に関する裁判例を研究し、従来の労働者概念では対応できない問題が増えていることを実感しています。このような新しい法的課題に対応するには、単なる実定法の解釈にとどまらず、労働法の基礎にある理念に立ち返り、国際比較を踏まえた新たな法的枠組みを構築する必要があると考えるようになりました。
貴校は、「法のパースペクティブ」など基礎法学を必修とし、法制度の本質的理解を重視されています。また、「グローバル・ビジネスロー・サマープログラム」では、各国の実務家から労働法制の最新動向を直接学べます。このような理論と実務の双方を重視する教育環境は、働き方改革やグローバル化に伴う新たな労働問題に対応できる法曹を目指す私にとって、最適な学びの場だと確信しています。
また、私は学部で労働判例研究会を立ち上げ、在宅勤務中の労災認定基準について、企業10社へのヒアリング調査も実施しました。この経験を通じ、法的問題を多角的に捉え、実効的な解決策を導く視点を養うことができました。
貴校での学びを通じ、これまでに培った理論と実務を結びつける力をさらに磨き、新しい時代の法的課題に挑む法曹として社会に貢献したいと強く願っています。
まとめ|東大ローのステメンは少ない文字数で説得力を持たせよう
東大ローのステメンは、未修者で1,200字以内、既修者は約800字程度と、他の大学院よりも文字数が限られているのが特徴です。
分量が少ないから重要視されていないわけではなく、簡潔かつ論理的に説明する能力が試されている可能性があります。
ステメンの出来が合否に影響した事例もあるため、主に以下の3つのポイントを押さえながら、説得力のある文章を作成しましょう。
- 「社会に貢献する高い志」「先端的・国際的法分野への意欲」「問題解決力の素養」といった要素を意識すること
- 問われていること全てに過不足なく答えること
- 具体的な事実や経験と志望動機を論理的に結びつけること
本記事で紹介したこれら3つのポイントと記載例を活用しながら、あなたならではの魅力が伝わるステメンを完成させてください。


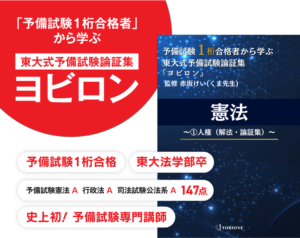



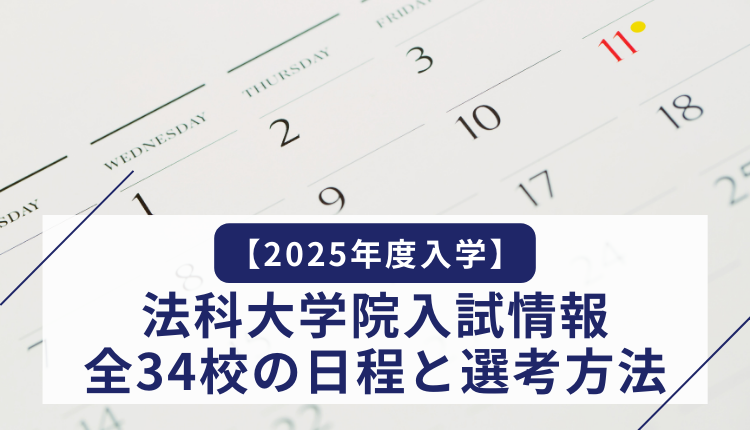
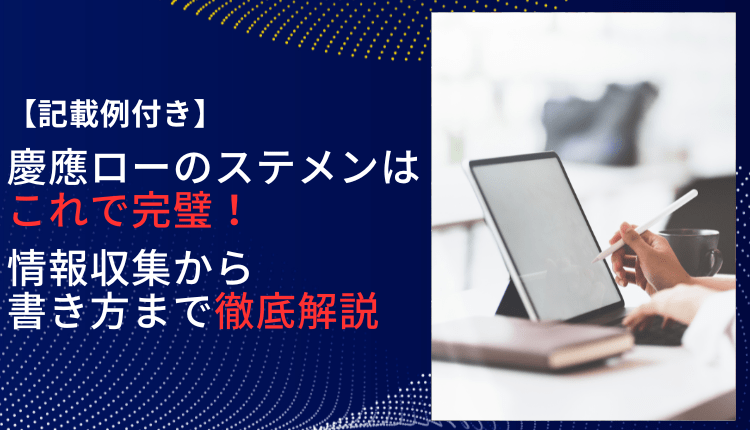
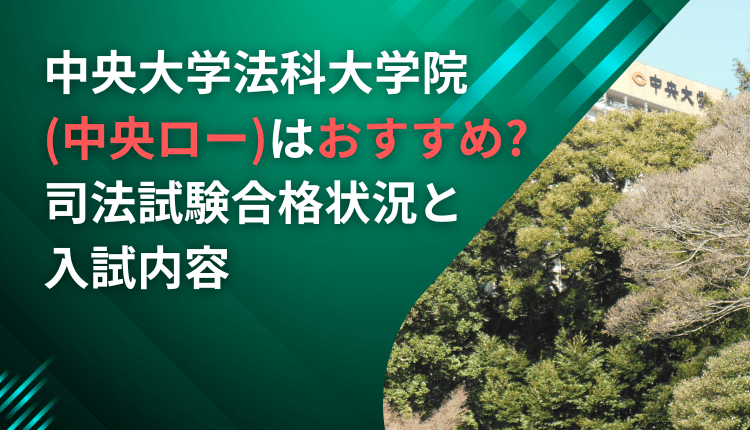
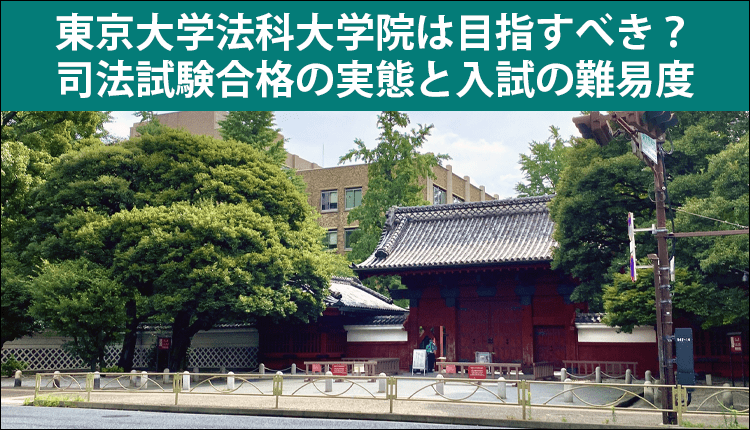
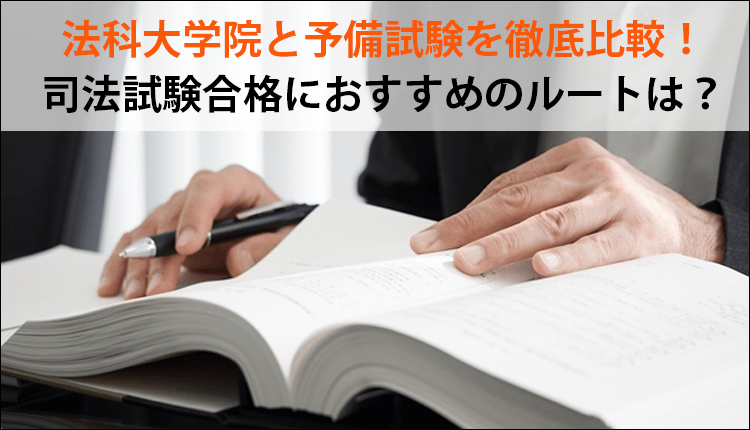
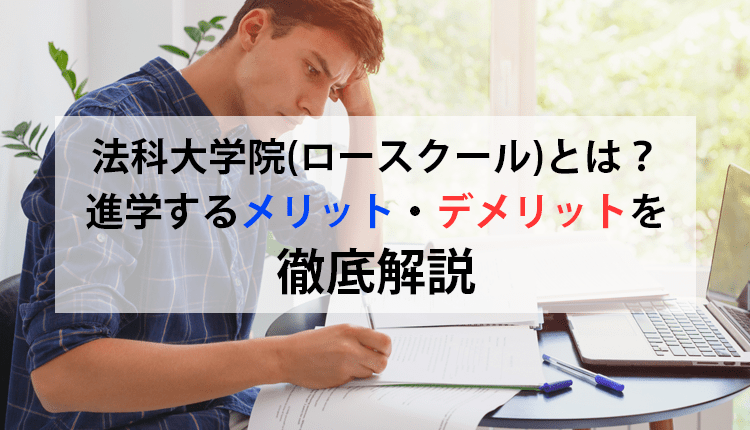
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。