【予備試験合格】失敗しない予備校の選び方、6つのチェックポイント

この記事を読んで理解できること
- 予備試験合格には予備校の選び方が重要
- 失敗しない予備校の選び方6つのチェックポイント
- 予備試験の対策に「ヨビロン」をオススメする理由
あなたは、
- 予備試験に向けて予備校が重要な理由は?
- 失敗しない予備校の選び方が知りたい
- 自分に合った予備校で予備試験に合格したい
などとお考えではありませんか?
予備試験受験生にとって予備校選びは、最初の重要なステップであり、予備試験合格を目指すためには必須といえます。
なぜなら、実績のある講師陣や質の高いテキスト、充実したカリキュラムを備えた予備校を選択することで、予備試験合格への近道となるからです。
そのため、各予備校の特徴を十分に理解し、自分のニーズや学習スタイルに合った選択をすることが、最終的な合格につながります。
安易な価格比較や表面的な評判だけでなく、実際に体験学習を行うなど、総合的な判断で選ぶことをお勧めします。
また最も大事なのは、予備試験の出題傾向に即した内容で、予備試験の高得点合格者が作成した、実践的な教材で学ぶことです。
そこでこの記事では、
1章では、予備試験合格には予備校の選び方が重要
2章では、失敗しない予備校の選び方6つのチェックポイント
3章では、予備試験の対策に「ヨビロン」をオススメする理由
について解説します。
「ヨビロン」は、予備試験1桁合格者が作成した、予備試験に特化した予備試験論証集の教材です。
この記事を読んで、予備試験に向けた予備校選びの重要性をしっかり理解して、合格への一歩を進めて下さい。
1章:予備試験合格には予備校の選び方が重要
予備試験に合格するためには、
- なぜ予備校の選び方が合否を分けるのか
- 独学との比較でみる予備校のメリット
について解説します。
1-1:なぜ予備校の選び方が合否を分けるのか
なぜ予備校の選び方が合否を分けるのか、その理由は以下の通りです。
■予備試験は難易度が極めて高い
予備試験に合格すると、司法試験の受験資格が与えられます。
つまり予備試験は、法科大学院修了者と同等の能力があるかどうかを判定する試験のため、法科大学院入試より科目数が多く、難易度も高くなります。
合格率も例年4%前後と、非常に厳しい試験です。
■予備校での受講が学習の基盤となる
予備試験合格には、効率的かつ効果的な学習方法の確立が不可欠であり、予備校の受講は学習の基盤となるため、その選択が合否を大きく左右します。
また、予備校によって教育方針や指導方法が大きく異なります。
例えば、基礎重視型の予備校もあれば、応用力育成に重点を置く予備校もあります。
自分の学習スタイルや現在の実力に合わない予備校を選んでしまうと、貴重な時間とコストを無駄にしてしまう可能性があります。
1-2:独学との比較でみる予備校のメリット
予備校に通うことには、独学では得られない以下のような3つのメリットがあります。
- 体系的なカリキュラムが用意されている
予備試験では憲法、民法、刑法などの法律科目に加え、一般教養科目まで幅広い知識が必要とされます。
予備校では、これらの科目を効率的に学習できるようにカリキュラムが組まれているため、学習の漏れを防げます。
- 経験豊富な講師による指導を受けられる
予備試験に精通した講師陣が、試験傾向を踏まえた的確なアドバイスや、答案作成のコツなど、独学では得難い実践的な指導を提供してくれます。
- モチベーションを維持するサポートが得られる
予備試験の学習は長期戦となりますが、予備校では同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨や、定期的な模試による実力確認など、モチベーションを保つための環境が整っています。
以上のように、予備校は予備試験合格への近道となる可能性が高いため、その選択は慎重に行う必要があります。
適切な予備校選びは、限られた時間と努力を最大限に活用し、効率的に合格を目指すための重要な第一歩となるのです。
2章:失敗しない予備校の選び方6つのチェックポイント
失敗しない予備校の選び方のチェックポイントは次の6つです。
- 学習環境の充実度を確認する
- 講師の合格実績と質、相性を見極める
- カリキュラムと教材の質を評価する
- フォロー体制とサポートシステムを確認する
- 予算と費用対効果を検討する
- 合格実績と評判を正しく評価する
それぞれ解説します。
2-1:学習環境の充実度を確認する
予備試験は、独学での合格は極めて難しいため、最後まで勉強を継続できる、適切な学習環境を提供してくれる予備校を選ぶことが重要です。
学習環境を確認する際には、以下の点に注意しましょう。
- 他の受講生との切磋琢磨の機会
- 講師による的確な指導とアドバイス
- 体系的なカリキュラムと進捗管理システム
- 質問対応の充実度
- 校舎の設備や自習室の環境
できれば事前に体験学習や校舎見学を行い、実際の学習環境を体感することをお勧めします。
特に通信講座の場合は、オンライン学習システムの使いやすさやサポート体制をしっかり確認しましょう。
学習環境やサポート体制が充実していない予備校を選んでしまうと、合格への道のりが遠くなるので注意が必要です。
2-2:講師の合格実績と質、相性を見極める
講師の質は、予備校選びにおいて最も重要なポイントの1つです。
以下の観点から評価することをお勧めします。
- 講師自身の予備試験合格体験や学習経験
講師自身が予備試験の合格者であれば、予備試験合格に向けた大変心強い味方になるでしょう。
なぜなら、実際の合格体験や学習経験から、受験生の視点に立った実践的なアドバイスが期待できるからです。
特に高順位合格者であれば、より予備試験に直結する実績のある対策が学べます。
また、講師による添削は答案の評価として非常に大切ですが、そもそも講師が高順位合格者でない場合は、大事なポイントを押さえきれていないケースもあります。
講師自身に予備試験合格実績がない場合は、あなたと同じ立場にあるともいえます。
予備試験合格を目指すならば、高順位合格者の講師から学ぶことが最も有効な学習法です。
- 講義スタイルと自分との相性
体験授業などを通じて、講師の説明方法や授業の進め方が自分に合っているかを確認することが重要です。
良い講師は、以下のような特徴を持っています。
- 講義がわかりやすく、説明が論理的
- 興味を引き出す話術と教授法
- 実践的な知識と経験の共有
- 質問しやすい雰囲気づくり
- 受講生の理解度に合わせた指導
講師との相性は学習効率に大きく影響するため、必ず事前に講義を体験するようにしましょう。
多くの予備校で無料体験講座を提供しているので、積極的に活用することをお勧めします。
2-3:カリキュラムと教材の質を評価する
予備校のカリキュラムと教材は、効率的な学習を左右する重要な要素です。
カリキュラムについては、基礎から応用まで段階的に学習できる構成になっているか、また予備試験の出題傾向に即した内容であるかを確認しましょう。
特に、短答式試験と論文式試験の両方に対応できる総合的なカリキュラムであることが重要です。
■カリキュラムのポイント
- 基礎から応用までの体系的な構成
- 短答・論文試験対策の充実度
- 実践的な演習の機会
- 進度に合わせた柔軟な学習計画
教材は日々の学習の基礎となるものです。
サンプルテキストを確認し、自分の学習スタイルに合っているかを判断しましょう。
最新の出題内容に対応した教材が、更新・提供されているかも重要なポイントです。
できれば、予備試験で高得点を取った合格者が作成した、実践的な教材で学ぶのがベストだといえるでしょう。
2-4:フォロー体制とサポートシステムを確認する
予備校で学習するうえで、フォロー体制とサポートシステムを確認することも大事なポイントの1つです。
予備試験や司法試験に向けた長期の学習期間中、様々な困難に直面することがあります。
充実したフォロー体制は、そうした困難を乗り越えるための重要な支援となるでしょう。
主なチェックポイントとしては、
- 質問制度の充実度
- 個別カウンセリングの有無
- 模擬試験と添削指導の頻度
- 学習相談の機会
- 合格者との交流会や情報交換の場
- 奨学金制度や分割払いなどの経済的サポート
などがあげられます。
2-5:予算と費用対効果を検討する
ここまで解説したチェックポイントをふまえて、予算と費用対効果を検討することも重要です。
予備校の費用は決して安くありませんが、単純な価格比較だけで判断するのは危険です。
以下の観点から総合的に判断しましょう。
- 講座内容と価格のバランス
- 付加サービスの内容
- 分割払いや奨学金制度の有無
- 返金制度やフォロー制度の充実度
- 合格までのトータルコスト
安易な価格比較や表面的な評判だけでなく、予備校での勉強や学習環境で自分が合格できるイメージが持てるか、総合的な判断を行うことをお勧めします。
2-6:合格実績と評判を正しく評価する
合格実績は重要な指標ですが、それだけで判断するのは適切ではありません。
以下の点に注意して、正しく評価しましょう。
- 直近の合格実績
- 受講生の属性(社会人・学生など)との関連
- 実際の受講生の声
- 合格者の具体的な体験談
- 口コミやSNSでの評判
予備校のサイトで合格者の体験談が載せられている場合は、どうしても予備校寄りの感想が載せられているケースもあります。
できれば、合格者の勉強法の共通点や、スランプ脱出法、受験後の反省など、自身の学習や行動にプラスになる情報をより多く集めることが重要です。
ここまで予備校選びで失敗しないポイントを解説してきましたが、中でもなにより重要なのは「2-2」で解説した「講師の合格実績」です。
3章:予備試験の対策に「ヨビロン」をオススメする理由
「ヨビロン」は、予備試験1桁合格の講師が、予備試験に合格するための独自の方法を公開した予備試験に特化した論証集です。
予備試験の対策に「ヨビロン」をオススメする理由は、次の2つです。
- 予備試験1桁合格者の独自ノウハウが学べるから
- 初見の問題でも点が取れるポイントがわかるから
それぞれ解説します。
3-1:予備試験1桁合格者の独自ノウハウが学べるから
予備試験の難易度が非常に高いのは、予備校などで予備試験に特化した勉強法が浸透していないことも、1つの要因としてあげられます。
「ヨビロン」は、予備試験対策に特化した論証集で、講師である予備試験1桁合格者の独自ノウハウが学べます。
「ヨビロン」は、他の予備校の予備試験に合格していない講師が作成した従来の論証集と異なり、実際に予備試験で高得点を取った合格者が作成した実践的な教材です。
「ヨビロン」は、基礎知識を網羅しているだけでなく、最新の判例や学説にも対応しており、受験生が過去問だけでは補えない知識を効率よく吸収できるように設計されています。
また、司法試験とは異なる予備試験に対応した解き方も詳細に説明されており、司法試験対策をそのまま応用する誤りを防ぎます。
予備試験の過去問に加えて、司法試験の過去問も対策することで、予備試験を無双できる実力を身に付ける内容で構成されています。
3-2:初見の問題でも点が取れるポイントがわかるから
予備試験1桁合格者が作成した教材「ヨビロン」では、予備試験で出題される問題の考え方のパターンを体系化し、初見の問題に対応できる独自ノウハウが学べます。
多くの予備校では、「論証パターン」や講師の解答例を繰り返し学ぶ方法が一般的です。
しかし、この方法では初見の難問に対応できず、受験生が「何を問われているか分からない」という状況に陥ることが多いです。
特に、予備校の教え方は講師のセンスに依存しており、体系的な「解法パターン」が教えられていないため、予備試験に特有の問題への対応が難しいという点が問題視されています。
「ヨビロン」では、他の予備校・講師では学べない、予備試験特有の対策が得られるため、上位で合格できる確実性の高い実践的な学習が期待できます。
「ヨビロン」は、2024年11月時点で憲法に関する教材を販売していますので、ぜひ活用してください。
まとめ:予備試験に合格するための予備校の選び方
予備試験合格を目指す受験生にとっては、予備校選びは最も重要な選択といってもいいでしょう。
「合格率:例年4%前後」という非常に難しい予備試験に対して、予備校での学習の充実度が合否を大きく左右します。
■失敗しない予備校の選び方のチェックポイントは次の6つです。
- 学習環境の充実度を確認する
- 講師の合格実績と質、相性を見極める
- カリキュラムと教材の質を評価する
- フォロー体制とサポートシステムを確認する
- 予算と費用対効果を検討する
- 合格実績と評判を正しく評価する
予備試験に合格していない予備校講師が多い中、「ヨビロン」では、予備試験1桁合格者の講師から、試験本番で初見の問題が出ても対応できる方法が学べます。
予備試験1桁合格の専門講師から学べる「ヨビロン」を、ぜひ、最難関試験合格への第一歩としてお役立てください。


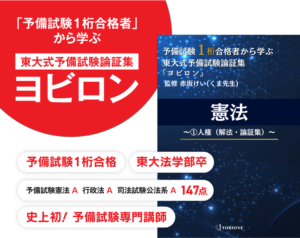




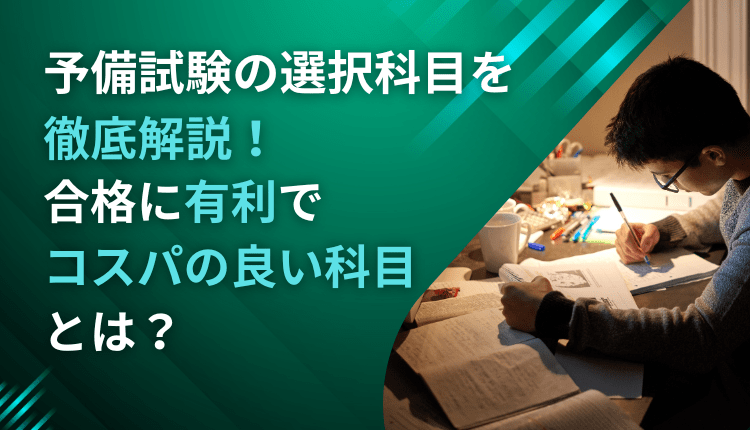
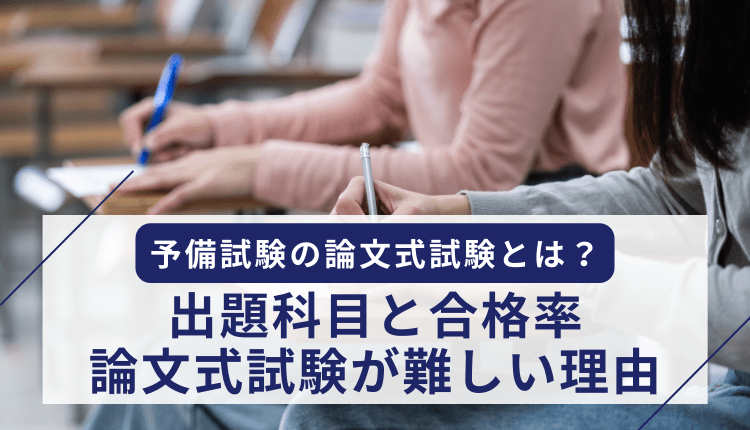
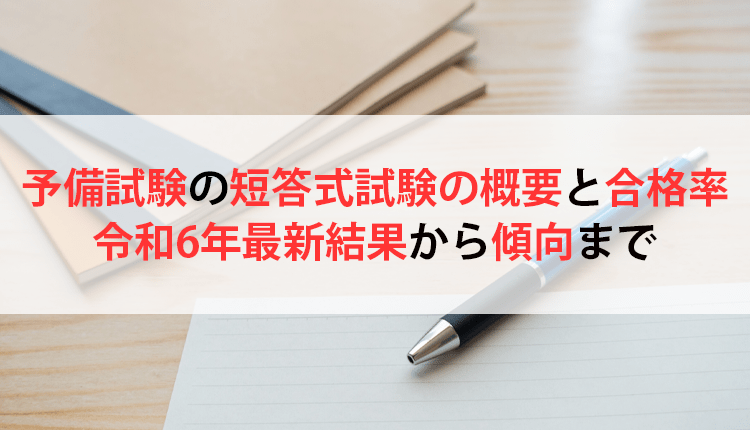

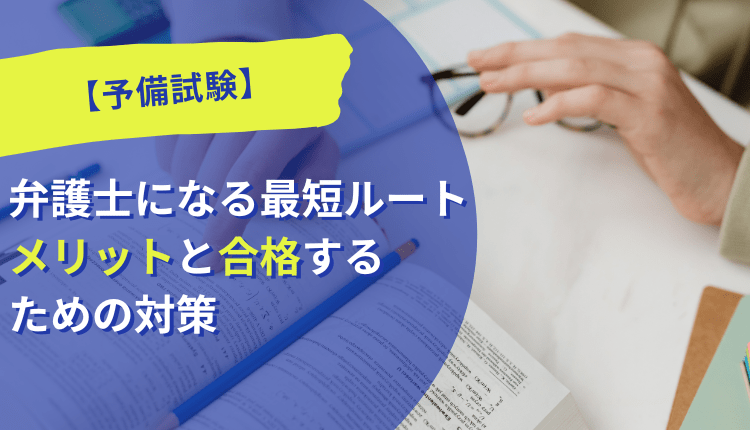
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。