【憲法入門6】学問の自由と大学の自治を徹底解説!
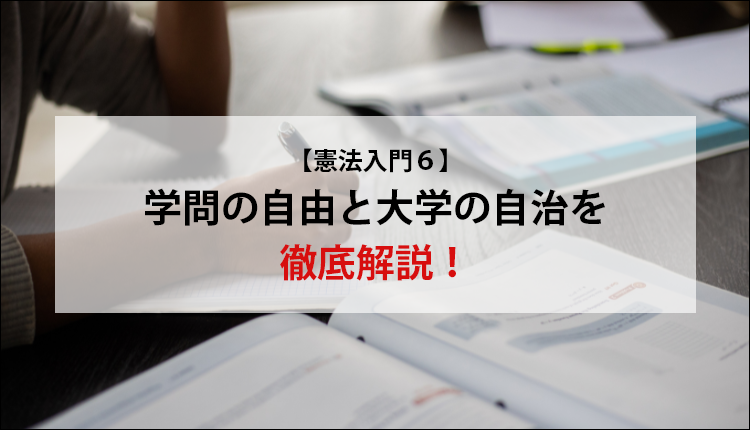
目次
この記事を読んで理解できること
- 学問の自由について
- 大学の自治について
- 学生の学問の自由について
この記事は、
- 学問の自由とは何かを知りたい
- 大学の自治とは何かを知りたい
- 学生に学問の自由は保障されるのか知りたい
といった方におすすめです。
学問の自由は精神的自由権の一つですが、思想良心の自由や表現の自由と比べると、ややマイナーな人権というイメージがあるかもしれません。
しかし、実は学問の自由は司法試験でも頻出の論点なので、理解しているかどうかで大きく差がつくといえるでしょう。
そこで、この記事では、
第1章で学問の自由とはどのような権利なのか、
第2章で大学の自治とは何か、
第3章で学生に学問の自由は保障されるのか、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 学問の自由について
この章では、
- そもそも学問の自由とは何なのか
- なぜ学問の自由は重要なのか
について解説します。
1-1 学問の自由とは何か
まずは憲法の条文を読んでみましょう。
第二十三条
学問の自由は、これを保障する。
このように、憲法の条文はとてもシンプルです。
これだけでは、学問の自由が何なのかわからないので、判例を手がかりにしてみましょう。
東大ポポロ事件判決(最判昭和38年5月22日)などによれば、学問の自由とは
- 学問研究の自由
- 学問発表の自由
- 教授の自由
を保障するものであると考えられています。
それぞれ説明します。
1-1-1 学問研究の自由
学問研究の自由とは、公権力から干渉されることなく、自由な立場で研究ができる自由のことです。
学問研究に政府が干渉してくると、真理の探究が妨げられてしまうおそれがありますし、学問とは知的活動であり、普通はどのような研究をしようと実害をもたらすことはないため、強く保障されます。
他方、近年では科学技術の発達により、先端科学研究が社会に直接の害悪をもたらすおそれもあります。
遺伝子研究などがその一例です。
このような研究は、まかり間違えば人間の尊厳を根底から覆すような取り返しのつかない事態を生む可能性も否定できません。
そのため、重大なプライバシーや生命・身体などの極めて重要な法益を守るためには、必要最小限の制約は許されると考えられています。
1-1-2 学問発表の自由
学問発表の自由とは、学問研究の結果を発表する自由のことです。
研究をすることが自由でも、それを他者に公開できなければ意味がないため、学問研究と同じように保障されます。
ただし、前述したように、先端科学研究は社会に直接の害悪をもたらすおそれもあります。
例えば、原子力爆弾の研究結果を発表した場合、悪用される危険性が高いと考えられます。
だからといって、少しでも危険があれば簡単に制約されるのでは学問の自由を保障した意味がなくなってしまうので、発表を制約するには、それによって明らかに差し迫った危険が具体的に予見される必要があると考えられます。
1-1-3 教授の自由
教授の自由とは、大学教授などの研究者が、研究結果を大学の講義や演習において教授する自由のことです。
法学部の授業で、大学の先生が自分の見解を自由に教えることができるのも、教授の自由が保障されているからなのです。
なお、旭川学力テスト事件判決(最判昭和51年5月21日)によれば、初等中等教育においても、学校教師に教授の自由は一定の範囲で認められますが、大学の場合とは異なり完全な自由ではなく、制約を受けることになります。
大学の学生には批判能力があり、どの教授の授業を受けるかを選べるのに対し、初等中等教育の場合は生徒に十分な批判能力がなく、教師を選ぶこともできないので、授業の内容について一定の水準を確保する必要があるからです。
1-2 学問の自由が重要な理由
では、なぜ学問の自由は重要な権利として憲法で保障されるのでしょうか。
その理由は、歴史的な経緯を遡る必要があります。
皆さんは、天皇機関説事件という出来事をご存知でしょうか?
明治憲法下において、美濃部達吉という憲法学者が、「天皇は法人たる日本という国家の機関である」という学説を提唱しました。これが天皇機関説です。
この学説は、天皇への不敬であるとして貴族院議員などから激しい非難を受けました。
その結果、当時議員でもあった美濃部は辞職に追い込まれ、さらに著書が発禁処分にまでなりました。
このように、学問とは国にとって都合の悪い研究を伴うこともあるので、弾圧されるおそれがあります。
そこで、日本国憲法では、学問の自由を保障することにより、研究内容に政府が干渉できないようにしたということです。
|
■第1章のまとめ
・学問の自由が重要な理由 →天皇機関説事件のように、国にとって都合の悪い研究が弾圧されるおそれがある。 |
第2章 大学の自治について
この章では、大学の自治について解説します。
2-1 大学の自治とは何か
大学の自治とは、大学内部の管理・運営を大学の自主的な決定に任せるという原則です。
学問の自由が保障されるためには、教授個人が自由に研究できるだけでなく、大学という組織自体が国などから不当な影響を受けないことが必要なので、憲法は学問の自由と共に大学の自治を保障していると解釈されています。
2-2 大学の自治の内容
大学の自治は、大きく分けて
- 人事の自治
- 施設・学生の管理の自治
の2つがあります。
2-2-1 人事の自治
人事の自治とは、教授などの研究者の人事について、大学の自主的判断に委ねるという原則です。
誰を教授として採用するかといった問題に国が干渉できるとすると、結果的に研究内容なども国に忖度したものとなってしまうおそれがあります。
そのため、国による人事干渉は許されません。
2-2-2 施設・学生の管理の自治
施設・学生の管理の自治とは、大学施設内や学生の問題について、大学の自主的判断がある程度認められるという原則です。
なぜ「ある程度」かというと、大学の自治とは治外法権を認めるということではないからです。
例えば、大学内で殺人事件が発生した場合に、「大学の方で対応しますから、警察は立ち入らないでください」と言えるわけがありませんよね。
他方、捜査の名のもとで警察が無制限に大学に干渉できるとすると、学問の自由に対する事実上の圧力になってしまうおそれもあります。
そこで、どこまで大学側の自主的判断に委ね、どこまで国が干渉できるかは、ケースバイケースの判断になるということです。
|
■第2章のまとめ →大学内部の管理・運営を大学の自主的な決定に任せるという原則
・大学の自治の内容
|
第3章 学生の学問の自由について
ここからは少し応用的な論点になりますが、学生の学問の自由について解説します。
3-1 保障の有無
これまで、学問の自由とは教授などの研究者に認められる自由であると説明してきました。
それでは、大学で授業を受ける学生には、学問の自由は認められるのでしょうか。
結論から言うと、学生にも学問の自由は認められます。
東大ポポロ事件判決は、学生の学問の自由は「大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果」として保障されるとしています。
教授に授業をする権利があるとしても、学生に授業を受ける権利がなければ、学問の自由を保障した意味がありません。
そのため、学生が大学の施設を利用することも認める必要があります。
このように、学生の学問の自由は学問の自由と大学の自治の効果なので、学生が大学の施設でなんでも自由にできるということではありません。
昭和女子大事件判決(最判昭和49年7月19日)も、国公立か私立かを問わず、大学は学生を規律する包括的機能があると判断しています。
3-2 保障の範囲
また、学生の学問の自由には限界があります。
東大ポポロ事件判決は、「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない」と判示しました。
つまり、名目上は研究発表という形であったとしても、その内容が政治的な集会を目的としたものなどである場合、学問の自由としての保障の範囲外にあるということです。
誤解がないように補足すると、あくまで「学問の自由としての」保障がされないというだけなので、表現の自由や集会の自由として保障されることは別問題です。
|
■第3章のまとめ →学問の自由と大学の自治の効果として保障される ・学生の学問の自由の範囲 →実社会の政治的社会的活動に当たる行為は含まれない |
第4章 まとめ
以上のとおり、学問の自由とは、
- 学問研究の自由
- 学問発表の自由
- 教授の自由
の3つがあります。
明治憲法下の天皇機関説事件のような出来事もあり、学問の自由は重要な権利であると考えられています。
また、大学の自治としては
- 人事の自治
- 施設・学生の管理の自治
が認められますが、治外法権ではないことに注意しましょう。
そして、学生の学問の自由は、学問の自由と大学の自治の効果として保障されます。
ただし、実社会の政治的社会的活動に当たる行為は含まれません。
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
判例などの詳細な解説や、実践的な答案の書き方を知りたい方は、ヨビロン憲法のテキストをご購入いただけると幸いです。


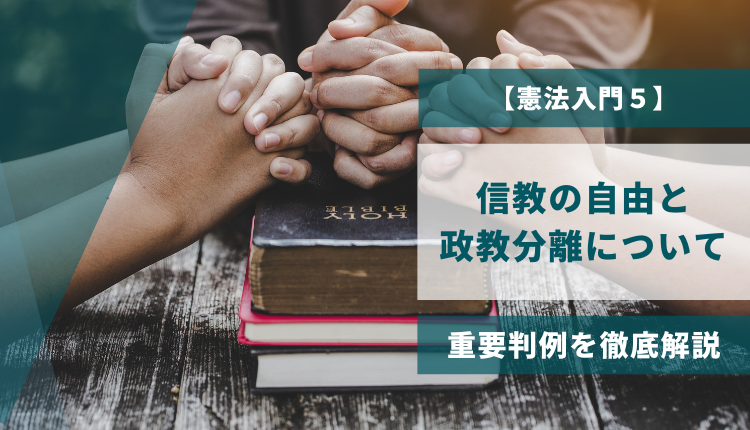
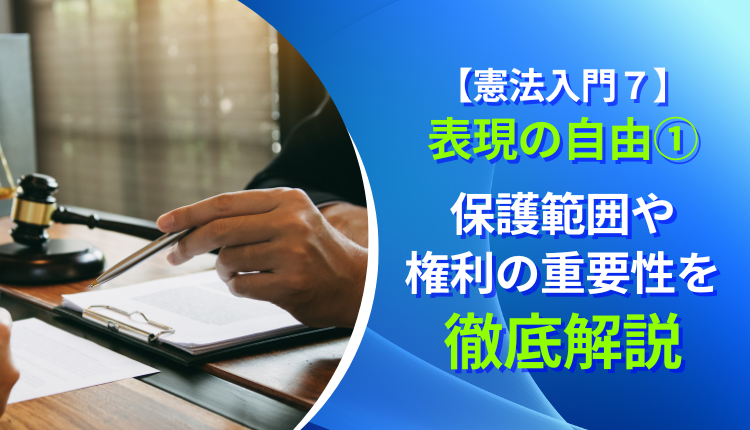
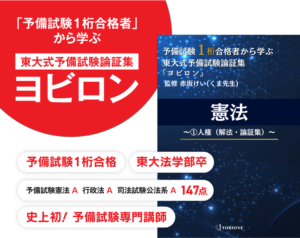



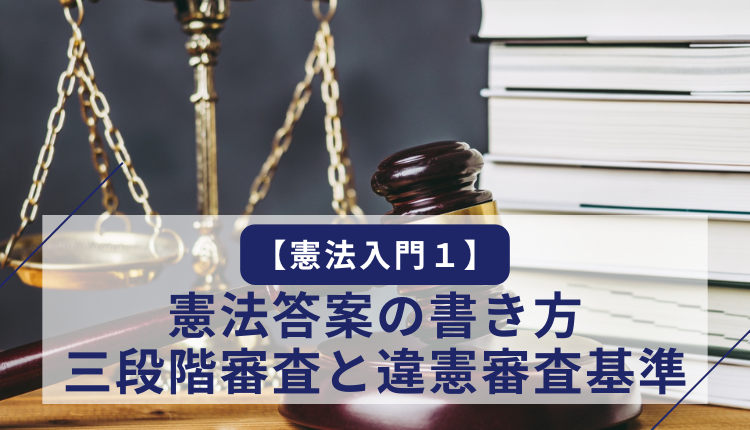
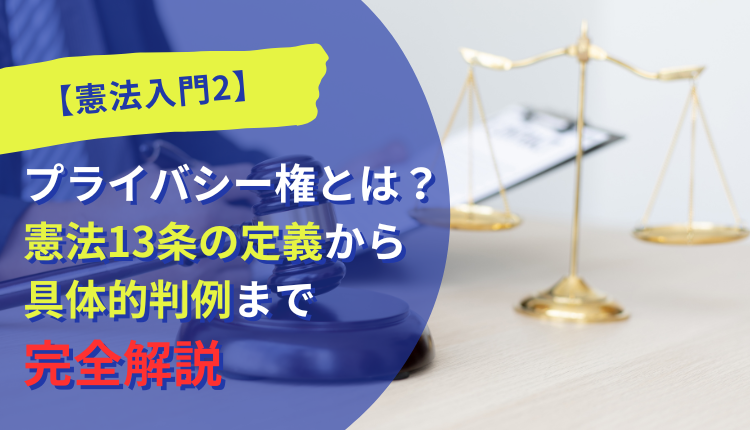
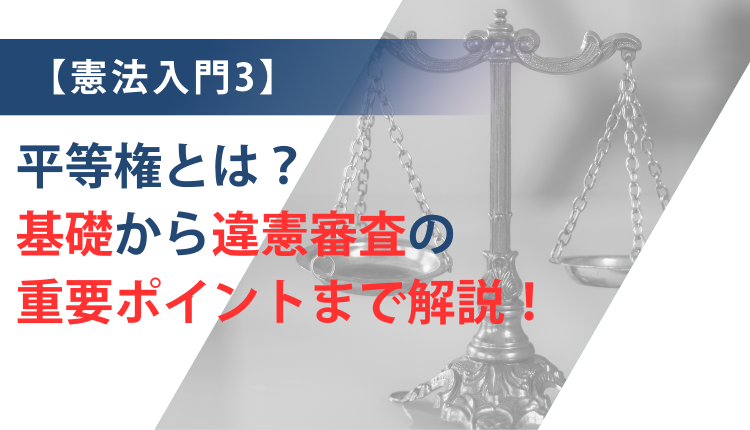
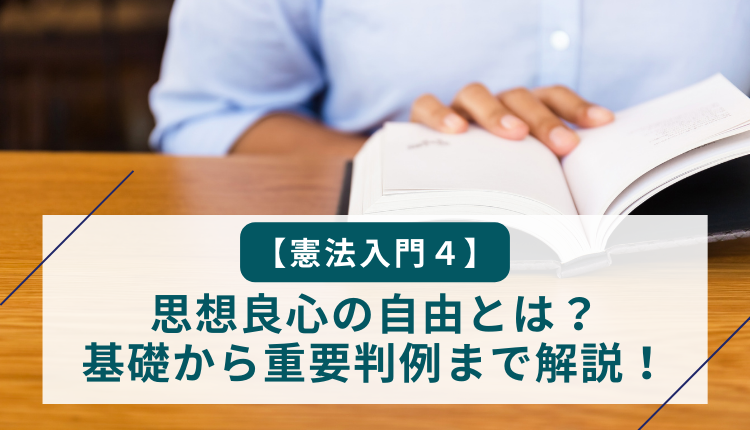
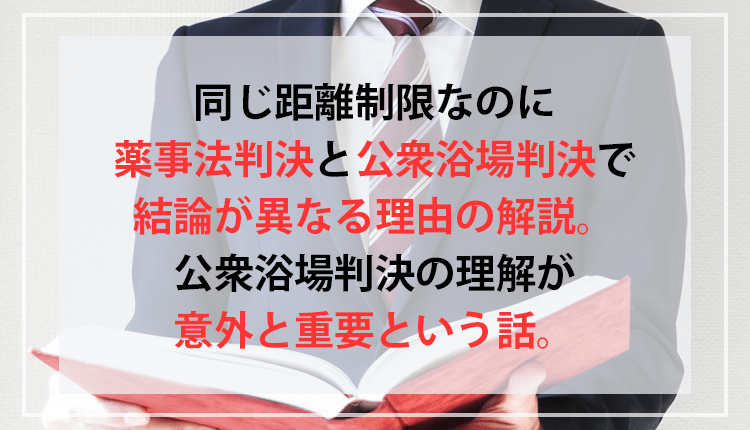
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。