【憲法入門8】表現の自由② 報道の自由から取材源の秘匿まで徹底解説
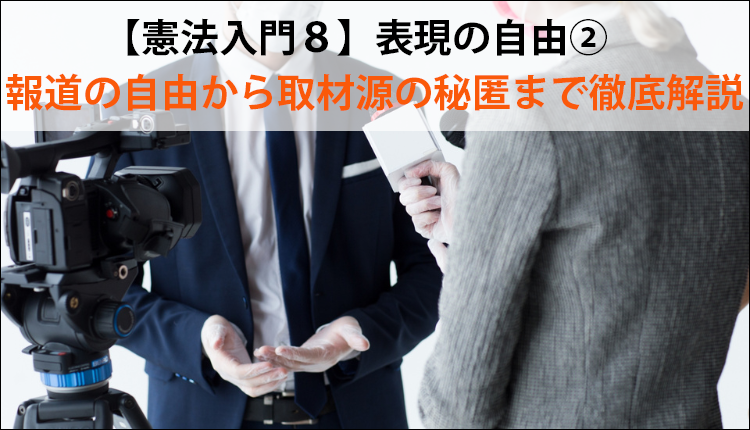
この記事を読んで理解できること
- 報道の自由
- 取材の自由
- 取材源の秘匿
この記事は、
- 報道の自由について知りたい
- 取材の自由について知りたい
- 取材源の秘匿について知りたい
といった方におすすめです。
報道の自由が表現の自由として保障されるということは、多くの方が知っていると思います。
では、
- なぜ報道の自由が保障されるのか
- どのような主体に保障されるのか
- 具体的にどのような行為が保障されるのか
といったことを説明できるでしょうか?
報道の自由は司法試験や予備試験でも問題になるため、基礎知識をしっかりと押さえておく必要があります。
そこで、この記事では、
第1章で報道の自由について、
第2章で取材の自由について、
第3章で取材源の秘匿について、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 報道の自由
この章では、報道の自由が表現の自由として保障される根拠などを解説します。
1-1 保障の有無
まずは憲法の条文を読んでみましょう。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2(略)
このように、21条1項に報道の自由は明記されていないため、「一切の表現の自由」に含まれるかという解釈の問題となります。
ここで、有名な最高裁判例を読んでみましょう。
- 博多駅事件(最決昭和44年11月26日)
「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。」
最高裁は、思想の表明の自由だけでなく、事実の報道の自由も憲法21条で保障されると判示しています。
その理由として、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供することが挙げられました。
前回の記事で解説したとおり、表現の自由には
- 自己実現
- 自己統治
- 思想の自由市場
という3つの価値があります。
最高裁は、自己統治の価値に着目して、事実の報道の自由も保障されるとしたのです。
1-2 保障される主体
もっとも、博多駅事件は、「報道機関の報道」という表現を用いています。
実は、この表現は博多駅事件だけでなく、他の最高裁判例においても共通しています。
つまり、最高裁が念頭においている報道の自由とは誰にでも直ちに認められるものではなく、「報道機関」の権利であることが前提なのです。
そのため、報道機関に所属していない個人ジャーナリストの場合、博多駅事件とは事案が異なるため、判例の射程が及ぶかを丁寧に検討する必要があります。
詳細はこちらの記事をご参照ください。
【令和5年予備憲法の解説・論証つき】既存予備校が間違える報道の自由の論証!予備試験頻出の博多駅事件と関連判例の射程を完璧に極めよう【外務省秘密電文漏洩事件・TBS事件・NHK事件】
第2章 取材の自由
この章では、取材の自由について解説します。
2-1 保障の有無
先ほど紹介した博多駅事件の続きを読んでみましょう。
- 博多駅事件(最決昭和44年11月26日)
「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。」
このように、最高裁は、報道のための取材の自由も十分尊重に値すると判断しています。
「尊重」という表現がやや抽象的ですが、学説上は、取材の自由も表現の自由の一環として保障されるという解釈が一般的です。
前回の記事でも説明したとおり、表現の自由は情報の流通過程が保護される権利です。
事実を報道する場合、
①取材をして正しい情報を集める
②集めた情報を編集して発信する
③情報が一般大衆に届く
という過程を経て初めて成り立ちます。
取材の自由が保障されないと①が達成できないので、報道の前提が失われてしまうのです。
ただし、ここでも「報道機関の報道」という表現が用いられているため、個人ジャーナリストにも保障されるかは別途問題になります。
2-2 手段の相当性
取材の自由が保障されるとして、具体的にどのような方法の取材であれば許されるのでしょうか。
この点についても有名な判例があります。
- 外務省秘密漏洩事件(最決昭和53年5月31日)
「報道機関の国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり、時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。」
まず、取材の自由の主体が「報道機関」とされている点は博多駅事件と同様です。
それにくわえて、取材の手段について、「手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認される」ものであることが必要とされています。
本件では、被告人が公務員の女性と強引に肉体関係を持ち、依頼を拒み難い心理状態になったのに乗じて秘密文書を持ち出させ、その女性を利用する必要がなくなると関係を消滅させたという行為について、「人格の尊厳を著しく蹂躪したもの」であるとして有罪となりました。
このように、取材の目的が正当であれば常に許されるのではなく、手段の相当性が必要とされるのです。
なお、外務省秘密漏洩事件は「公務員」に対する「国政に関する取材行為」についての事案なので、国家以外の機関(私企業など)からの情報の持ち出しについても判例の射程が及ぶかどうかの検討も必要になります。
第3章 取材源の秘匿
最後に、取材源の秘匿という論点について解説します。
3-1 根拠条文
例えば、報道機関がある企業の重大なスキャンダルについて、従業員から情報を得て報道したとします。
その企業が、報道機関に情報を流したと思われる従業員を訴えた場合、取材にあたった記者が証人として尋問を受ける可能性があります。
このときに、記者は取材源が誰であるかについて、証言を拒絶することができるでしょうか?
民事訴訟法197条1項3号を読んでみましょう。
第百九十七条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一(略)
二(略)
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2(略)
このように、民事訴訟法は、「職業の秘密」についての証言拒絶権を認めています。
そして、いかなる事項であれば「職業の秘密」に該当するのかについては、報道の自由や取材の自由といった憲法上の権利に鑑みて解釈する必要があるのです。
3-2 判断基準
ここでも有名な最高裁判例があるので紹介します。
- NHK記者証言拒絶事件(最決平成18年10月3日)
「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有するというべきである。そうすると、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である。」
このように、最高裁は、「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要」と考えています。
なぜ取材源を秘匿しないと取材の自由が確保できないのかピンとこない人もいるかもしれません。
例えば、みなさんが報道機関から取材を受けて、「取材源は明かさない」という条件で重大な秘密を話したとしましょう。
その後、報道機関の記者が「裁判所から呼ばれたので」ということで、あなたが取材源であると明かしてしまったらどうでしょうか?
もう二度とその報道機関の取材には協力しないと思いませんか?
つまり、取材源を秘密にするということは、取材の協力を得るために不可欠な前提であり、これが守られないと十分な取材ができず、ひいては報道の自由が脅かされてしまうのです。
ここでも、情報の流通過程が保護されるかという観点が重要になります。
その上で、最高裁は、
- 報道が公共の利益に関するものである
- 取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れない
- 取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾していない
- 取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない
という場合には、原則として取材源の証言拒絶を認めています。
取材源を秘匿することの価値と、証言の価値を比較衡量するということです。
第4章 まとめ
第一に、博多駅事件は思想の表明の自由だけでなく、事実の報道の自由も憲法21条で保障されると判示しています。
ただし、「報道機関の報道」という表現が用いられていることから、個人ジャーナリストにまで判例の射程が及ぶかどうかが問題となります。
第二に、博多駅事件は報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値すると判示しています。
ただし、外務省秘密漏洩事件は、取材の手段・方法が相当なものであることを必要として、「人格の尊厳を著しく蹂躪したもの」については違法と判断しました。
第三に、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」として取材源を秘匿できるかどうかについて、NHK記者証言拒絶事件は取材源の秘密の重要な社会的価値を認めた上で、取材源を秘匿することの価値と証言の価値を比較衡量する基準を採用しています。
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
判例などの詳細な解説や、実践的な答案の書き方を知りたい方は、ヨビロン憲法のテキストをご購入いただけると幸いです。


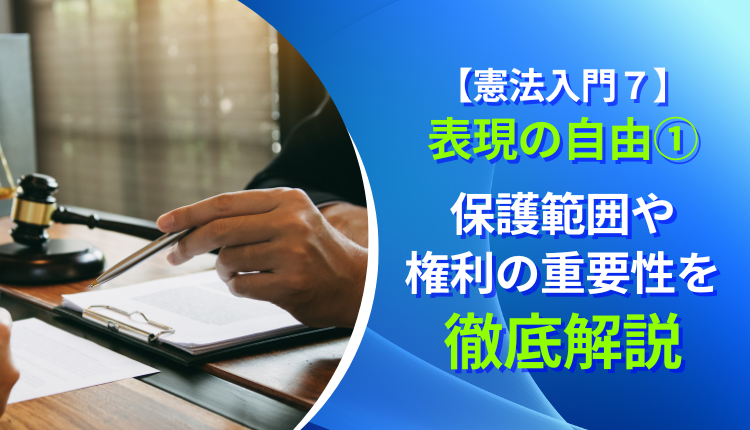
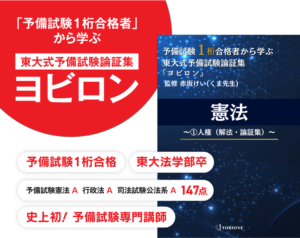



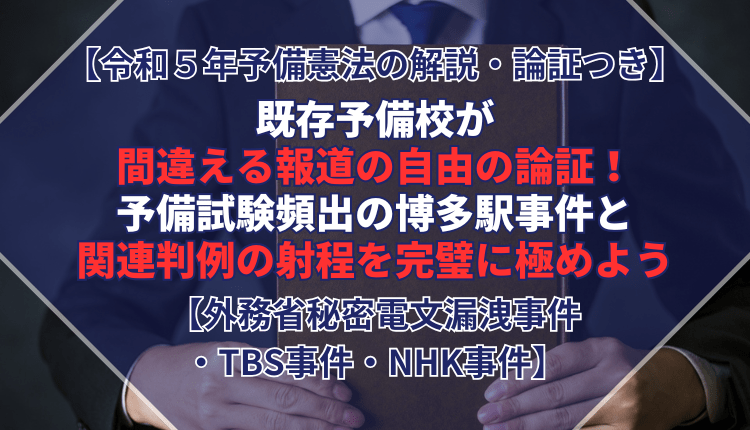

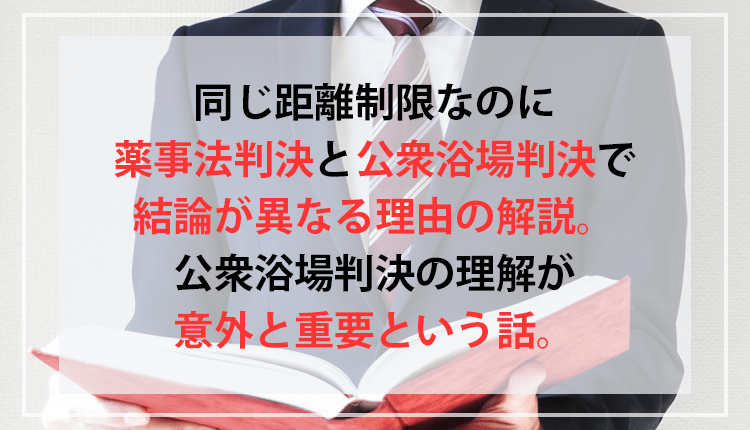
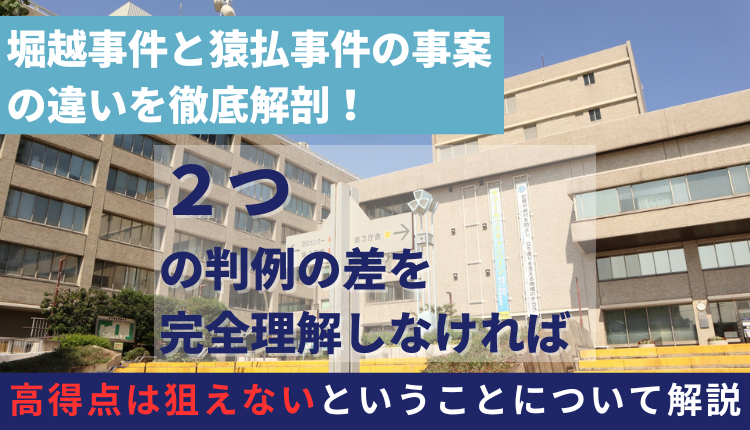


コメント