【憲法入門9】表現の自由③ 低価値表現について徹底解説!
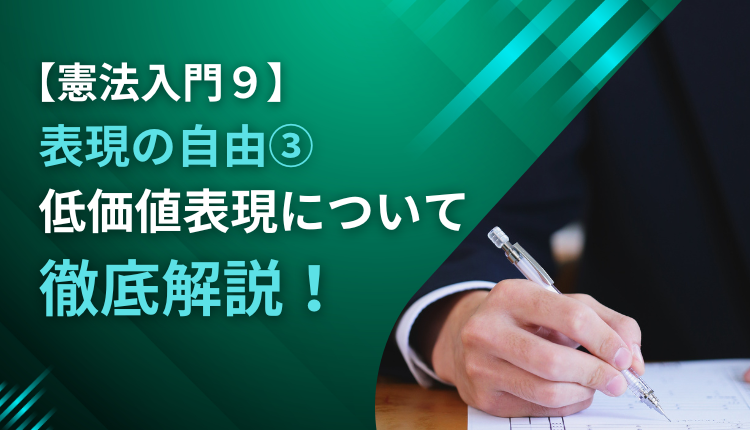
この記事を読んで理解できること
- 低価値表現とは何か
- 犯罪の扇動
- 性表現
- 営利的表現
この記事は、
- 低価値表現とは何かを知りたい
- 低価値表現の具体的な種類を知りたい
- 低価値表現に関する判例を知りたい
といった方におすすめです。
これまでの記事で解説したとおり、表現の自由は憲法上非常に強く保護されています。
しかし、いかなる表現行為も無条件で許されるのではなく、中には保障されない表現や、保障の程度が低い表現も存在するのです。
今回の記事では、そのような低価値表現について解説していきます。
具体的には、
第1章で低価値表現とは何かについて、
第2章で犯罪の扇動について、
第3章で性表現について、
第4章で営利的表現について、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 低価値表現とは何か
低価値表現とは、表現内容が社会的な害悪を有しているなどの理由から、表現の自由として保障されなかったり、保障の程度が低くなったりするものをいいます。
「害悪のある表現が保障されないって普通のことじゃない?」と思った方もいるかもしれません。
しかし、表現の自由に関しては、内容に着目した規制が許されるのは極めて例外的なのです。
以前の記事で、表現の自由には思想の自由市場という概念があることをお話ししました。
【憲法入門7】表現の自由① 保護範囲や権利の重要性を徹底解説
公権力が「この表現は内容がおかしい」と言って規制すると思想の自由市場が歪められ、民主制が機能不全となってしまいます。
そのため、表現内容に着目した規制は許されないのが原則です。
また、いくら憲法が表現の自由を保障していても、公権力が「価値のない内容だったら保障しないよ」と言ってきたら、怖くて自由な表現なんてできなくなりますよね。
このように、表現内容に着目した規制は萎縮効果を生じさせてしまうおそれもあるのです。
そのため、低価値表現を問題とする場合、
- 本当に規制しなければならないほどの害悪があるのか
- 規制範囲が不明確で萎縮効果が生じないか
といった点に注意する必要があります。
第2章 犯罪の扇動
この章からは、低価値表現といわれる表現の具体的な種類を説明します。
一つ目は犯罪の扇動です。
簡単に言えば、犯罪をそそのかす表現を処罰するということです。
誤解がないように補足すると、犯罪の扇動と刑法の教唆犯(61条)は全く違います。
犯罪を教唆して実現させた場合に、「教唆は人とのコミュニケーションだから表現の自由だ!」という主張が通用しないことに異論はないでしょう。
これに対し、犯罪の扇動は、犯罪をそそのかした時点で、実際に犯罪が実現される前に扇動者が処罰されるという特徴があります。
条文を読んでみましょう。
破壊活動防止法
(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
第四十条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。
一 刑法第百六条の罪
二 刑法第百二十五条の罪
三 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪
このように、扇動された者が実際に犯罪行為をしなくても、扇動行為をした時点で処罰されます。
渋谷暴動事件(最判平成2年9月28日)では、破壊活動防止法が表現の自由を侵害し違憲であるとの主張がなされましたが、最高裁は扇動行為について、「重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しない」と判断しました。
犯罪の扇動は表現の自由としての価値が下がるだけにとどまらず、そもそも保障されないということです。
第3章 性表現
この章では、性表現の規制について解説します。
初めに押さえていただきたいことは、性表現には
- わいせつ表現
- 有害図書
- 児童ポルノ
があり、規制の範囲や趣旨が異なるということです。
3-1 わいせつ表現
まずはわいせつ表現から説明します。
刑法の条文を読んでみましょう。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2(略)
刑法175条1項の「わいせつ」とは何かが、これまで繰り返し争われてきました。
最高裁は、「わいせつ」を以下のとおり定義しています。
- チャタレイ事件(最判昭和32年3月13日)
「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」
しかし、これだけでは具体的にどのような表現がわいせつであるかわかりませんよね。
その後、最高裁は以下の判断基準を示しました。
- 「悪徳の栄え」事件(最判昭和44年10月15日)
「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。」
「文書の個々の章句の部分は、全体としての文書の一部として意味をもつものであるから、その章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならないものである。したがつて、特定の章句の部分を取り出し、全体から切り離して、その部分だけについて猥褻性の有無を判断するのは相当でないが、特定の章句の部分について猥褻性の有無が判断されている場合でも、その判断が文書全体との関連においてなされている以上、これを不当とする理由は存在しない。」
このように、最高裁は、文書の芸術性や思想性が性的刺激を減少・緩和させる可能性あることを認めた上で、わいせつかどうかは一部だけを取り出すのではなく全体を見て判断すべきであるとしました。
さらに、最高裁は、以下のとおり具体的な考慮要素を示すようになりました。
- 「四畳半襖の下張」事件(最判昭和55年11月28日)
「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」…といえるか否かを決すべきである。」
以上のように、最高裁は徐々に判断基準を具体化し、妥当な結論を導く努力をしていることがわかります。
他方、様々な事情を考慮するとケースバイケースの判断になるので、萎縮効果が生じるおそれは否定できません。
そこで、最高裁とは異なる立場として、いわゆるハードコアポルノのみを規制すべきだという見解もあります。
このように、個別具体的な事情を検討するのではなく、あらかじめ憲法で保障されない範囲を明確に定める考え方を「定義付け衡量」といいます。
3-2 有害図書
次に、有害図書について説明します。
東京都青少年育成条例の条文を読んでみましょう。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二~四(略)
2(略)
「著しく性的感情を刺激し」とあるので、わいせつ表現のことかと思われるかもしれませんが、違います。
これは、わいせつ表現ほど性的ではないものの、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるような表現物を規制するということです。
有害図書規制の詳細は、こちらの記事をご参照ください。
【未成年の知る自由】岐阜県青少年保護育成条例事件ベースの問題は未成年と成年両方検討せよ【パターナリズム】
ひとまずここでは、「わいせつ」と「有害図書」は違うということ、「著しく性的感情を刺激し」は一般的に有害図書を意味することを頭に入れていただければ大丈夫です。
3-3 児童ポルノ
3つ目に、児童ポルノについて解説します。
児童ポルノ規制法の条文を読んでみましょう。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2(略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
性交又は性交類似行為(2条3項1号)であれば「わいせつ」にも該当する可能性がありますが、衣服の一部を着けない場合(3号)も処罰されるので、例えば水着姿なども該当するケースがあります。
これは、児童ポルノ規制法の趣旨が、「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性」(1条)に鑑みたものであるからです。
児童は判断能力が未熟なので、本人の十分な意思に基づいているとは限りませんし、写真や動画に収められることによる将来への影響も自覚していない可能性があります。
児童ポルノ規制法は、児童を性的搾取から守るという目的があるため、「わいせつ」よりも該当範囲が広くなっているのです。
ただし、児童本人を守るための法律なので、実在しない児童を描写したものは含まれません(最判令和2年1月27日)。
第4章 営利的表現
最後に、営利的表現について解説します。
4-1 営利的表現とは何か
営利的表現とは、簡単に言えば商品やサービスの広告のことです。
絶対に間違えないでいただきたいのですが、
お金もうけのための表現=営利的表現
ではありません。
仮にそうだとすると、有料で出版している書籍などは全て営利的表現ということになってしまいます。
営利的表現は広告だけであることを理解しましょう。
4-2 営利的表現の規制
一般的に、営利的表現は違憲審査基準が下がる(厳格に審査しなくてよい)と考えられています。
理由については様々な説明がありますが、第1章で説明した、なぜ表現内容の規制は許されないのかということに照らして考えるとわかりやすいです。
第一に、公権力が「この表現は内容がおかしい」と言って規制すると、思想の自由市場が歪められるおそれがあります。
しかし、営利広告の場合、宣伝文句が真実か虚偽かは客観的に判断することが可能なので、公権力が恣意的な制約をするおそれは低いといえます。
第二に、表現内容に着目した規制は萎縮効果を生じさせるおそれがあります。
しかし、営利的表現は経済的利益を得ることが直接の目的なので、利潤獲得という強い動機があり、萎縮効果は少ないといえます。
そのため、通常の表現の規制と比較して、審査基準は緩やかになると考えられています。
第5章 まとめ
低価値表現とは、表現内容が社会的な害悪を有しているなどの理由から、表現の自由として保障されなかったり、保障の程度が低くなったりするものをいいます。
ただし、表現内容に着目した規制は萎縮効果を生じさせるおそれがあるので、本当に規制が必要であるかを慎重に判断する必要があります。
低価値表現の例として、第一に犯罪の扇動があります。
これは刑法の教唆犯とは異なり、犯罪をそそのかした時点で処罰されることが特徴です。
第二に性表現が挙げられますが、
- わいせつ表現
- 有害図書
- 児童ポルノ
があり、規制の範囲や趣旨が異なることに注意しましょう。
第三に営利的表現があります。
お金もうけのための表現が全て含まれるのではなく、商品やサービスの広告だけです。
審査基準が下がる理由については、なぜ表現内容の規制は許されないのかということに照らして考えましょう。
その他、名誉毀損やプライバシー侵害も低価値表現の一種ですが、これらは次回の記事で解説する予定です。
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
判例などの詳細な解説や、実践的な答案の書き方を知りたい方は、ヨビロン憲法のテキストをご購入いただけると幸いです。


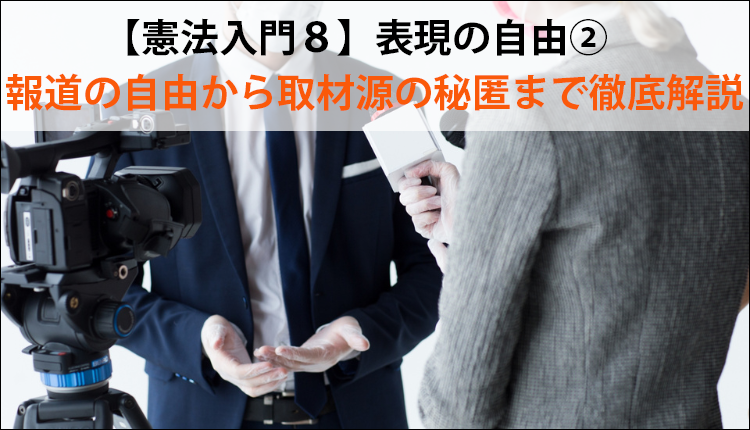
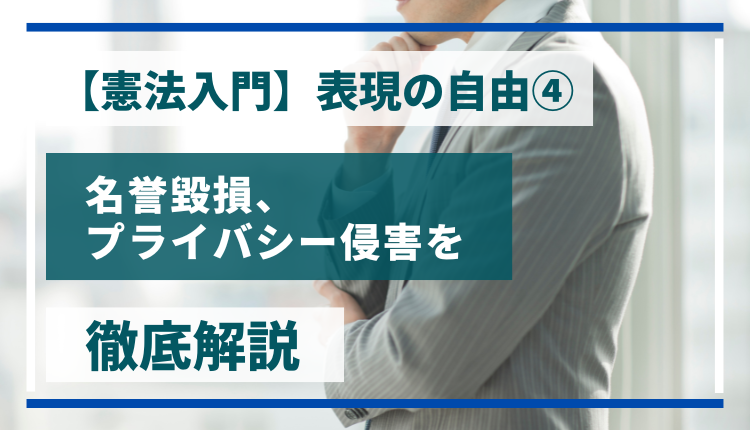
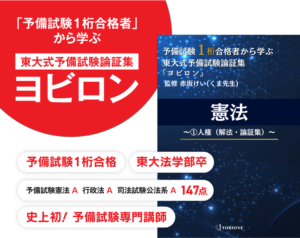



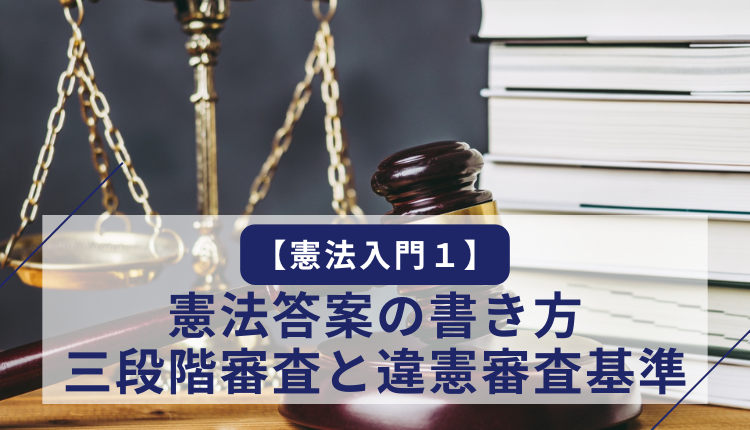
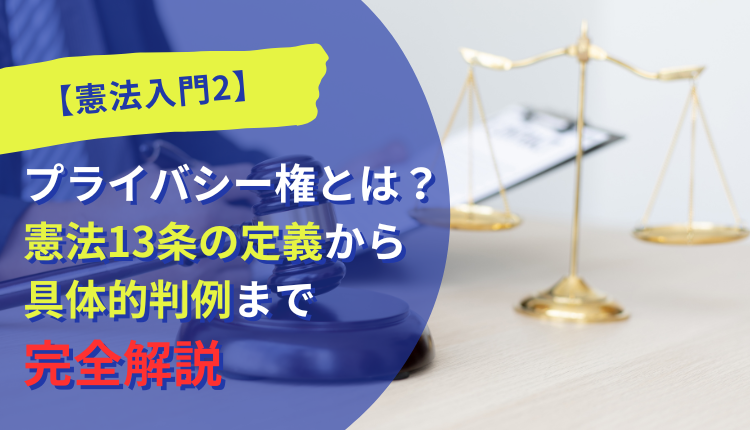
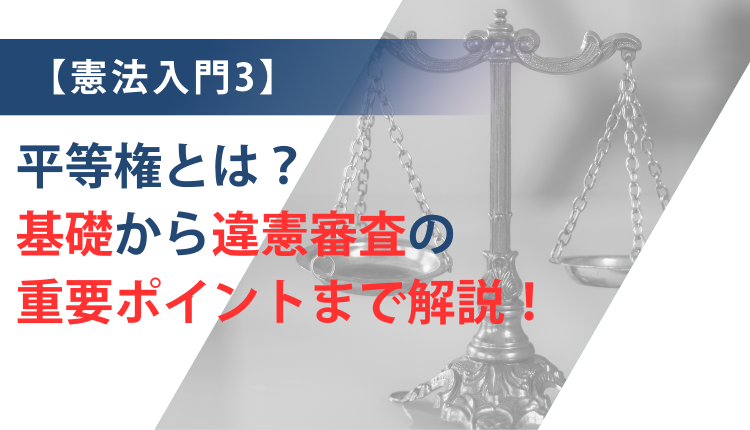
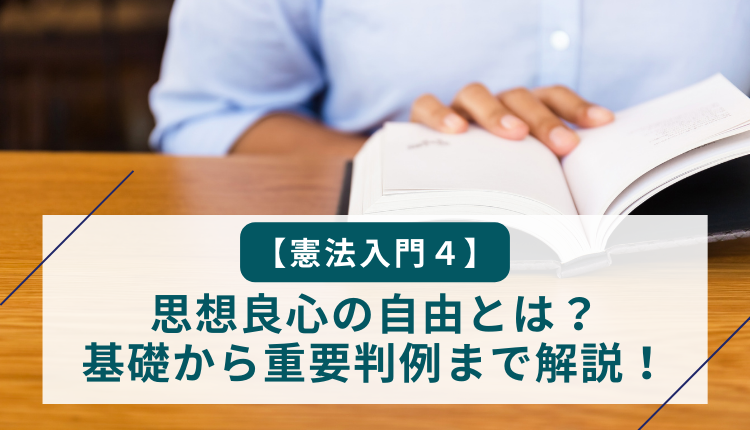
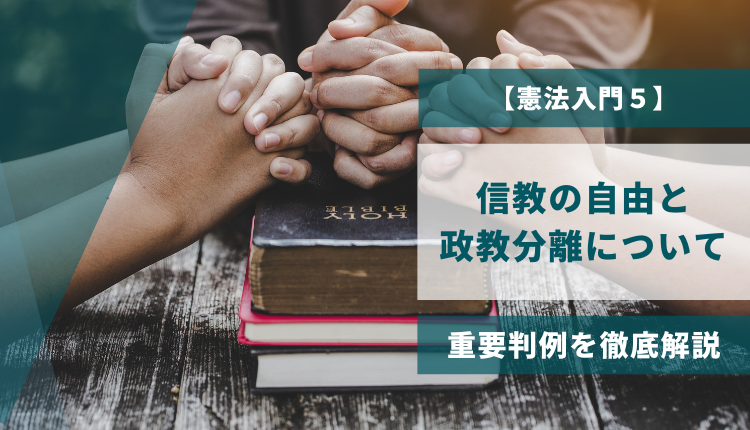
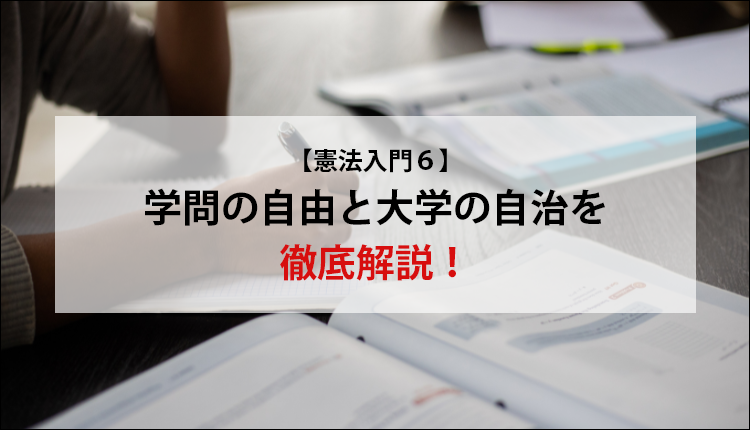
コメント