【憲法入門7】表現の自由① 保護範囲や権利の重要性を徹底解説
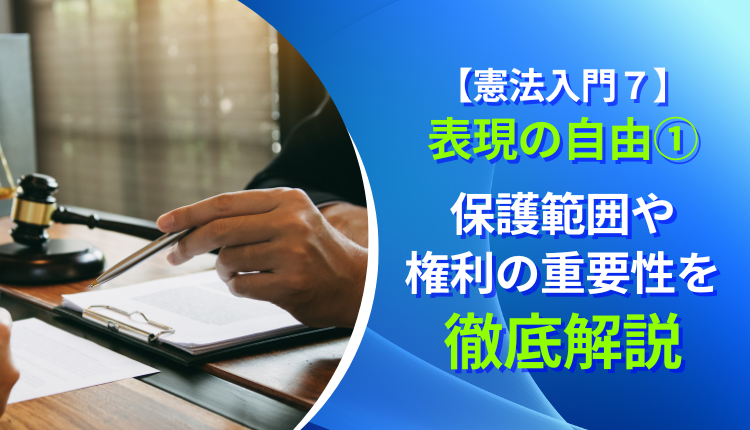
目次
この記事を読んで理解できること
- 表現の自由とは何か
- 表現の自由が重要な理由
- 知る権利
- アクセス権
この記事は、
- 表現の自由とは何かを知りたい
- 表現の自由が重要とされる理由を知りたい
- 表現の自由は何が保障されるのかを知りたい
といった方におすすめです。
表現の自由は、精神的自由権の中でも特に重要な権利です。
司法試験でも予備試験でも頻出で、論点も多くあります。
そこで今回からは、表現の自由について、複数回に分けて丁寧に説明する予定です。
この記事では、
第1章で表現の自由とは何かについて、
第2章で表現の自由が重要な理由について、
第3章で知る権利について、
第4章でアクセス権について、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 表現の自由とは何か
この章では、そもそも表現の自由とは何かについて解説します。
まずは憲法の条文を読んでみましょう。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2(略)
このように、憲法は「一切の表現の自由」を保障しています。
表現の自由とは、思想、情報を発表し伝達する自由のことです。
自分の意見や情報を他者に伝えることを、国家が「その意見は間違っている」と言って禁止することは許されません。
ここでのポイントは、表現の自由は他者に伝達されなければ意味がないということです。
例えば、無人島に連れていかれて「ここでなら好きなことを喋っていいよ」と言われたところで、その表現は誰にも伝わることがないので意味を持ちません。
そのため、表現の自由とは、思想や情報を発信することだけでなく、発信から受領までの情報流通過程を保護していると解釈されています。
第2章 表現の自由が重要な理由
では、なぜ表現の自由は重要な権利であると言われているのでしょうか。
その理由は、大きく分けると
- 自己実現
- 自己統治
- 思想の自由市場
の3つであると考えられています。
2-1 自己実現
自己実現とは、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させることです。
簡単に言えば、他者とのコミュニケーションを通して人として成長していくということですね。
これは、表現の自由の個人的な価値という位置づけになります。
2-2 自己統治
自己統治とは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するということです。
民主制は、国民一人一人が自由に発言できることが大前提であり、表現の自由と民主主義は密接な関係があります。
これは、表現の自由の社会的な価値という位置づけになります。
2-3 思想の自由市場
思想の自由市場とは、自由な言論活動を行わせることで、民主的決定に真理が残るという考え方です。
例えば、経済活動の場合、市場において各人が好きなものを選ぶことで需要と供給が生まれ、良い商品やサービスが残ることになりますよね。
言論活動もこれと同じで、各人が自由な意見を持ち、それが流通することで議論が発展し、真理に近づくことができるという考え方です。
逆に、公権力が都合の悪い思想を流通させなかったり、特定の思想が流通するよう操作したりすると、思想の自由市場が歪められ、民主制が機能不全となってしまいます。
第3章 知る権利
この章では、情報を発信する権利ではなく、情報を受け取る権利、すなわち知る権利について解説します。
具体的には、
- 情報を受領する自由
- 情報公開請求権
の2つがあります。
3-1 情報を受領する自由
情報を受領する自由とは、個人が情報を受け取ることを公権力に妨げられないという消極的自由です。
第1章でも説明したとおり、表現の自由は他者に伝達されなければ意味がありません。
無人島で好きなように発言していいと言われても、表現の自由が保障されたことにはならないのです。
そこで、情報を発信する側の自由だけでなく、受領する側の自由も保障する必要があります。
このように、情報を受領する自由は、表現の自由の派生原理として保障されるものです。
有名な判例としては、よど号ハイジャック記事抹消事件(最判昭和58年6月22日)があります。
少し長いですが、判旨を読んでみましょう。
「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる」
難しい言い回しですが、実はこれまでに解説した概念から説明できます。
|
・個人として自己の思想及び人格を形成・発展 →自己実現
・民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保 →自己統治、思想の自由市場
・意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由 →情報を受領する自由 |
このように、判例は、
- 自己実現
- 自己統治
- 思想の自由市場
という表現の自由の重要性から、情報を受領する自由を表現の自由の派生原理として認めているのです。
なお、情報を受領する自由は未成年者にも認められますが、成人と異なり思慮分別能力が未熟であることから、有害図書規制などの制約が存在します。
判例としては、岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平成元年9月19日)が有名です。
詳細は以下の記事をご参照ください。
【未成年の知る自由】岐阜県青少年保護育成条例事件ベースの問題は未成年と成年両方検討せよ【パターナリズム】
3-2 情報公開請求権
情報公開請求権とは、公権力が保有する情報の公開・提供を求めるという積極的権利です。
民主制において国民が正しい判断をするためには、さまざまな情報を知る必要があります。
そこで、個人が情報を取得することを妨げられないだけでなく、公権力に対して積極的に情報の公開を求めることも、知る権利に含まれていると解釈されています。
しかし、具体的にどのような情報が公開の対象となり、そのためにどのような手続が必要になるのかは、憲法21条から直ちに導くことはできません。
そのため、情報公開法などの法制度の形成が必要となります。
第4章 アクセス権
この章では、アクセス権という概念について解説します。
4-1 アクセス権とは何か
アクセス権とは、マスメディアに対し、自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利です。
例えば、ある新聞で個人が批判される内容の記事が掲載されたとします。
当然その個人としては反論したいわけですが、一個人の影響力では新聞のように広く意見を発信することはなかなか難しいですよね。
繰り返しになりますが、表現の自由は情報が他者に伝達されなければ意味がありません。
そこで、新聞などのマスメディアに、自分の意見を載せてほしいと要求する権利がアクセス権ということです。
4-2 判例の考え方
結論として、判例はアクセス権を否定しています。
サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)の判旨を読んでみましょう。
「新聞の記事に取り上げられた者が、その記事の掲載によつて名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、自己が記事に取り上げられたというだけの理由によつて、新聞を発行・販売する者に対し、当該記事に対する自己の反論文を無修正で、しかも無料で掲載することを求めることができるものとするいわゆる反論権の制度は、記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライバシーに属する事項等について誤つた報道をされたとする者にとつては、機を失せず、同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ、これによつて原記事に対する自己の主張を読者に訴える途が開かれることになるのであつて、かかる制度により名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることも否定し難いところである。しかしながら、この制度が認められるときは、新聞を発行・販売する者にとつては、原記事が正しく、反論文は誤りであると確信している場合でも、あるいは反論文の内容がその編集方針によれば掲載すべきでないものであつても、その掲載を強制されることになり、また、そのために本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるのであつて、これらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゆうちよさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するのである。このように、反論権の制度は、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由…に対し重大な影響を及ぼすものであつて、たとえ被上告人の発行するサンケイ新聞などの日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力をもち、その記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい上告人主張のような反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないものといわなければならない」
このように、判例は、アクセス権(反論権)が「名誉あるいはプライバシーの保護に資する」ということは認めつつ、
- 反論文が誤りだと確信していても掲載が強制される
- 他に利用できたはずの紙面を割くことになる
という負担から、公的事項に関する批判的記事の掲載を躊躇させる危険があると指摘しました。
つまり、新聞を発行する側の表現の自由に配慮して、アクセス権を否定したのです。
第5章 まとめ
表現の自由は、思想、情報を発表し伝達する自由のことであり、発信から受領までの情報流通過程を保護しています。
表現の自由が重要な理由としては、
- 自己実現
- 自己統治
- 思想の自由市場
の3つが挙げられます。
また、表現の自由は情報を発信する権利ではなく、情報を受け取る権利、すなわち知る権利も含まれ、
- 情報を受領する自由
- 情報公開請求権
の2つがに分けられます。
マスメディアに対し、自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利としてアクセス権という概念もありますが、判例は新聞を発行する側の表現の自由に配慮して、アクセス権を否定しています。
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
判例などの詳細な解説や、実践的な答案の書き方を知りたい方は、ヨビロン憲法のテキストをご購入いただけると幸いです。


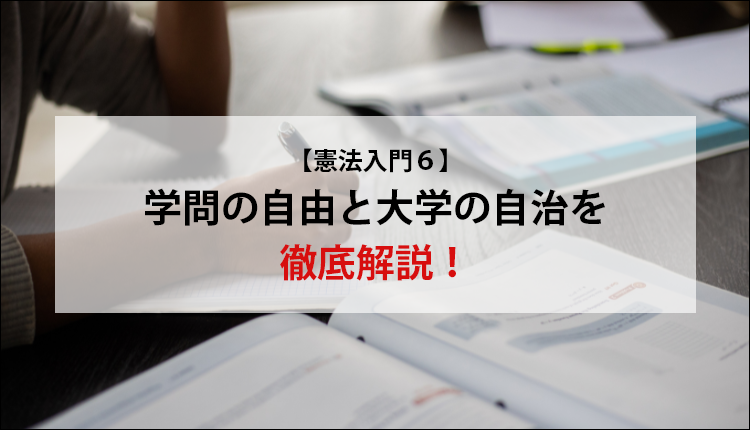
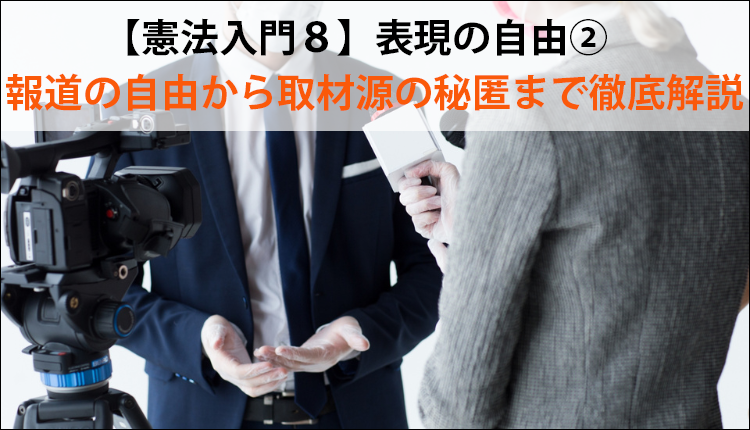
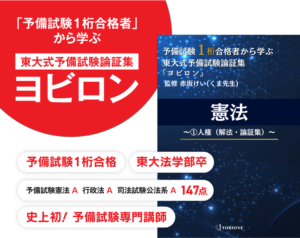



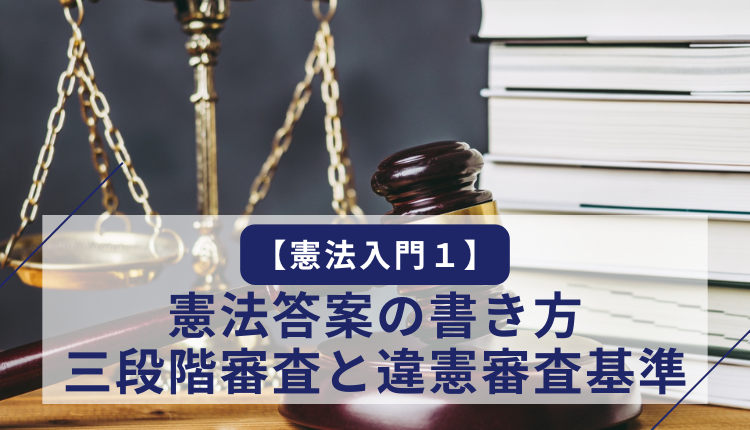
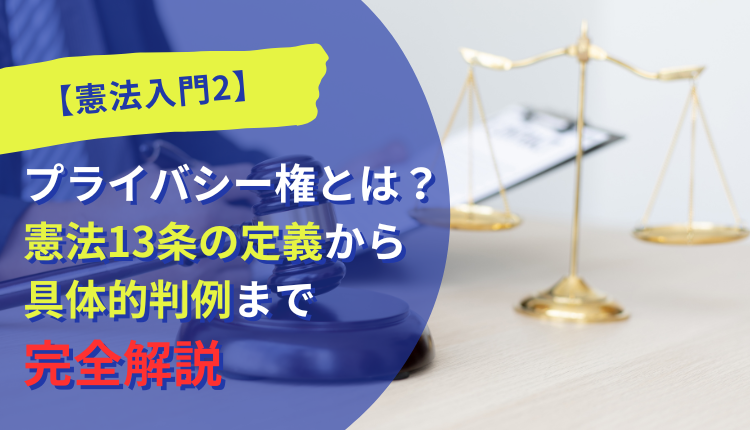
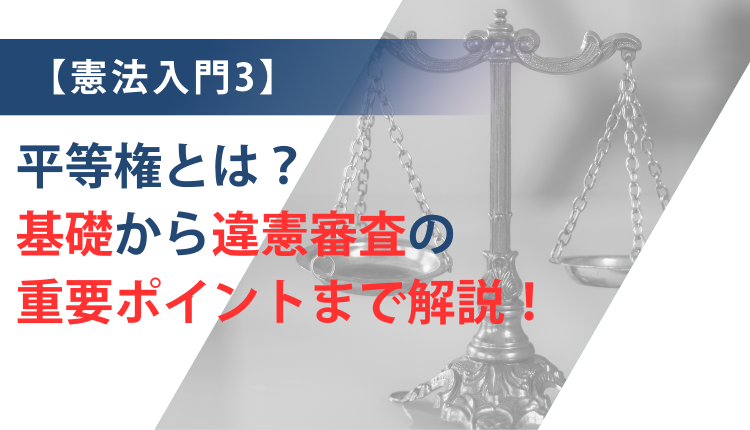
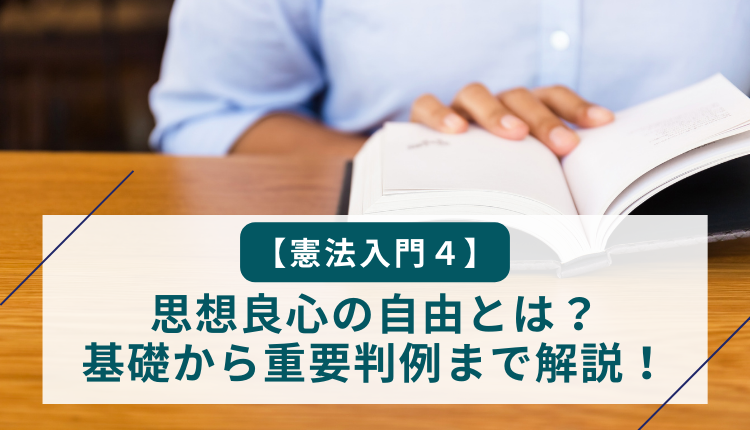
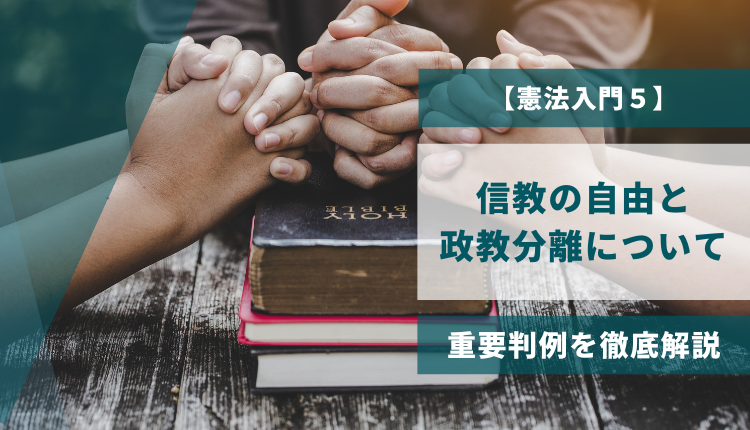
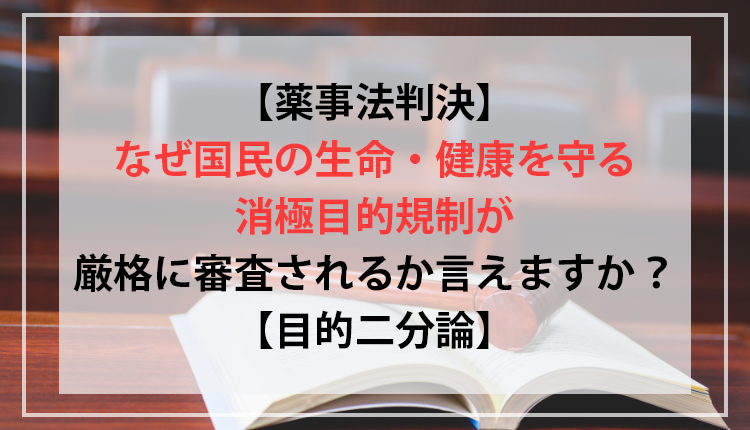
コメント