【憲法入門】表現の自由④ 名誉毀損・プライバシー侵害・ヘイトスピーチを徹底解説
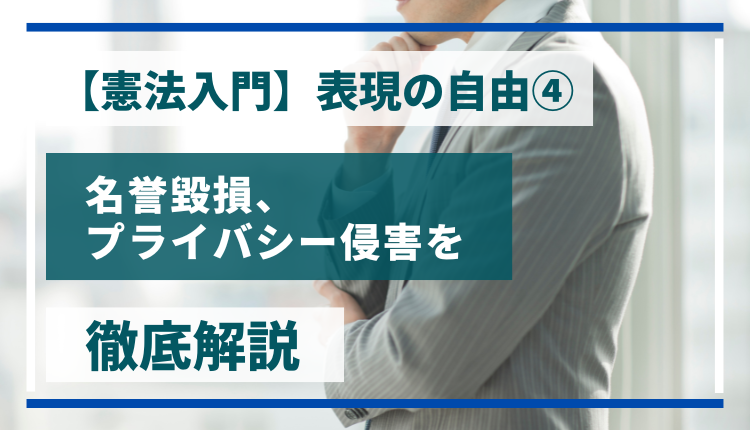
目次
この記事を読んで理解できること
- 名誉毀損
- プライバシー侵害
- ヘイトスピーチ
この記事は、
- 表現の自由と名誉毀損について知りたい
- 表現の自由とプライバシー侵害について知りたい
- 表現の自由とヘイトスピーチについて知りたい
といった方におすすめです。
前回の記事では、低価値表現について解説しました。
今回解説する名誉毀損やプライバシー侵害も、低価値表現の一種と考えられています。
特に名誉毀損は要件が複雑ですが、一つ一つ丁寧に説明するのでご安心ください。
この記事では、
第1章で名誉毀損について、
第2章でプライバシー侵害について、
第3章でヘイトスピーチについて、
それぞれ解説します。
基礎知識をわかりやすく簡潔に説明しますので、初学者の方はもちろん、憲法をひと通り学んだ方のまとめ用にも最適です。
第1章 名誉毀損
この章では、表現行為と名誉毀損との関係について解説します。
1-1 名誉棄損罪と「公共の利害」
まずは条文を読んでみましょう。
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2(略)
このように、人の名誉を毀損する行為は刑事罰の対象となります。
北方ジャーナル事件(最判昭和61年6月11日)も、「他人の名誉を害する表現は表現の自由の濫用であつて、これを規制することを妨げない」と判示しています。
ただし、これには例外があります。
刑法
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2(略)
上記のとおり、
- 「公共の利害に関する事実」であること
- 「その目的が専ら公益を図ることにあった」こと
- 「真実であることの証明があった」こと
の3要件を満たした場合、名誉棄損罪は成立しないのです。
日ごろ、マスメディアや週刊誌が容疑者の逮捕や有名人のスキャンダルについて報道していますが、これらの報道は刑法230条の2により名誉棄損罪には当たらないことになります。
なお、「公共の利害に関する」という言葉からは、犯罪や政治家の不祥事などが思い浮かびやすいですが、私人に関することであっても該当する可能性があります。
- 月刊ペン事件(昭和56年4月16日)
「私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があると解すべきである。」
例えば、一般人が不倫をしたことを世間に公表されたら名誉毀損となる可能性が高いですが、社会的な影響力を有する人の場合は「公共の利害に関する事実」に該当し得るということです。
1-2 真実性の誤信(相当性の法理)
先ほど説明したように、名誉棄損罪の例外に当たるためには、③「真実であることの証明があった」ことが必要となります。
では、公共の利害に関する事実を報道したにもかかわらず、後でそれが事実ではないと発覚した場合、名誉棄損罪が成立してしまうのでしょうか?
実は、この点については「例外の例外」が存在します。
- 夕刊和歌山時事事件(最判昭和44年6月25日)
「刑法二三〇ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」
このように、真実性の証明ができなかった場合も、
- 「その事実を真実であると誤信」したこと
- 「確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」こと
の2要件を満たせば、犯罪の故意がないとして名誉棄損罪は成立しないのです。
通常であれば、故意は行為者の内心の問題なので、①の誤信さえあれば故意がないともいえそうです。
しかし、きちんとファクトチェックもしないまま真実だと思いこんだとしても、「例外の例外」を認めてあげる必要はありません。
行為者が真実だと思うだけでなく、客観的な調査も必要なのです。
「相当の理由がある」ことが要件とされることから、この考え方は「相当性の法理」と呼ばれています。
1-3 公正な論評の法理
刑法230条1項は「事実を摘示」することが要件となるので、具体的な事実を示さない批判について名誉棄損罪は成立しません。
他方、民事裁判で不法行為に基づく請求をする場合には、事実を摘示しない批判も名誉毀損に含まれます。
では、批判的な意見を発表した場合は必ず慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
それでは自由な表現活動を行うことはできないですよね。
この点について、最高裁判例を読んでみましょう。
- 「脱ゴーマニズム宣言」事件(最判平成16年7月15日)
「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は過失は否定される」
少しややこしいですが、整理すると以下のとおりです。
|
ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明である ↓ 【違法性が否定される場合】 ①公共の利害に関する事実に係る ②目的が専ら公益を図ることにある ③人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない ④前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった
【故意又は過失が否定される場合】 ①~③は同上 ④前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明がない ⑤重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由がある |
このような考え方は「公正な論評の法理」と呼ばれています。
第2章 プライバシー侵害
この章では、表現行為とプライバシー侵害との関係について解説します。
2-1 伝統的見解
伝統的な見解としては、表現行為によるプライバシー侵害は、以下の3要件を満たした場合に法的救済が与えられると考えられてきました。
- 「宴のあと」事件(東京地判昭和39年9月28日)
「プライバシーの侵害に対し法的な救済が与えられるためには、公開された内容が(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とする」
伝統的な3要件
|
①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること ②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること ③一般の人々に未だ知られていないことがらであること ↓ このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えた場合は法的救済あり |
2-2 近時の最高裁判例
もっとも、最近はこのような3要件にこだわらない判例も見られるようになりました。
- 長良川報道事件(最判平成15年3月14日)
「プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するのであるから…、本件記事が週刊誌に掲載された当時の被上告人の年齢や社会的地位、当該犯罪行為の内容、これらが公表されることによって被上告人のプライバシーに属する情報が伝達される範囲と被上告人が被る具体的被害の程度、本件記事の目的や意義、公表時の社会的状況、本件記事において当該情報を公表する必要性など、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を個別具体的に審理し、これらを比較衡量して判断することが必要である。」
近時の判例
|
【判断枠組み】 ①その事実を公表されない法的利益 ②これを公表する理由 を比較衡量 ↓ ①が②に優越する場合に不法行為成立
【考慮要素】 ・当該私人の年齢や社会的地位 ・当該犯罪行為の内容 ・公表によって情報が伝達される範囲 ・当該私人が被る具体的被害の程度 ・本件記事の目的や意義 ・公表時の社会的状況 ・本件記事において当該情報を公表する必要性 |
このように、近時の最高裁判例は「その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する」という枠組みを定めた上で、比較衡量においては個別具体的な事情を総合的に考慮する方法を採用しています。
第3章 ヘイトスピーチ
この章では、表現行為とヘイトスピーチとの関係について解説します。
3-1 ヘイトスピーチとは何か
ヘイトスピーチについて、法律上明確な定義はありません。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の前文では、「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽せん動する不当な差別的言動」という表現が用いられているため、これを一応の定義と考えることはできますが、何が「不当な差別的言動」であるかは不明です。
そこで、地方公共団体の条例を参照してみましょう。
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
(定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2(略)
このように、大阪市の条例では、
- 表現活動の目的
- 表現の内容又は表現活動の態様
- 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態
の3要件を採用しています。
では、ヘイトスピーチと名誉毀損の何が違うのかというと、ヘイトスピーチは特定の個人を対象としない表現も含まれます。
|
名誉毀損 →特定の個人の名誉を毀損することが必要
ヘイトスピーチ →民族全体などの、不特定多数の人々を対象とする表現活動も含まれる |
このように、ヘイトスピーチは範囲が広いので、表現の自由との調整も問題となりやすいのです。
3-2 最高裁の合憲判決
先ほど紹介した大阪市の条例について、最高裁で合憲判決が言い渡されました。
- 大阪市ヘイトスピーチ条例事件(最判令和4年2月15日)
「条例ヘイトスピーチに該当する表現活動のうち,特定の個人を対象とする表現活動のように民事上又は刑事上の責任が発生し得るものについて,これを抑止する必要性が高いことはもとより,民族全体等の不特定かつ多数の人々を対象とする表現活動のように,直ちに上記責任が発生するとはいえないものについても,…これを抑止する必要性が高いことに変わりはないというべきである。加えて,市内においては,実際に上記のような過激で悪質性の高い差別的言動を伴う街宣活動等が頻繁に行われていたことがうかがわれること等をも勘案すると,本件各規定の目的は合理的であり正当なものということができる。
また,本件各規定により制限される表現活動の内容及び性質は,上記のような過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られる上,その制限の態様及び程度においても,事後的に市長による拡散防止措置等の対象となるにとどまる。そして,拡散防止措置については,市長は,看板,掲示物等の撤去要請や,インターネット上の表現についての削除要請等を行うことができると解されるものの,当該要請等に応じないものに対する制裁はなく,認識等公表についても,表現活動をしたものの氏名又は名称を特定するための法的強制力を伴う手段は存在しない。
そうすると,本件各規定による表現の自由の制限は,合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものというべきである。」
このように、最高裁は、「民事上又は刑事上の責任が発生し得る表現活動」を抑止する必要性が高いことはもちろんのこと、「民族全体等の不特定かつ多数の人々を対象とする表現活動のように,直ちに上記責任が発生するとはいえないもの」についても「これを抑止する必要性が高いことに変わりはない」としました。
特定の個人への名誉毀損が規制されるのは当然ですが、それだけなく不特定多数の人々へのヘイトスピーチも抑止する必要性が高いと判示した点に意義があると考えられます。
第4章 まとめ
今回は、
- 名誉毀損
- プライバシー侵害
- ヘイトスピーチ
について解説しました。
名誉毀損は
- 「公共の利害に関する事実」であること
- 「その目的が専ら公益を図ることにあった」こと
- 「真実であることの証明があった」こと
を満たすと罪が成立しません。
「真実であることの証明があった」ことが認められなくても、
- 「その事実を真実であると誤信」したこと
- 「確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある」こと
が認められる場合も犯罪の故意がないと認められます(相当性の法理)。
事実を摘示しない批判の場合、
|
ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明である ↓ 【違法性が否定される場合】 ①公共の利害に関する事実に係る ②目的が専ら公益を図ることにある ③人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない ④前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった
【故意又は過失が否定される場合】 ①~③は同上 ④前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明がない ⑤重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由がある |
となります(公正な論評の法理)。
プライバシー侵害は、伝統的には
|
①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること ②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること ③一般の人々に未だ知られていないことがらであること ↓ このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えた場合は法的救済あり |
という3要件が挙げられていました。
これに対し、近時の判例では、
|
①その事実を公表されない法的利益 ②これを公表する理由 を比較衡量 ↓ ①が②に優越する場合に不法行為成立 |
という判断枠組みに基づき、個別具体的な事情を総合考慮する方法が採用されています。
ヘイトスピーチは、名誉毀損とは異なり、特定の個人を対象としない表現も含まれます。
令和4年最高裁判決では、大阪市のヘイトスピーチ条例が合憲とされました。
この記事では、初学者の方にもわかりやすいように、一般的な考え方をざっくりと解説しています。
判例などの詳細な解説や、実践的な答案の書き方を知りたい方は、ヨビロン憲法のテキストをご購入いただけると幸いです。


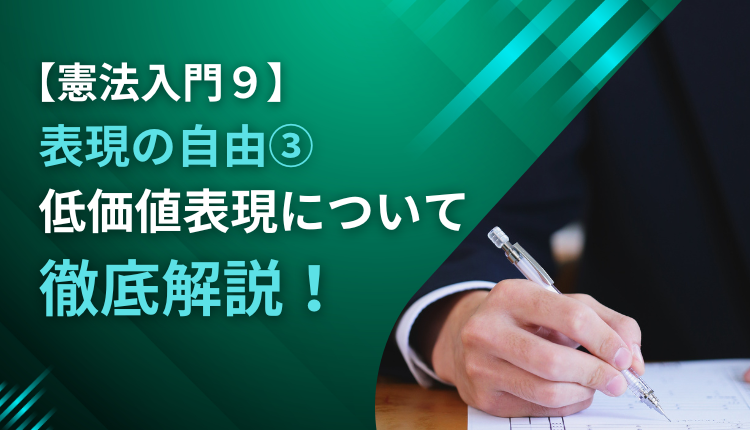
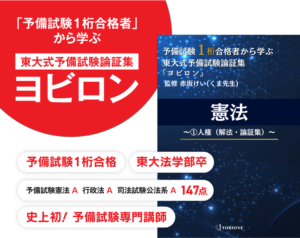



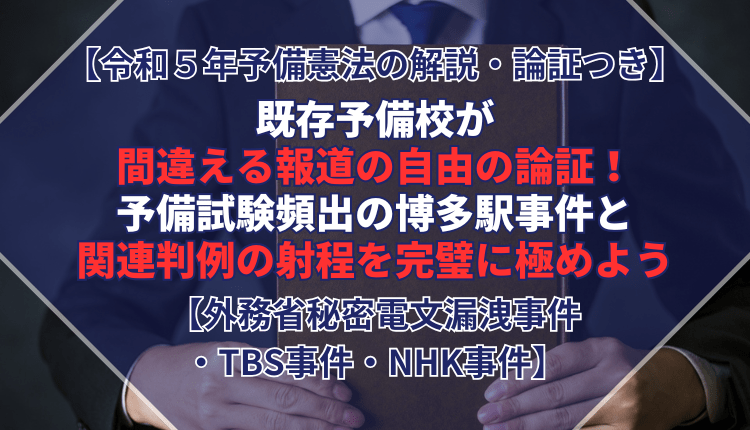
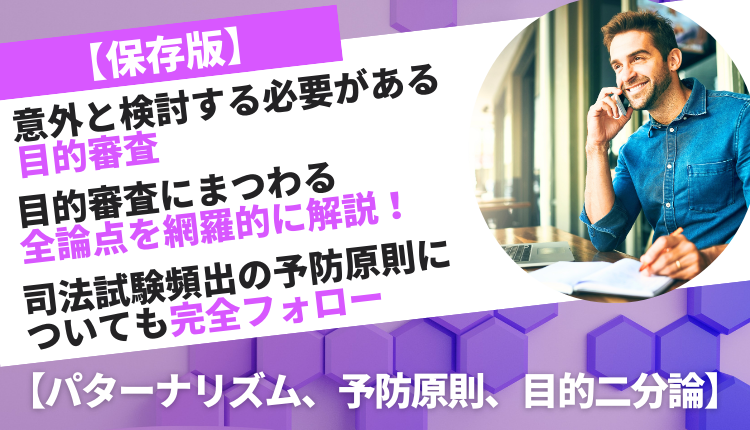
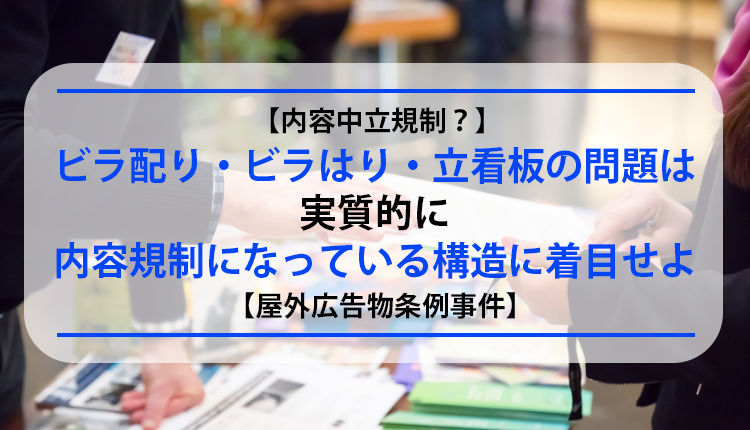
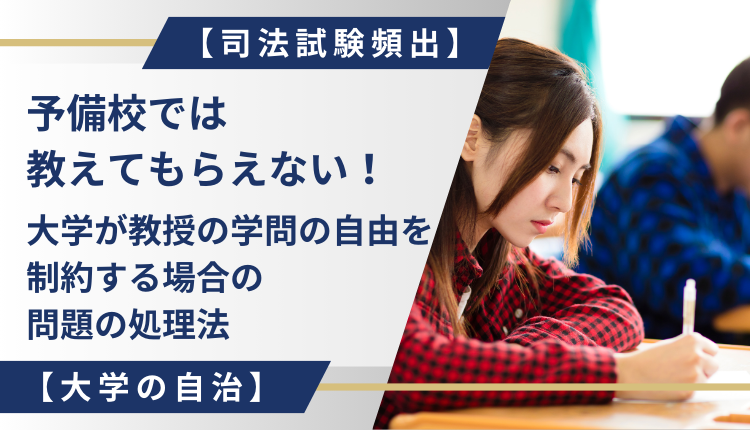

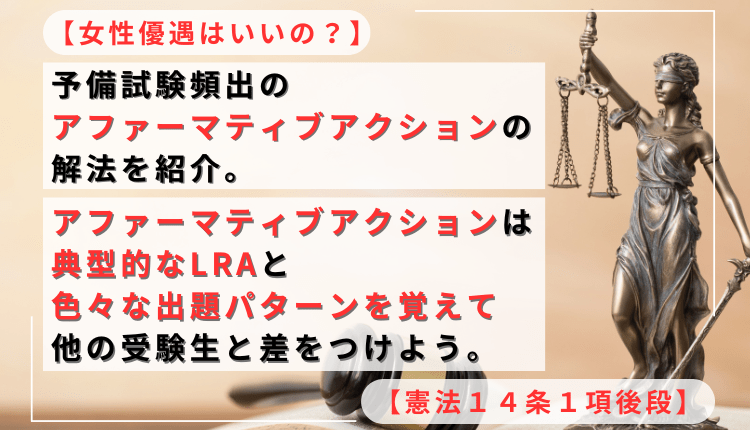
コメント